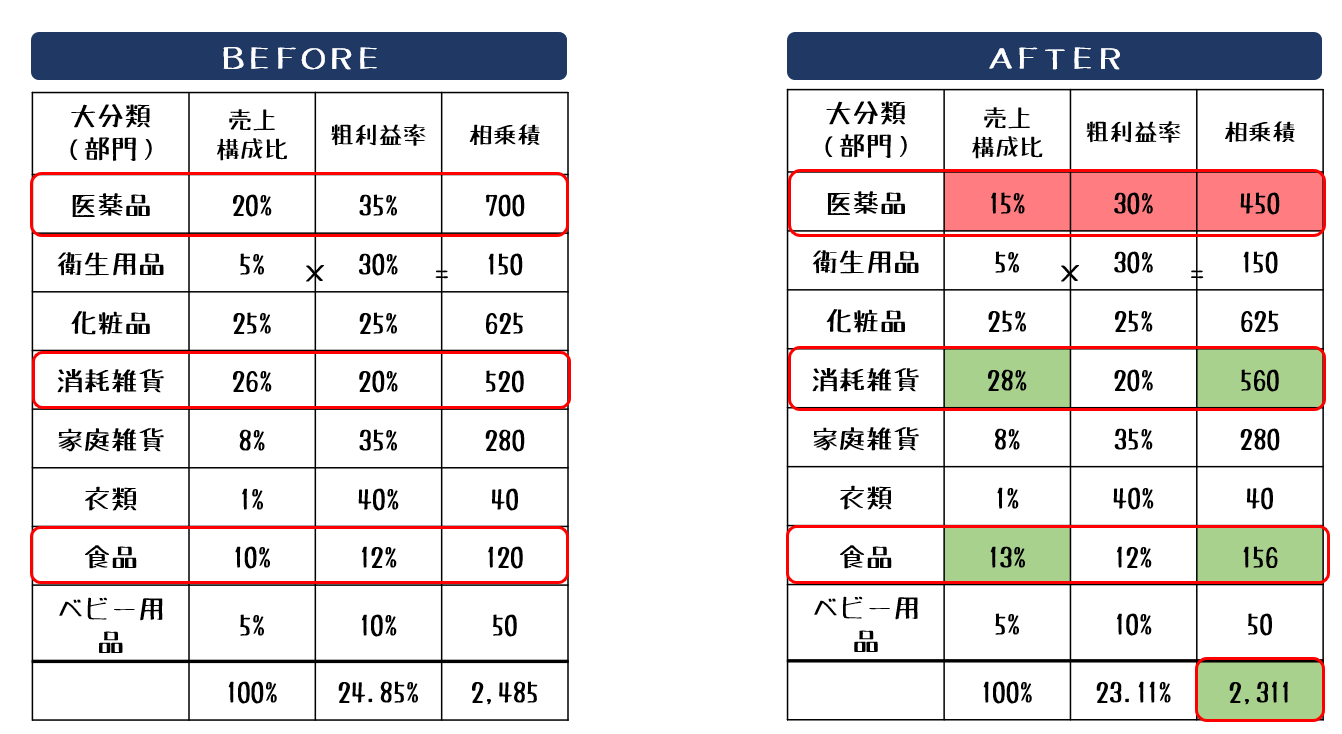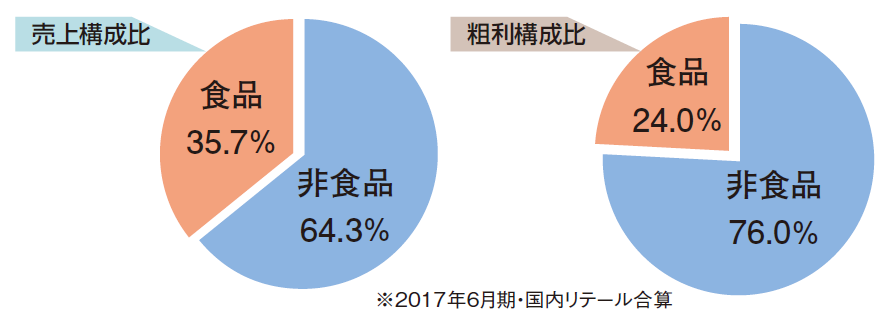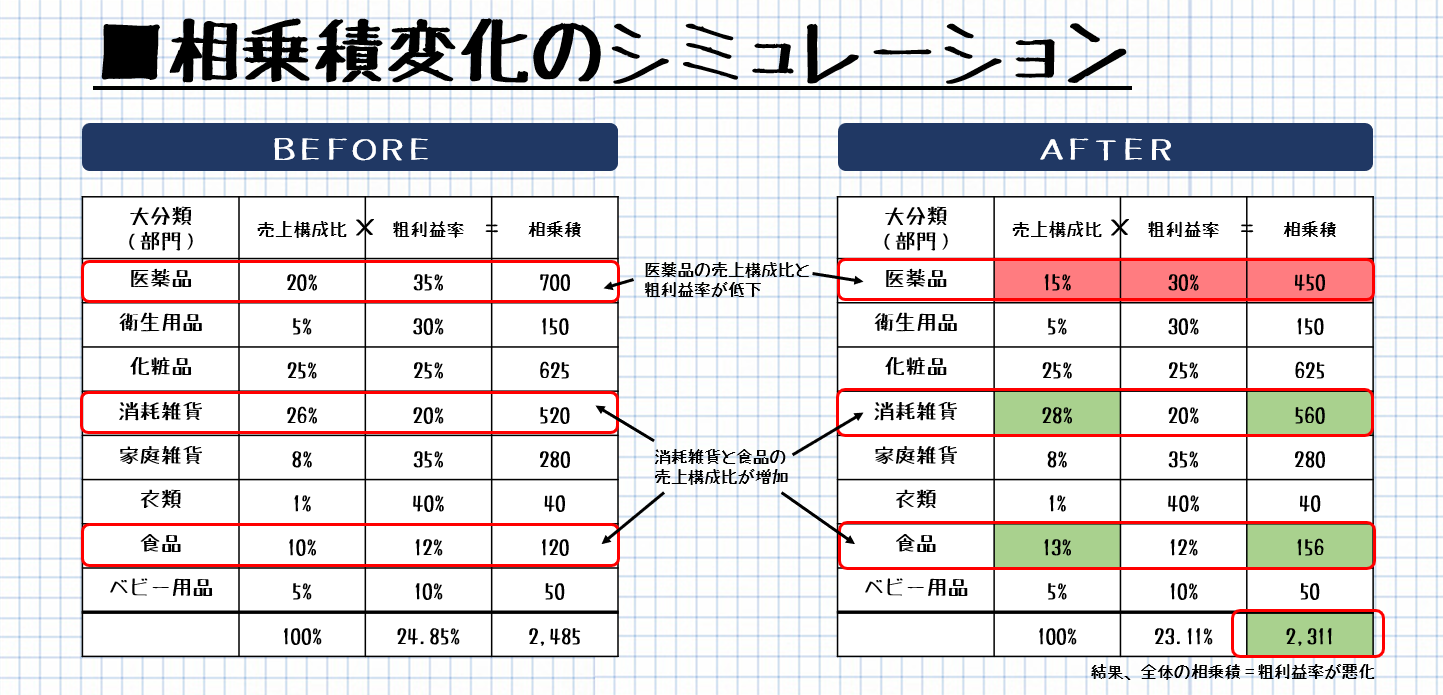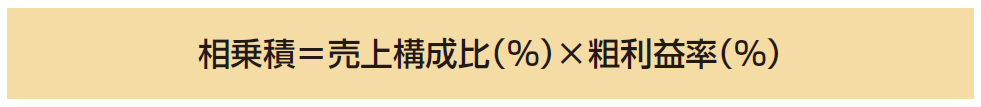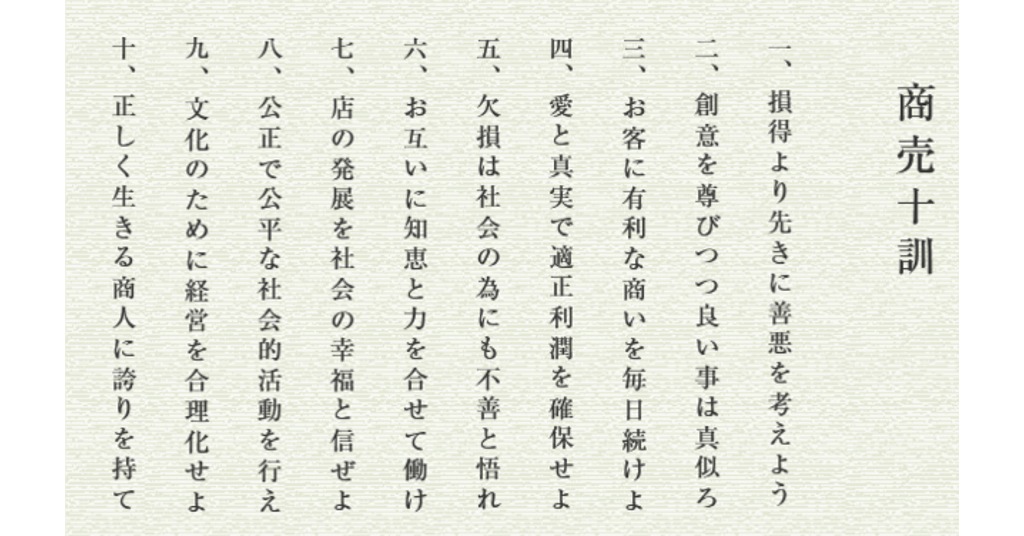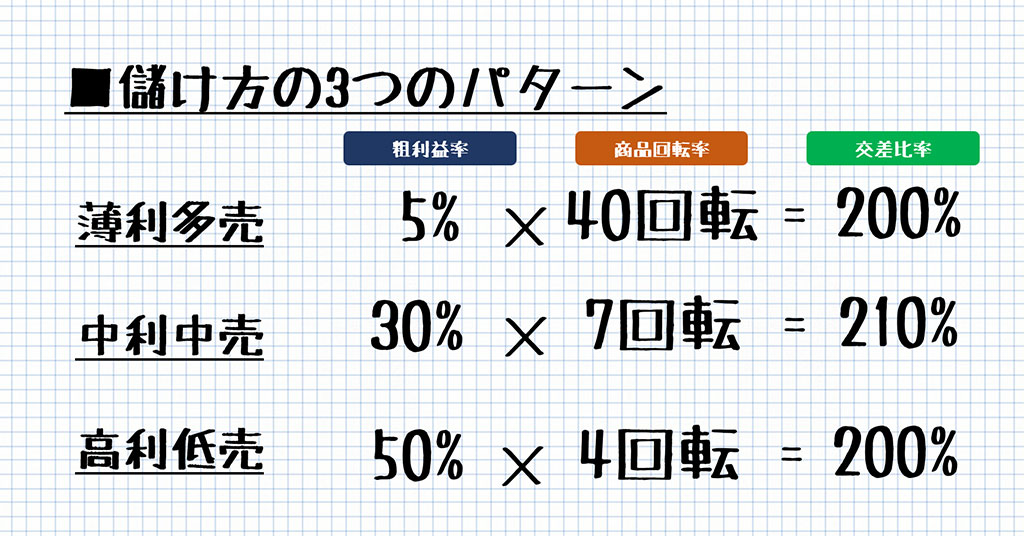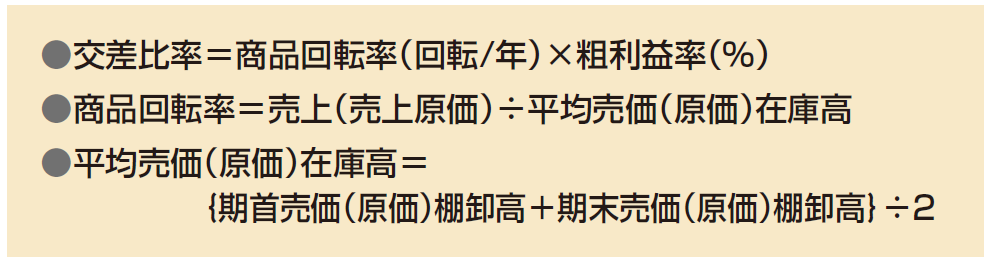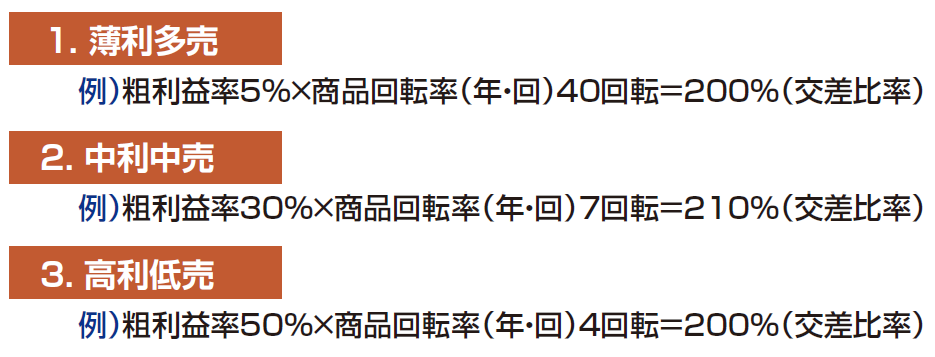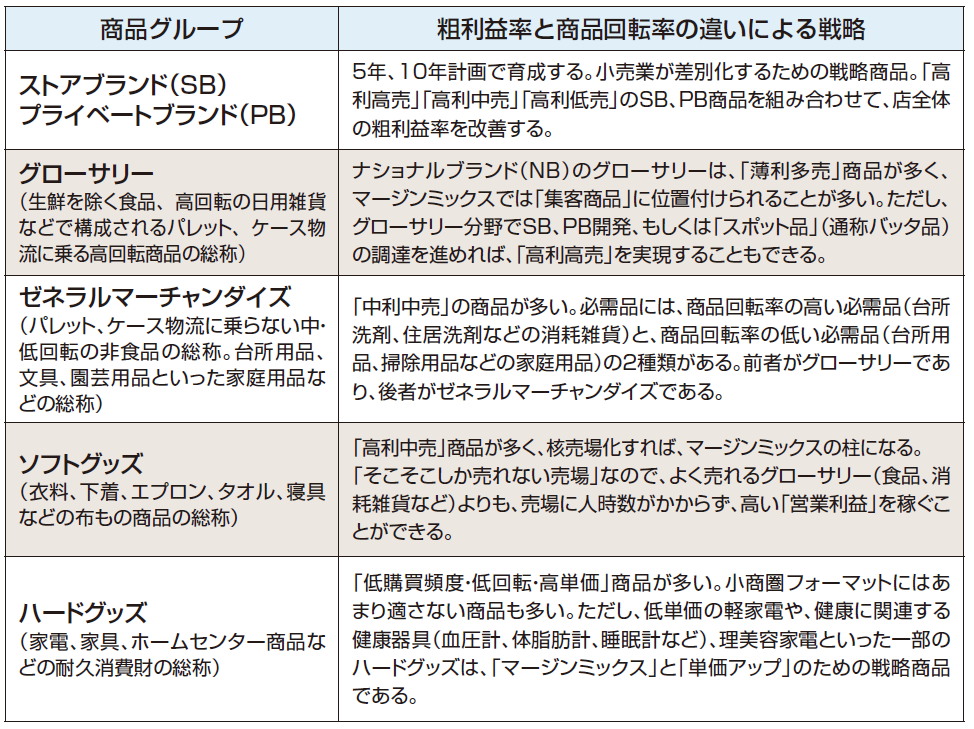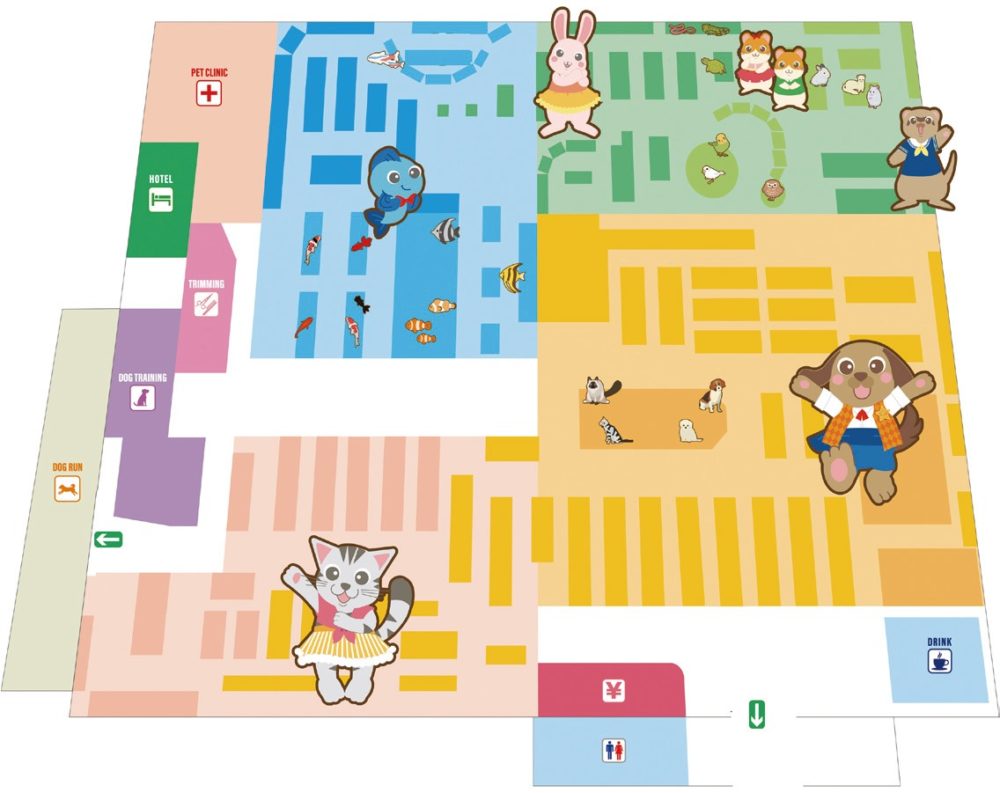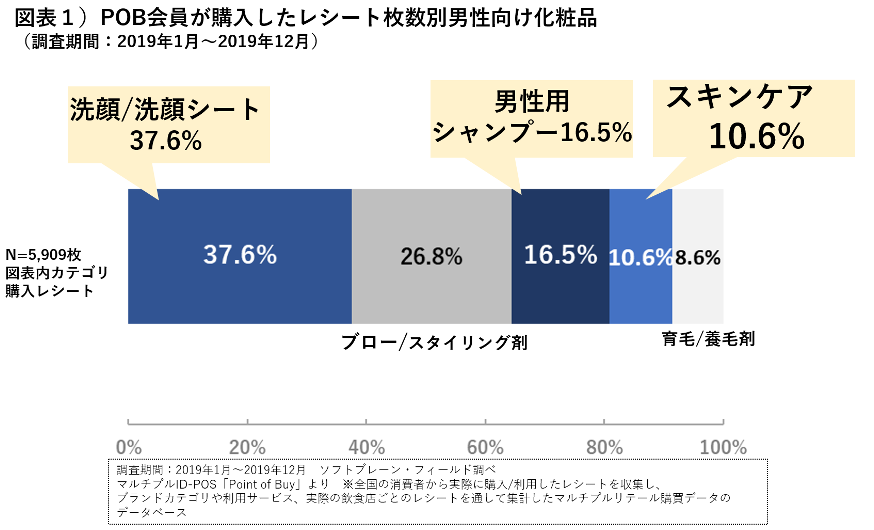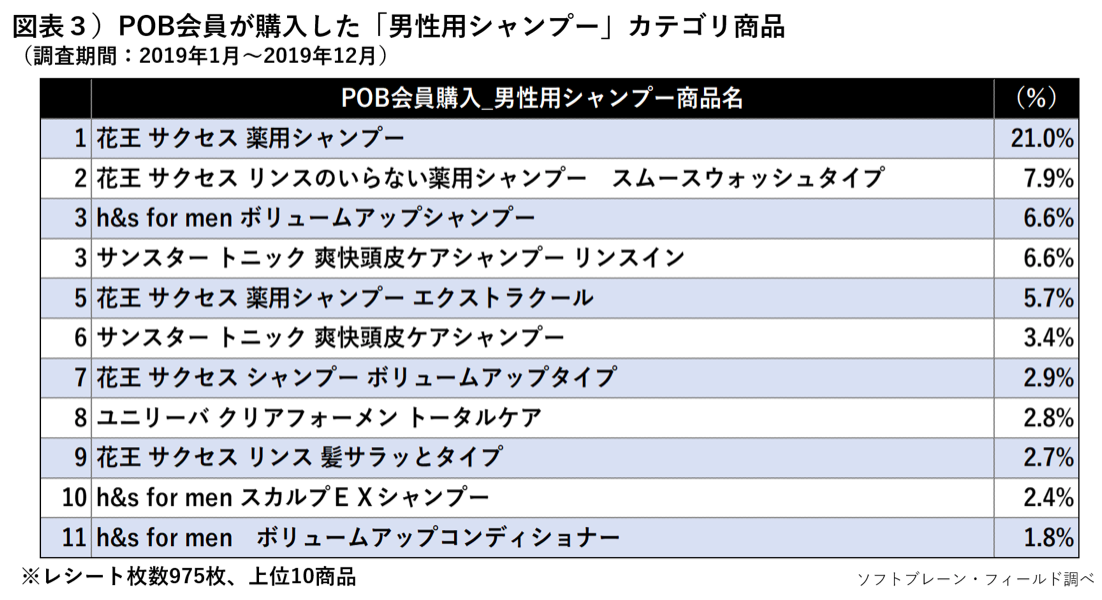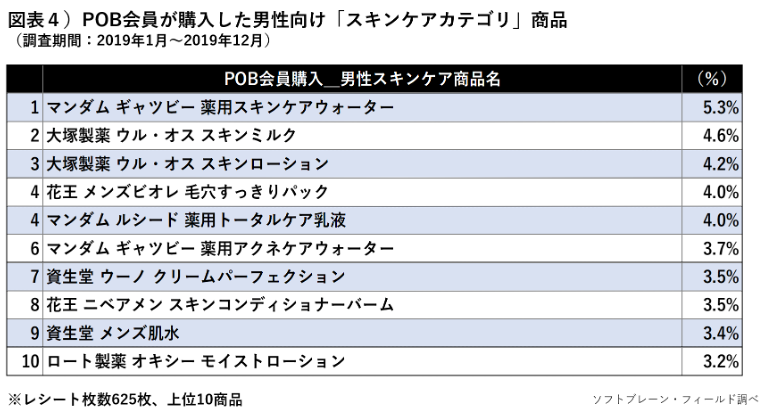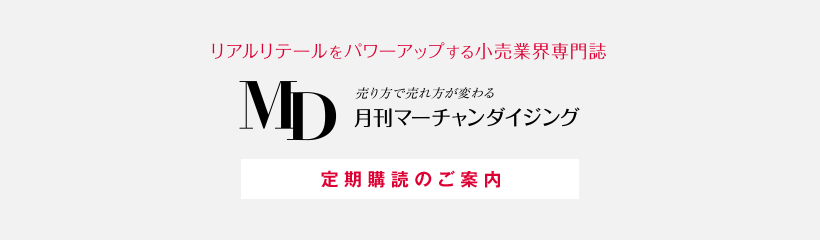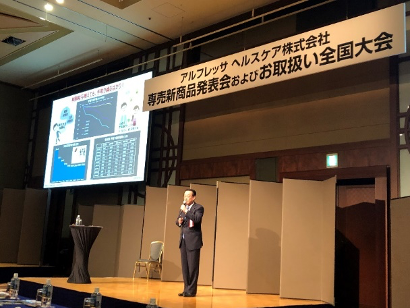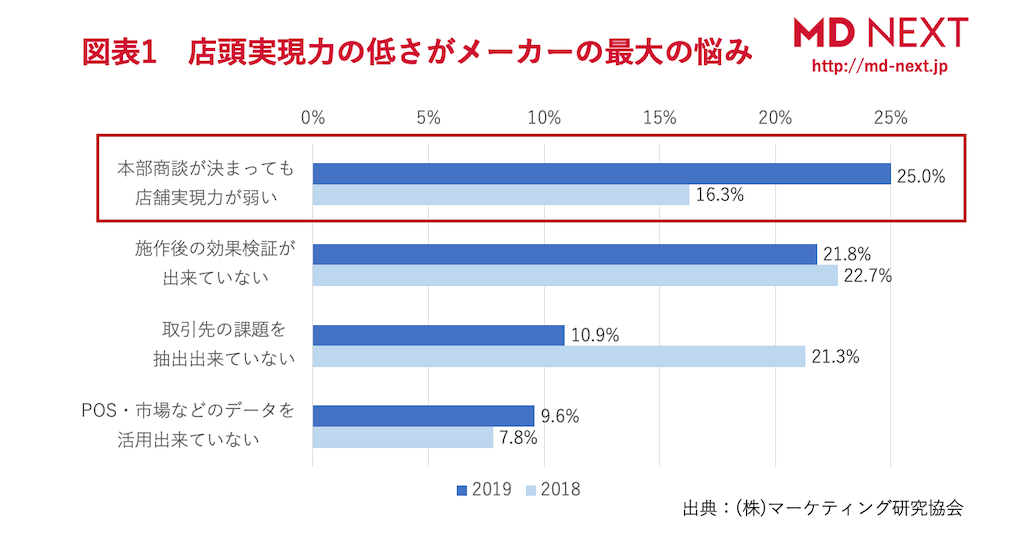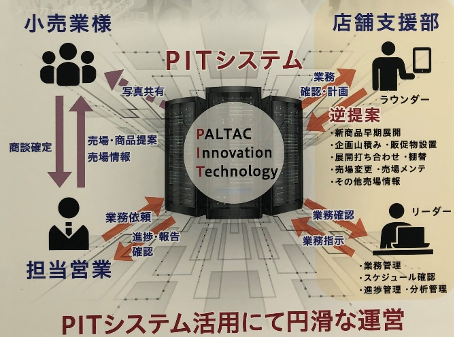AIカメラの活用、タブレットカートの導入など、リアル小売業の「デジタル革命」に果敢に挑戦しているトライアルホールディングスの亀田晃一社長に、変貌する小売業の未来を聞いた。(聞き手:本誌主幹 日野 眞克/月刊マーチャンダイジング2020年2月号より転載)
人口減少で日本は生産性革命待ったなし
──現在の日本の流通業を取り巻く「環境変化」についてお聞かせください。
亀田 われわれは、「短期的な環境変化」よりも「長期的な環境変化」を重視しています。長期的な環境変化の第1は、日本の人口減少と高齢化(GDP成長率の低下)です。人手不足により人件費が高騰しますので、IoT(Internet of Things すべてのモノがインターネットでつながる社会)・AI(人工知能)を活用した労働生産性の向上は待ったなしの経営戦略です。
GDP成長の約半分は、人口ボーナスによるもので、生産性改善は半分だといわれています。日本は2060年に人口が現在の3分の2になるといわれています。「人口ボーナス」はもはやない国なので、生産性を高めなければ成長できないということが、日本の小売業として考えなければならない事実ですね。
人手不足のなかで優秀な人材を確保するためにも、働き方改革による待遇改善は不可欠です。また、小売業の生産性向上のためには、専門性の高い人材を確保する必要があり、そうした専門的人材には高水準の報酬を支払うことも重要です。そういう人材は従来の小売業の企業文化とは異なるので、分社化によるIT・AI人材の確保も必要になるとおもいます。
長期的な環境変化の第2は、「100年に一度の基幹技術の革新」という大変化が起こることです。2000年代前半から、世界は第4次産業革命(インターネット・AI革命)の中にいますが、1960年代から発展した日本のチェーンストア産業は、第4次産業革命に乗り遅れ、この半世紀まったく進化できていません。その結果、日本の小売業の生産性はきわめて低い状況です。
AI、IoTなどの技術を活用したデジタル化によって、小売業の仕組みを変革する「デジタルトランスフォーメーション(DX)型」の小売業への進化が必要です。
──トランスフォーメーションという言葉が出ましたが、「小売業の在り方」を根本から見直す時期に来ているということですか。
亀田 これからは「単純な安売り」は成り立たなくなっていきます。人件費の高騰、建築費の高騰、物流費も高騰しています。当然、店舗運営のコストも高騰し、これまでの単純なディスカウントはできなくなってきます。当社でも、平均年率3~4%人時単価が上がっています。これに対応できるだけの生産性の改善を進めなければ、間違いなくコストを吸収できなくなります。
現在、「店舗の在り方」「運営の仕方」をもう一度、根本的に見直そうと考えています。デジタルの世界だけを捉えると、1990年ぐらいから劇的な変化が起きています。
ただし注意しなければならないのは、店舗という資産があるなかで、すべての店舗を一気に変化させるのはできないということです。新店や、投資回収の終わった店舗から順次変えていく必要があります。
当社の社内では「レトロフィット」という言葉をよく使います。いまある既存設備と適合させて新設備の導入を図ることを優先するという意味です。当社が実験している「AIカメラ」も「レジカート」も、既存のオペレーションにプラスオンしたデバイスですので、既存の小売業にも導入しやすい機器だとおもいます。
リアル小売業は、Amazonとは異なり、「店舗運営優先」の技術導入が先だとおもいます。少しずつ変化しながら、すべての小売業が第4次産業革命の恩恵を受けられるのは10年以上先の話かも知れません。
パートナーとの協働でデジタル革命を推進
──御社が参画している「リテールAI研究会」などで、多くの企業と協働して、小売業のデジタル化を進めようとしていますね。
亀田 Amazonのような巨大企業のように、一社でサプライチェーン全体を再構築することはできません。だから当社は、多くのパートナー企業さんと協働することを重視しています。
メーカー、卸、小売、物流、メディア、金融、システム、ファシリティなどの、ビジョンを共有できる有力企業さんとの協業を図り、効率的なサプライチェーンを構築できればいいと考えています。
たとえば、冷蔵庫の外付けのデバイスなどで、ある程度の実験結果が出始めた技術を「フクシマガリレイ」さんと共同で開発しています。店舗内の棚や冷蔵・冷凍ショーケースは、老朽化するなかで、新しい技術に置き換わっていきますので、それを設備機器メーカーさんと一緒に進めています。
また、物流に関しても、低温物流に強みを持つ「ムロオ」さんと協働して、デジタル時代の新しい物流システムを構築しようとしています。
メーカーさんとの協働に関しても、ジョイント・ビジネス・プラン(JBP)という手法を使って、当社の販売データ、顧客データをメーカーさんや卸売業さんに提供して、「新しい売り方」や「カテゴリー創造」を製配販で協働して変革する試みも継続的に実施しています。
JBPによる協働では、メーカーさんの営業部門だけでなくて、本部のマーケティング部門の担当者とも取り組んでいます。「リベートを渡すから売ってくれ」という従来の商談から脱却したいと考えています。
また、「リテールAI研究会」には、ドラッグストア(DgS)さんなどのほかの小売業も参加しており、小売業のデジタル化に関して共同で研究しています。当社が実験中の「AIカメラ」も、当社一社で導入するよりも、多くの企業さんに採用してもらえれば、1台当りの費用が下がります。インフラはともに使おうという考え方です。
銀行さんとは「小売」と「決済(金融)」の新たな連携方法を模索しているところです。当社はいま流行の「キャッシュレス還元」よりも、「本質的なキャッシュレス化」への対応を検討しており、「自社プリペイドカード」を軸に低コストの決済方法を銀行さんと一緒に研究中です。
浮動客よりもロイヤルカスタマーを重視
──以前取材させていただいた「新宮店(新宮町)」では、「AIカメラ」や「タブレットカート」などの新しいIT技術を導入していましたね(写真1、2参照)。
亀田 当社もまだすべて実験段階です。とにかくいろんなことに挑戦しています。「AIカメラ」は、人間が目視で確認していたものは、カメラで代替できるようになっています。カメラで「欠品状況」を見たり、「棚割」を見たり、棚前のお客さまの「購買前行動」を見ることができるようになり、そのビッグデータを分析できる時代になっています。
棚前の購買前行動データは、JBPの取組みのなかでメーカーさんに提供し、売り方や棚割の改善につなげればいいと考えています。
これからの小売業は「省人化」を進めていく必要があり、新宮店ではレジ作業を大幅に省人化する「タブレットカート」を導入しました。しかし、タブレットカート導入の目的は、省人化だけではなくて、お客さまの「買物体験」の質の改善も重要な目的です。
当社のハウスカードをスキャンしてからタブレットカートの買物はスタートし、お客さまが商品をタブレットカートでスキャンしながら店内を回遊します。お客さまのIDが特定されているので、お客さまのパーソナルな購入履歴や属性に基づいたパーソナルクーポンを画面に表示したり、「リコメンド機能」でおすすめ商品を表示することもできます。将来的には、販促がよりパーソナル化していくことは間違いないとおもいます。
[写真1]新宮店では、「タブレットカート」を実験している。目的は、レジ作業の省力化と、顧客データに紐付いたパーソナルクーポンなどのワンツーワンマーケテイングの実験。 [写真2]新宮店では天井に設置されたAIカメラで、顧客の購買行動と、棚の状態の可視化を進めている
亀田 そうです。当社がいままでできなかったことは、本当にトライアルを愛してくれている「ロイヤルカスタマー」に対する特別な対応です。デジタル化によって、プリペイドカードやID-POSデータで、個人のIDを確認できるようになりました。また、AIカメラを使って、個人の属性を特定することもできるようになってきました。
ID特定ができると、当社の「ロイヤルカスタマーがだれなのか」がわかります。これまでは、チラシ販促などで、ロイヤルカスタマーもバーゲンハンターもだれでも万遍なく、同じディスカウント価格で集客していました。
しかし、これからは、ロイヤルカスタマーの購買履歴や属性に合った「特別な販促」をワンツーワンで提供できるようになります。
タブレットカートによる販促の個別化の成果が出るのは、まだこれからです。いま、お客さまがタブレットカートに価値を感じてくれているのは、リコメンド機能よりも、合計金額が見えるとか、決済をレジ待ちせずにできる省力化と便利性の部分です。
当社のタブレットカートは、海外も含めて多くの小売業さんが見学に来られますが、皆さんが驚かれるのは「利用率」の高さです。平均で来店客の40%がタブレットカートを利用しています。これは世界的に見ても高い利用率だとおもいます。
まだ小ロット生産なので、投資回収できる段階ではないのですが、手応ええを感じていることは、「お客さまの購買体験は変わったよね」「利用者は増えているよね」ということです。
──ロイヤルカスタマーとの関係性の強化に取り組んでいこうとしているわけですね。
亀田 ロイヤルカスタマーの関係性の優遇(エンゲージメント)に取り組んでいきたいとおもいます。短期的な浮動客相手ではなくて、固定客の長期的なライフ・タイム・バリュー(LTV)の向上をベースにした経営に転換していきます。
タブレットカートを利用してもらうと、お客さまの購買情報の詳細がわかります。だれが購入したかがわかり、お客さまの購入の順番がわかり、買物時間もわかるようになります。
また、ネット販売が画面のサイズだけの情報提供に対して、「タブレットカート+店全体」で、お客さまの五感に訴えるような情報提供を強化しています。
だから、サイネージによる情報発信も増やしています。五感で体感できるのがリアル店舗の強さですね。実際にリアルの商品がそこにある。全方位で見える、取って触れる、試食できるという体験価値を演出できるのはリアル店舗の最大の強みだとおもいます。当社では「ショールーム」としてのリアル店舗の空間価値と体験価値を向上していき、「リアルの強み」と「デジタルの強み」の融合を目指します。
トレーサビリティ(生産→物流→店舗→廃棄までの追跡システムのこと)を可視化できることもリアル店舗の新しい買物体験ですね。デバイスでバーコードリーダーを読めば、生産者の顔が見えて、取れた場所がわかって、生産方法がわかるなどの情報提供も可能になります。その情報価値によって購買行動は変わります。
とくに、POPよりも伝達能力の高い「動画」による情報発信をもっと店頭で強化したいですね。これからは「店舗のメディア化」の可能性は大きく広がっていくとおもいます。
–続きは月刊マーチャンダイジング2020年2月号でご覧ください。
・ワンツーワンの時代に売場で何を工夫しているのか?
ご購読は以下のバナーから。