海外では店舗を物流拠点に位置付ける事例も
──物流と聞くと、漠然としていて捉えづらい印象もあります。最近は有店舗、無店舗が入り乱れているというのも理解を難しくしているようです。私たちは物流という観点からはどのように分類して理解すればよいのでしょうか。
西尾 いわゆる「物流」というと、一般的には最終消費者の手に届く「ラストワンマイル」とおもわれがちですが、実はその工程はチェーンのように長く、階層も深いものです。
物流を分類するときに、明らかに作業の質が違うのは、「最終消費者に届けるための機能を有する物流」か「物流センターや店舗に分配する物流」かというところです。ですから、実店舗を運営している企業の物流なのか、無店舗・通販なのか、あるいはそのハイブリッドなのか…というのが物流の種類を分類するカギになりますね。
昨今の小売業の物流トレンドとしては、実店舗を物流拠点としてどう位置付けるかが話題になっています。アメリカや中国は一歩進んでいて、店舗を在庫保管拠点として位置付け、そこから最終消費者まで商品を運ぶというような取組みも進んでいます。(※編集部注:マイクロ・フルフィルメント・センター、MFCと呼ばれる)
日本でもそのようなことに挑戦している企業もありますが、取り扱っているのがコモディティ中心で、単価が低いため、利益の大半を配送費で食いつぶしてしまうという問題があり、ビジネスとして成立させるのは非常に難しい状態です。
わかりやすくいえば、コンビニで1本100円のジュースやおにぎりをお客さまのご自宅までお届けするのに、どれぐらいの費用がかかるのか…という話で、構造的にはどう考えても赤字になってしまいます。
一方で、「〇円以上送料無料」というように、送料無料となる購入金額を設定する方法もあるんですが、「そもそもコンビニで5,000円も買うか?」という問題になってきてしまいます。
ネットスーパーのようなモデルは世界を見渡してもまだ成立しづらい状況です。とはいえ、自宅に配送を行って、成立しているモデルもあります。たとえば都心で配達を中心に規模を拡大しているカクヤスさんのように、商品単価が高いアイテムを取り扱っていて、都心で高密度に配送すればよいというモデルです。
──昨今ではBOPIS(Buy Online Pickup In Store)に取り組もうとする企業も増えてきました。
西尾 弊社では小売業の物流センター設計の支援をさせていただいているのですが、物流を設計をするのに、ネットやアプリから注文された商品をどうやってお客さまに店頭でお渡しするのかということまで加味して設計をしています。ですから、必ずしもお客様のところまで届けに行くことがすべてではないということです。
人の介在とリードタイムをゼロにする潮流
──世界的に、物流の潮流というのはどういう方向に進んでいるのでしょうか。
西尾 確実に挙げられる世界的な動向は2つあります。
ひとつは商品配達までのリードタイムをゼロにしていくという流れ、もうひとつは人間の介在をゼロにしていくという流れです。
まず配達までのリードタイムをゼロにするという点です。ECでは、ここしばらく「注文翌日配送」や「受注1時間後に配送」など、注文から配送までのリードタイムをゼロに近づけるための努力が進んでいました。しかしその動きはいったん緩和されているようにもおもいます。
もちろん、お客さまに買った瞬間に手元に届けてほしいというニーズはあるものの、そこに労働力が追いつかず、コストも合わないという状況です。さらにこの数年で、「そこまではしなくてもよい」と消費者のマインドがやや変わったように感じています。とはいえ、購入してから到着まで5日、10日かかるのはちょっと長すぎるので、各社適切なリードタイムを模索している状況といえます。
もう一点が自動化の流れです。世界各国で自動化の流れは出てきていますが、全自動がいいのか、人の作業を一部残した方がいいのかという「自動化の程度」についてはまだ答えが見つかっていません。
これは私の推測ですが、Amazonは明らかに人間の介在を物流工程に残しています。物流の設計から人のよさと機械のよさをうまく使い分けようとしているのが感じ取れて、彼らは全自動となることをよしとしていないように感じます。
一方、中国の企業は「全自動の物流センターを立ち上げました!」と華々しくアピールすることも少なくありません。中国EC大手企業「京東集団(JD.com)」は、2017年に全自動倉庫の設立をリリースしました。全自動の未来が来たと、関係する企業は色めき立ったのですが、それ以降とんとそのニュースを聞かなくなりました。ある種宣伝的な位置付けで設計した物流だったのではないかとおもっています。
日本の物流自動化を妨げる「こまやかな対応」
西尾 日本の自動化はきわめて遅れている状況です。これには日本特有の「こまやかな対応」が関係しています。アメリカや中国の物流機器メーカー、物流システムメーカーは「俺たちの提供するサービス・プロダクトはこうだ。使いたいのであれば、御社の業務を仕組みに合わせるべきだ」というスタンスを崩しません。
日本は逆で、物流機器メーカー・システムメーカーは「御社では一体どのように業務を進めていらっしゃるのですか? それに全部きめ細かに対応させていただきます」というスタンスです。
結果、日本の物流の現場は、各社各様という状況に陥っています。ホームセンターであれば、カインズ、ビバホーム、ホーマックでは同じような物流作業でいいのではないか、とおもいますが、それぞれの企業がそれぞれ特殊な仕事の仕組みを持っていて、同じ物流の設計では対応できません。
自動化にとってもっとも重要なのは業務の標準化なのですが、同じXという商品を「Aというお客さまに納品するときにはこういうラベルをここに貼る」、Bというお客さまに納品するときには「違う印刷のしてあるこういうラベルを別の場所に貼る」…という個別対応が必要になってきてしまうんですね。
これまで私は、膨大な「うちの現場は特殊で、自動化に向いていないです」と、自動化を見送るケースを見てきました。
これは日本らしいといえば日本らしいのですが、日本が強みとしてきたきめ細かなサービスが、自動化やシステム化の前では足を引っ張ってしまっているわけです。自動化という局面では、日本企業は苦しんでいる状況といえます。
──Amazonはまだ人のよさを残そうとしているとおっしゃられましたが、なぜなのでしょうか。特殊なオペレーションに急に対応できるとか、特殊な荷姿の商品にも対応しやすいという点なのでしょうか。
西尾 たとえば判断をしながら行う検品作業は機械にはできなくて人間でなければ対応ができません。お客さまが買ったこのAという商品と、こちらのBという商品は同じものを指しているととか、箱がへこんだ商品を値引きして販売するべきか、これぐらいならそのまま出荷しても大丈夫と考えるか…だとか。現時点では、このような現場で起こる事象を機械で画一的に判断するのは難しいんです。
人間の方が状況に応じた対応をすることができるので、検品検査は人間が頑張ってやっている分野ですね。
もう一点は、波動対応のようなものです。1日に機械で処理できる荷物の分量というのは上限が決まってしまいます。ですが、ブラックフライデー&サイバーマンデーのように、受注が跳ねるタイミングがあり、それをすべて機械に対応させようとすると、オーバースペックになってしまいます。
ですが、低めに設定してしまうと、急に入荷・出荷量が跳ねたときに対応できません。この波動対応は機械が苦手な部分なので、人がそのときどきに応じて処理する必要が出てきます。
──日本特有のこまやかなサービスのせいで自動化が進んでいないとおっしゃられていましたが、それは強みといえるのでしょうか。
西尾 これは非常に難しい問題なのですが、私はそういった考えは捨てるころ合いに来ているのではないかとおもっています。現場が回せなくなってきたからです。現場でいろいろなご用聞きを続けていた結果、そのしわ寄せが個別性を生んできました。
個別性があるということは、それぞれの現場に「匠」がいるということです。
定型化しづらい作業、標準化しづらい作業を匠が抱えていたのですが、その匠がどんどん定年退職しています。標準化しておかなければ量をさばくことができません。匠を抱え込んでおければいいのですが、今後人口が減少する世の中ではそれも難しくなってくることでしょう。
ある程度作業を標準化し、人間の判断をなるべく減らすようなプロセスを構築しないと、とくに物流関連の企業は永続的に企業活動を続けていくことが難しくなってきています。人手を集めて匠の世界でやっていくのはもはや限界です。
モノタロウは「買い手に対する解像度」が高い
──西尾さんが立ち上げに関わられていたモノタロウの物流については、非常に評価が高いですね。その秘訣をご自身ではどのように分析なさっていますか。
西尾 物流は、それそのものが主役になることはないと、個人的にはおもっています。どのような販売戦略を取るのか…つまり、だれにどのようなリードタイムで、どんなふうに商品を提供するのか…という意思があり、それに合わせて設計されるべきものです。
それで、モノタロウの物流をご評価いただいているのであれば、そもそも会社としてその物流設計の前段階である「買い手に対する解像度の高さ」が理由なのではないかとおもいます。
Amazonや楽天のように、一般消費者向けのECサイトは、衝動買い的に「欲しい!」とおもって、ポチッと購入することが多いとおもいますが、モノタロウのお客さまは小さな町工場のような事業者さんがとても多いんです。
このような方々は、「この部品は摩耗するから年に1回、毎年1月に交換しよう」というように、計画的な購買をされていたり、一方で、「今日作業をしようとしたら、このパーツが足りない!」といって慌てて購入されるようなケースもあります。
企業であれば平日の日中は必ず人がいるから時間帯指定はいらないかもしれません。このような、買い手に対する理解が深く、買い手の方に対して「お客さまがこういうことを求めているなら、こんなふうに届けよう」と、販売側から展開されてくる要件を、物流でどう実現するのかを考えるのが私たちの仕事でした。
そのためには「どの配送会社にお願いしようか」「配送料はいくらぐらい?」「拠点の立地はどこ?」…などを検討します。商品も、小さなねじから物干しざおまで取り扱いますから、どこまでを自動化の対象にするのか、緻密に考えて設計する必要がありました。
モノタロウの物流は、まずお客さまを正しく理解して、その方たちに価値を提供するための物流であるという考え方が、わりと明確だったのではないかと思います。
──お客さまの解像度の高さというのは意識してそうなさっていたということでしょうか。
西尾 そうですね。私の管轄外の業務なので私の個人的な認識にはなりますが、通販の会社だからこそ、取得したお客さまのデータを活用しようと意識していたとおもいます。どのカテゴリーがどう売れているか、どんなお客さまがどの商品を購入されたかなどの分析はかなり力を入れていたのではないかと思います。
──実店舗を運営している小売業でさえ、まだそこまでデータ分析は進んでおらず、モノタロウのような解像度は得られていないと感じています。
西尾 実店舗の小売業は、ネット通販ほどお客さまのデータを取ることできませんよね。もしも、そのデータが物流設計のインプットとして存在していれば、もっと効率的なセンター運営ができるのではないかとおもいます。
たとえばペットフードとミネラルウォーターを同じリードタイムで店舗に運ぶ必要があるのか。いまは細かいお客さまの買い方、店舗での売れ方がわからないので、とにかく同じ基準で出荷し、同じリードタイムで配送するという設計になっているのではないかとおもいますが、販売のデータがわかれば、ロジスティクスの設計はもっとしやすくなるはずです。
店内物流作業はもっと減らせる
──現状の実店舗の小売業の物流に対して、西尾さんがどのように見ているかを教えてください。
西尾 店内の物流作業をもっと減らしていくことができるのではないかとおもっています。店舗の従業員の方が、もっと接客に時間を割きたくても、接客時間以上に品出しに時間がかかっている。狭いバックヤードに詰め込まれたかご車を引っ張りだしながら品出しをする…。そこをもっとスマートにできるのではないかと。
全文は 月刊MD note版にて公開中!(有料記事)
以下のリンクからご覧ください。
https://note.com/mdnext/n/nc621a7bd70cb


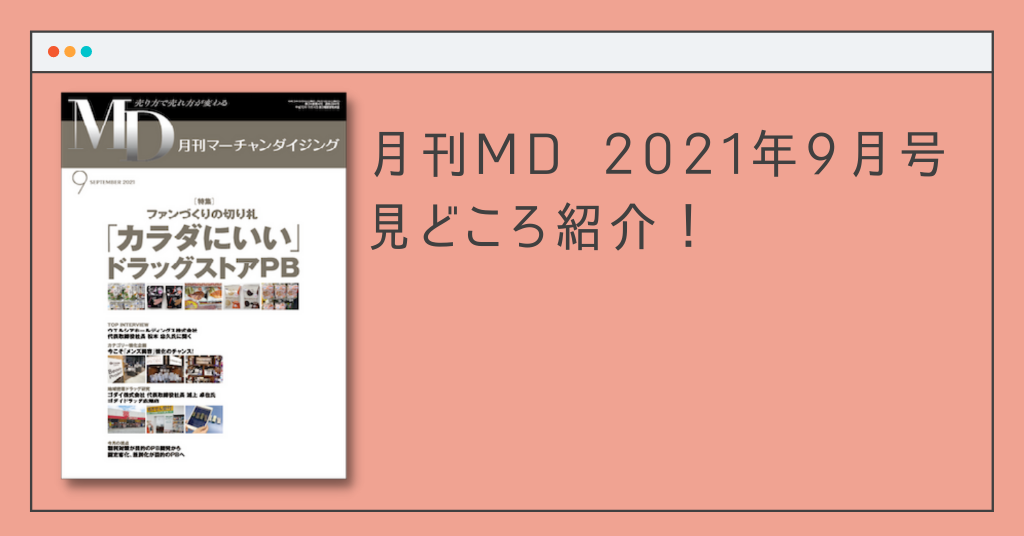
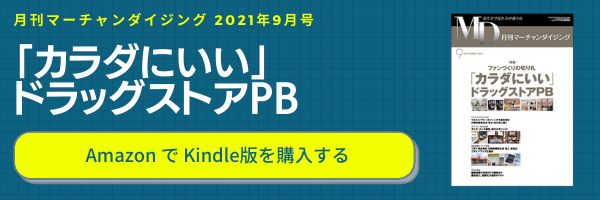
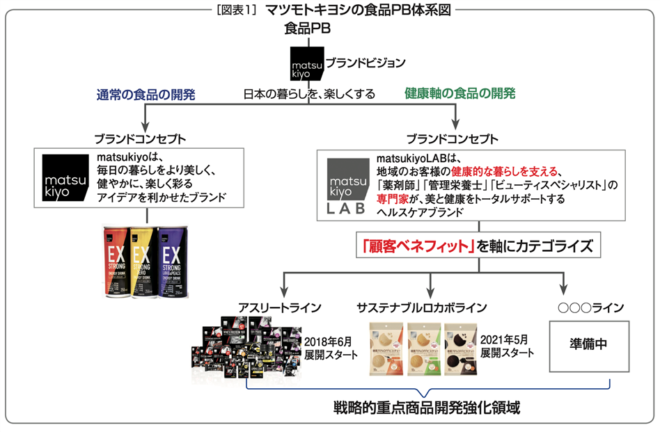
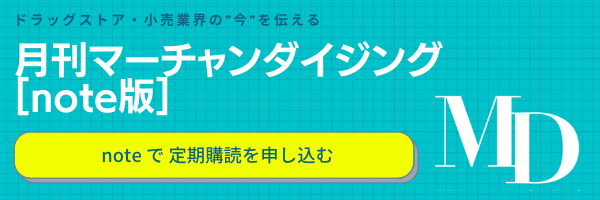



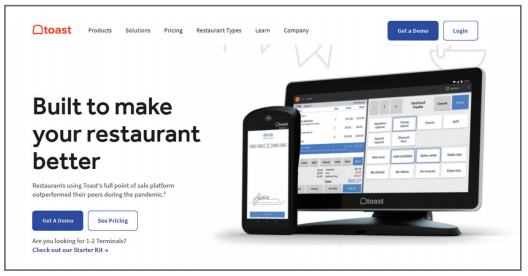
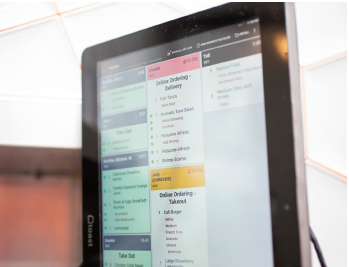
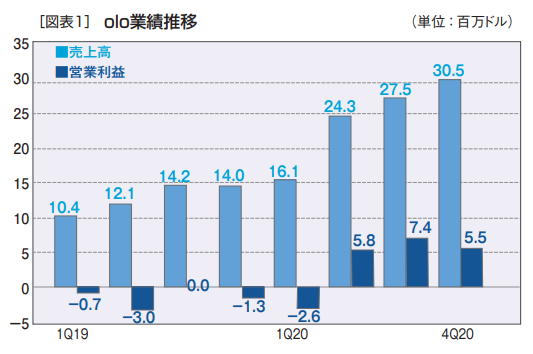


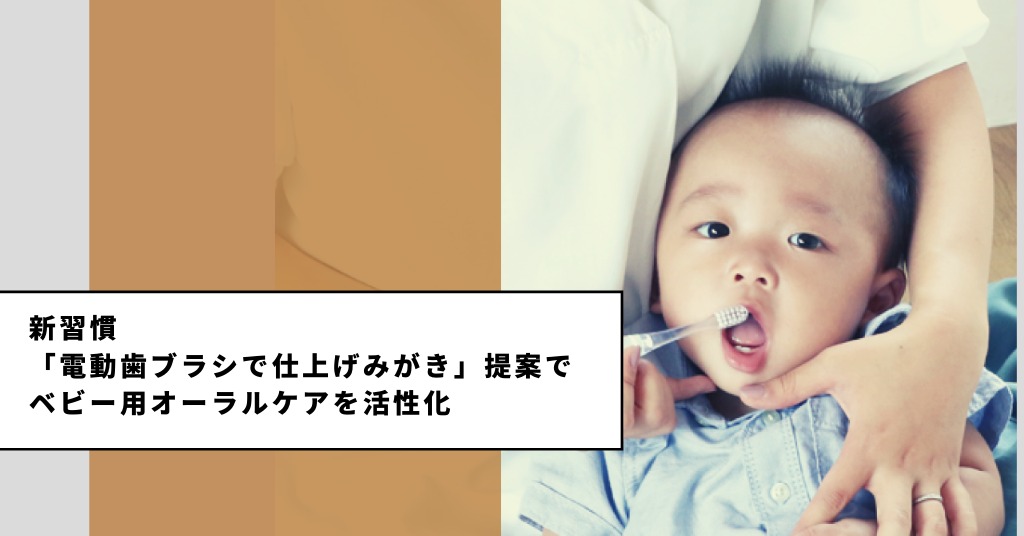





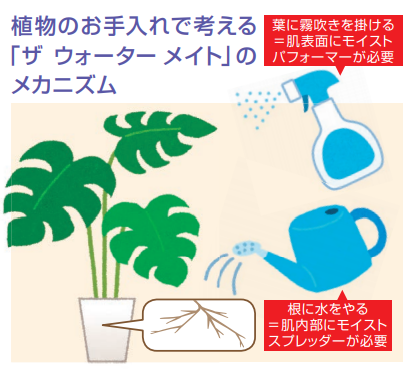
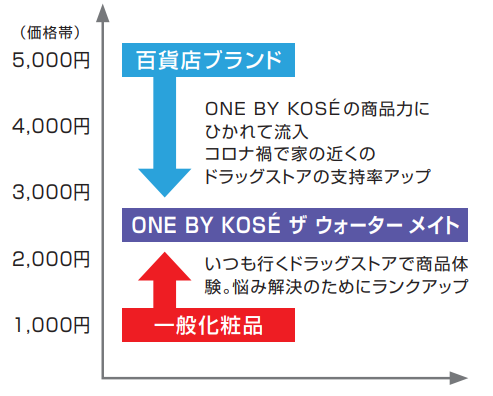


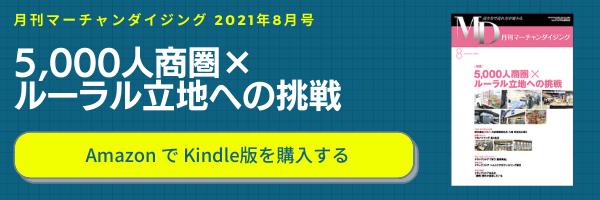
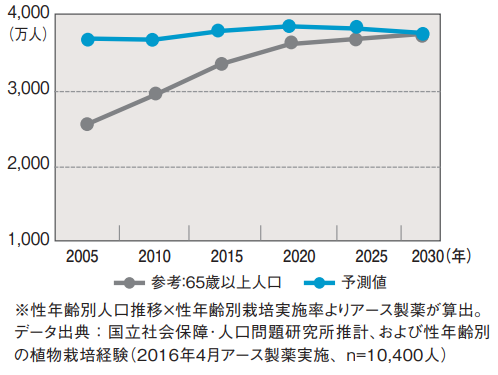
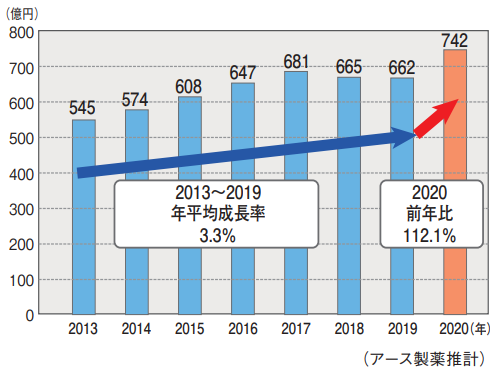
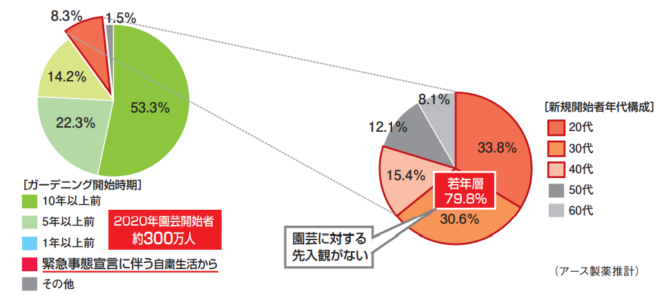




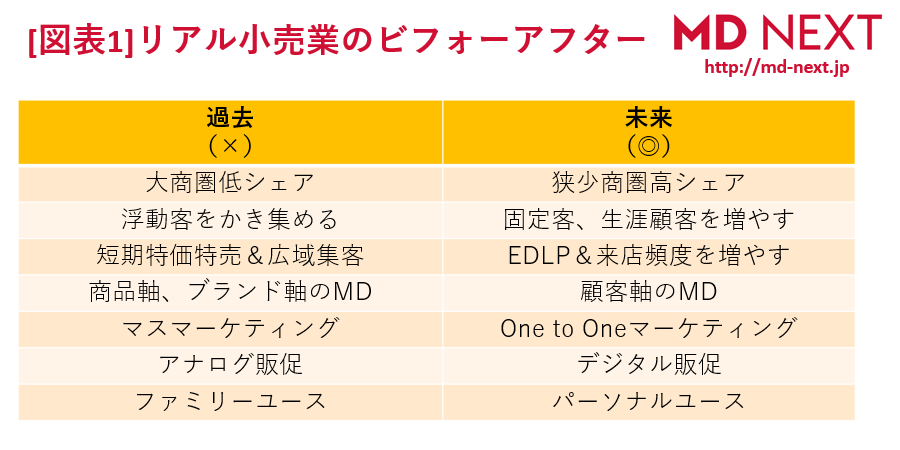
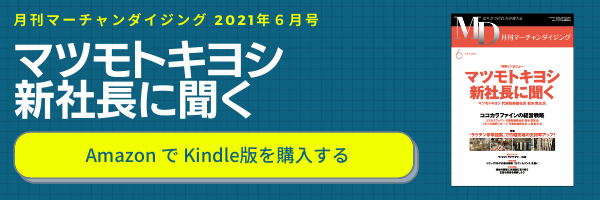
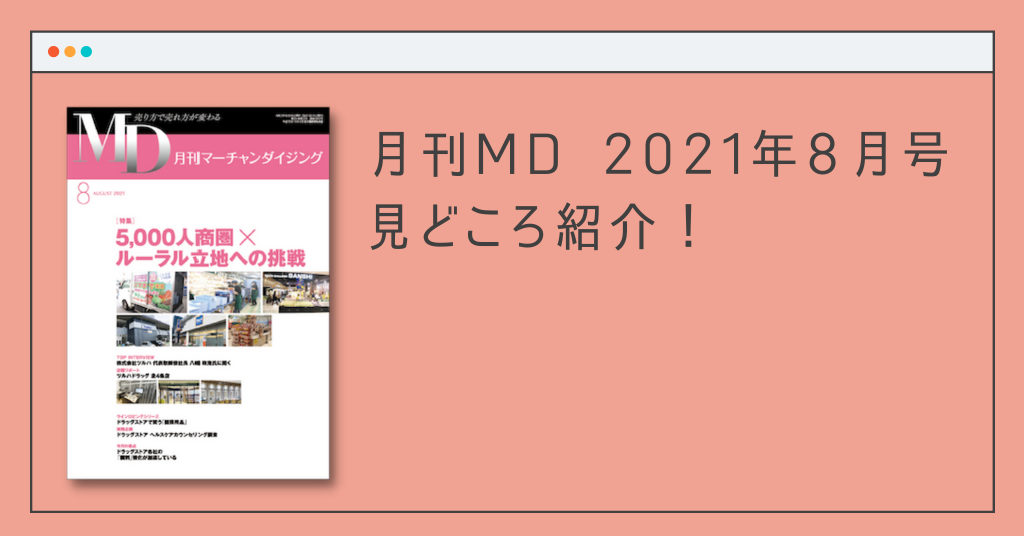




![NFI定例セミナー「ドラッグストア白書[最新版]『決算分析』『経営戦略&業態戦略』の深堀り解説」(2021/09/15 13:00~15:20)開催ご案内(オンライン)](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2021/07/202109_seminar.jpg)





