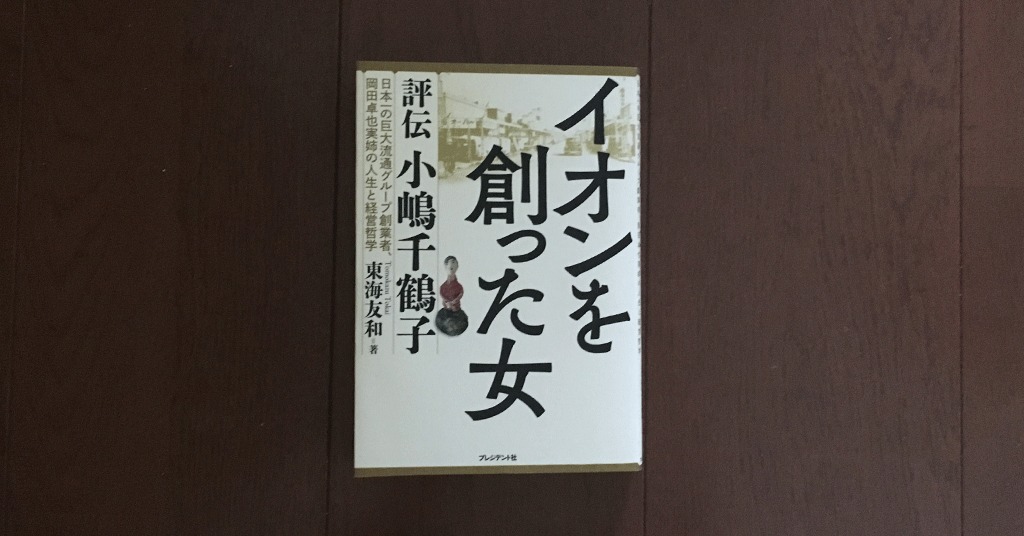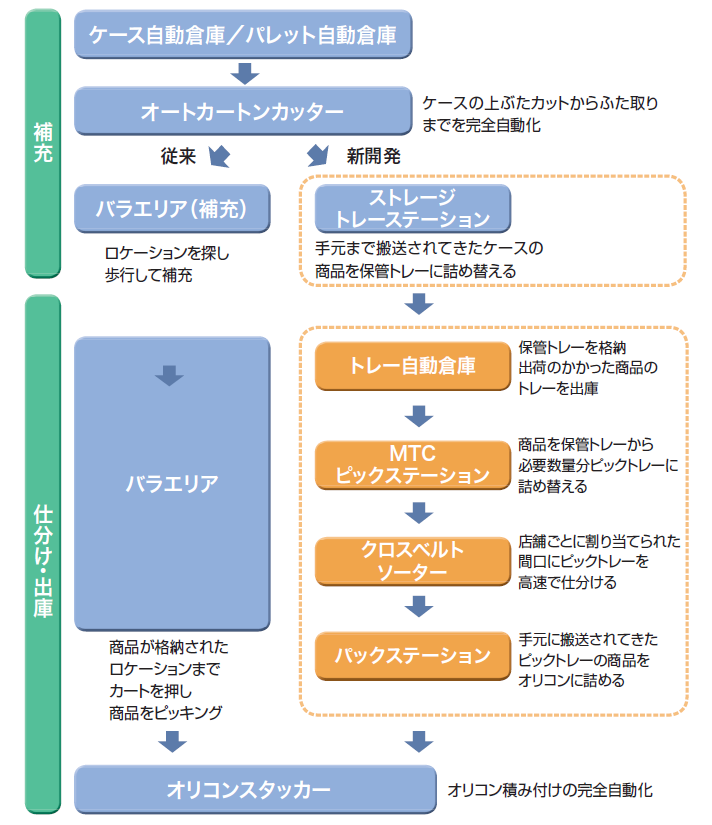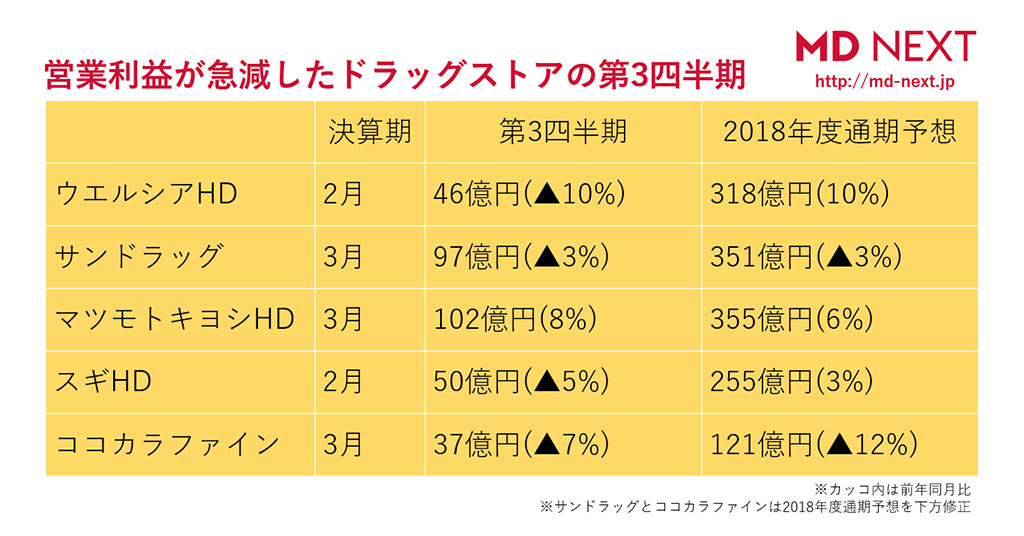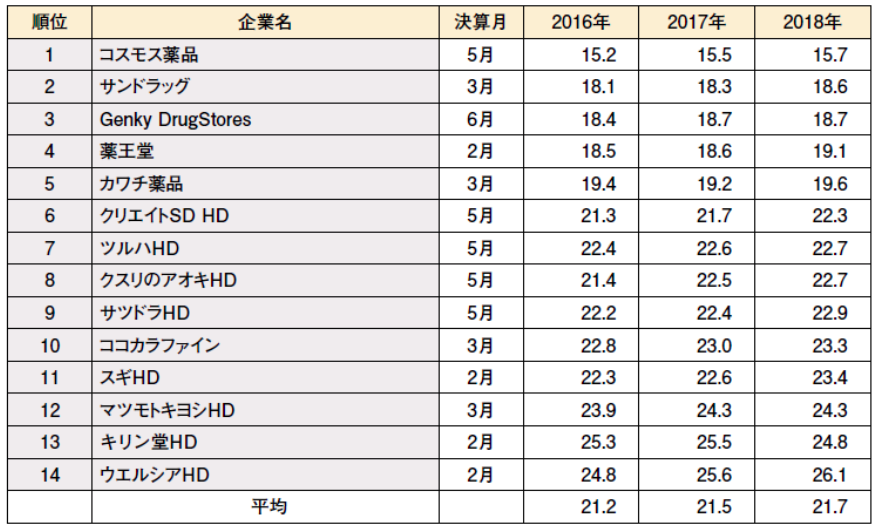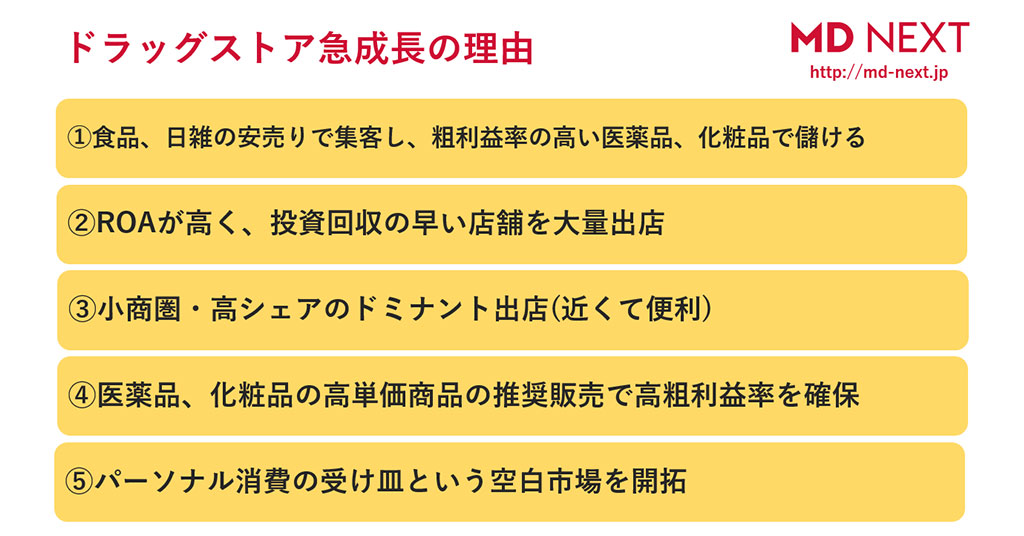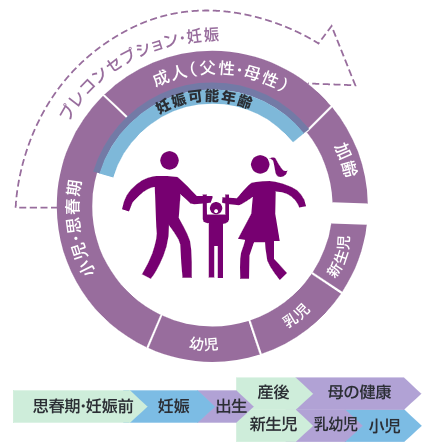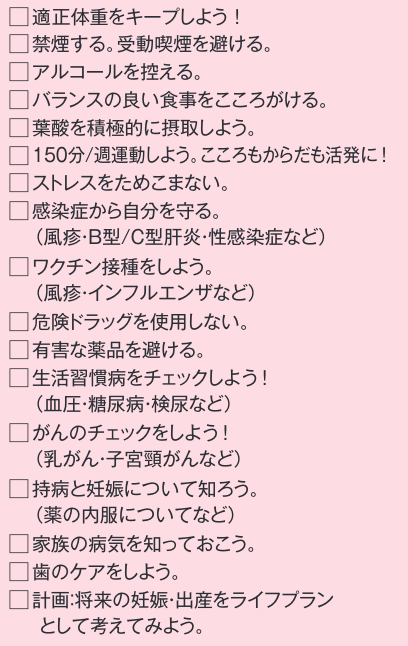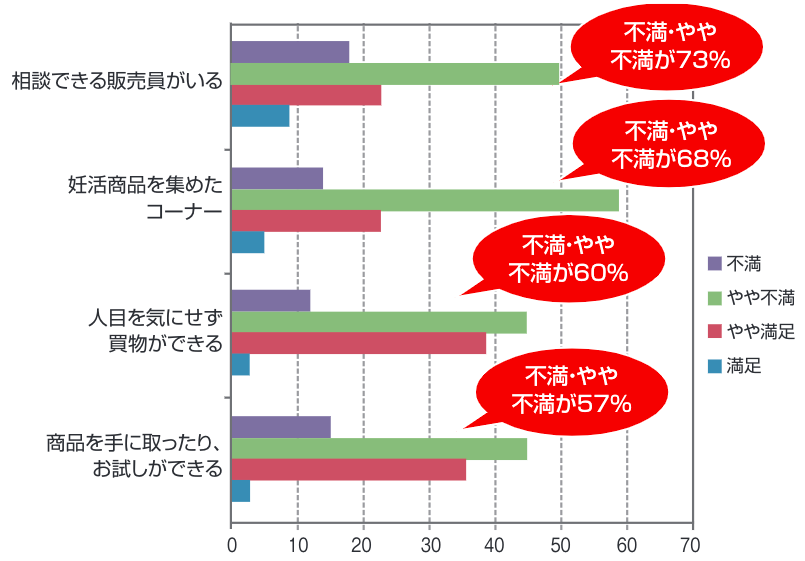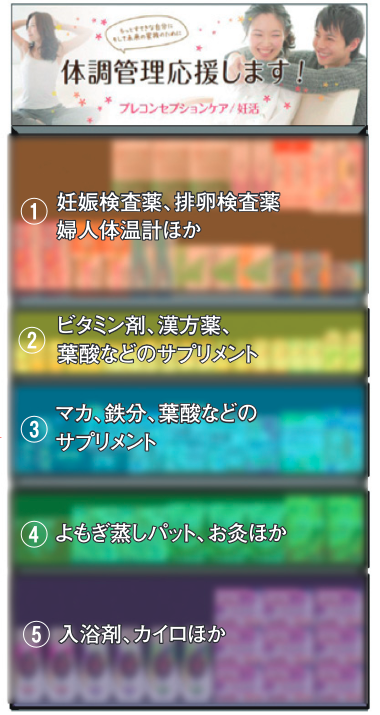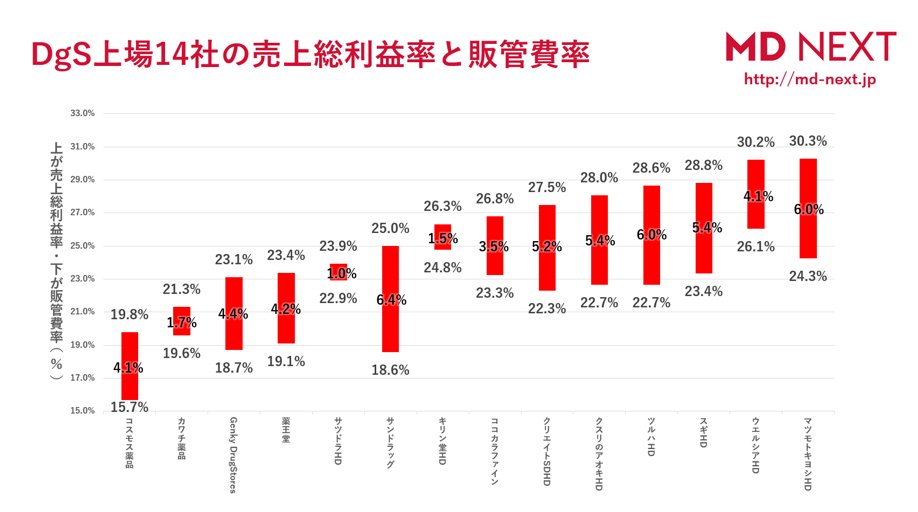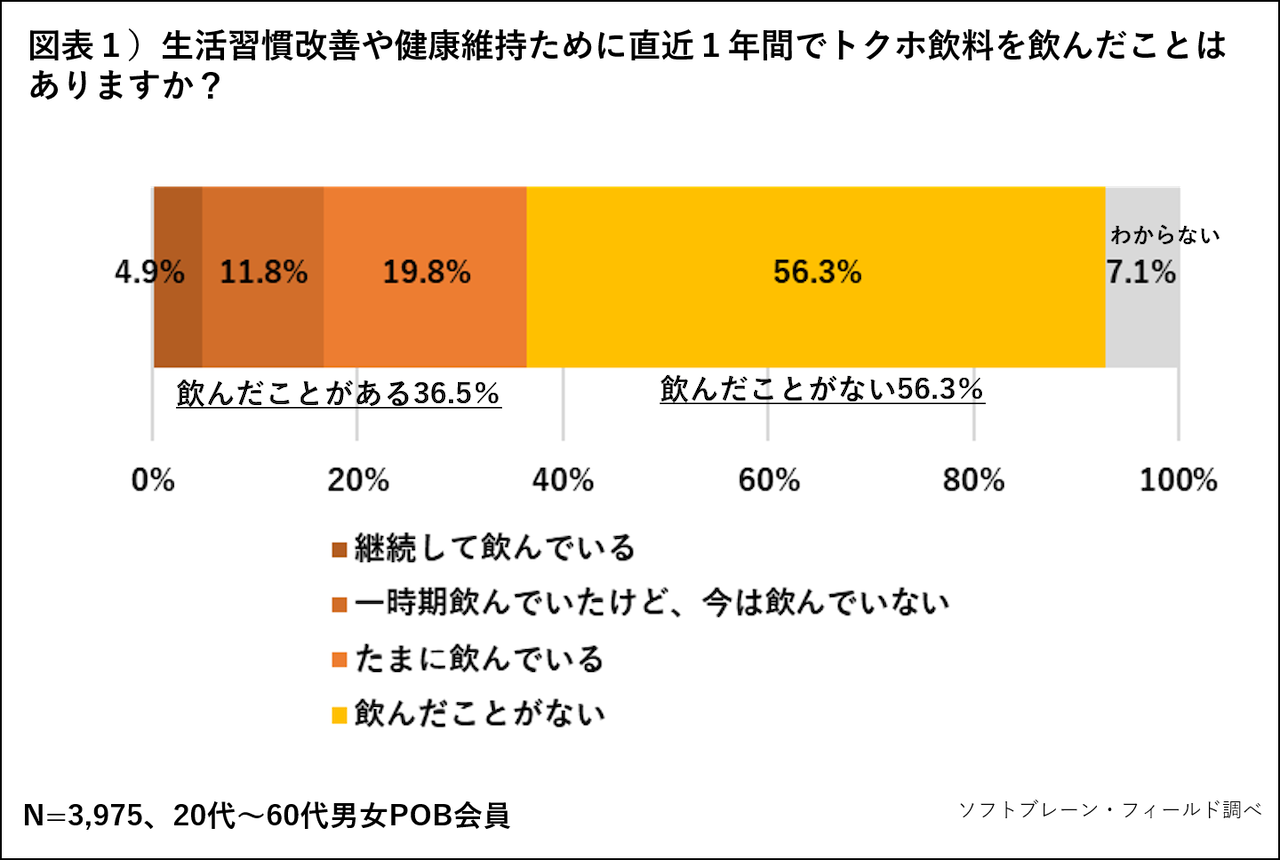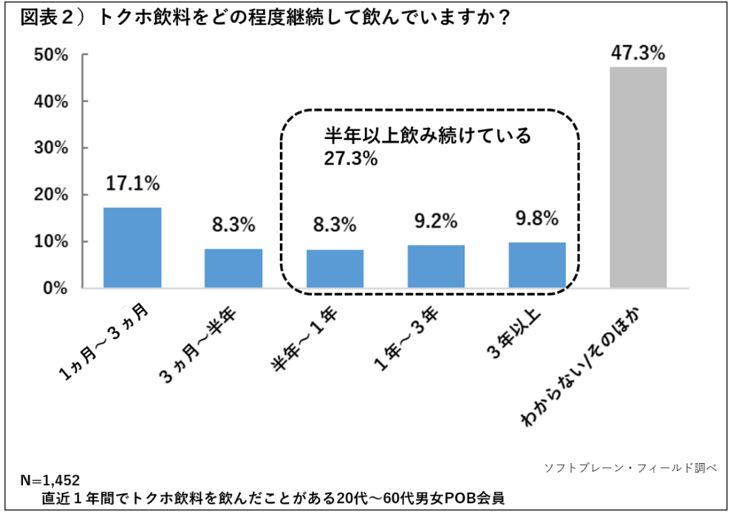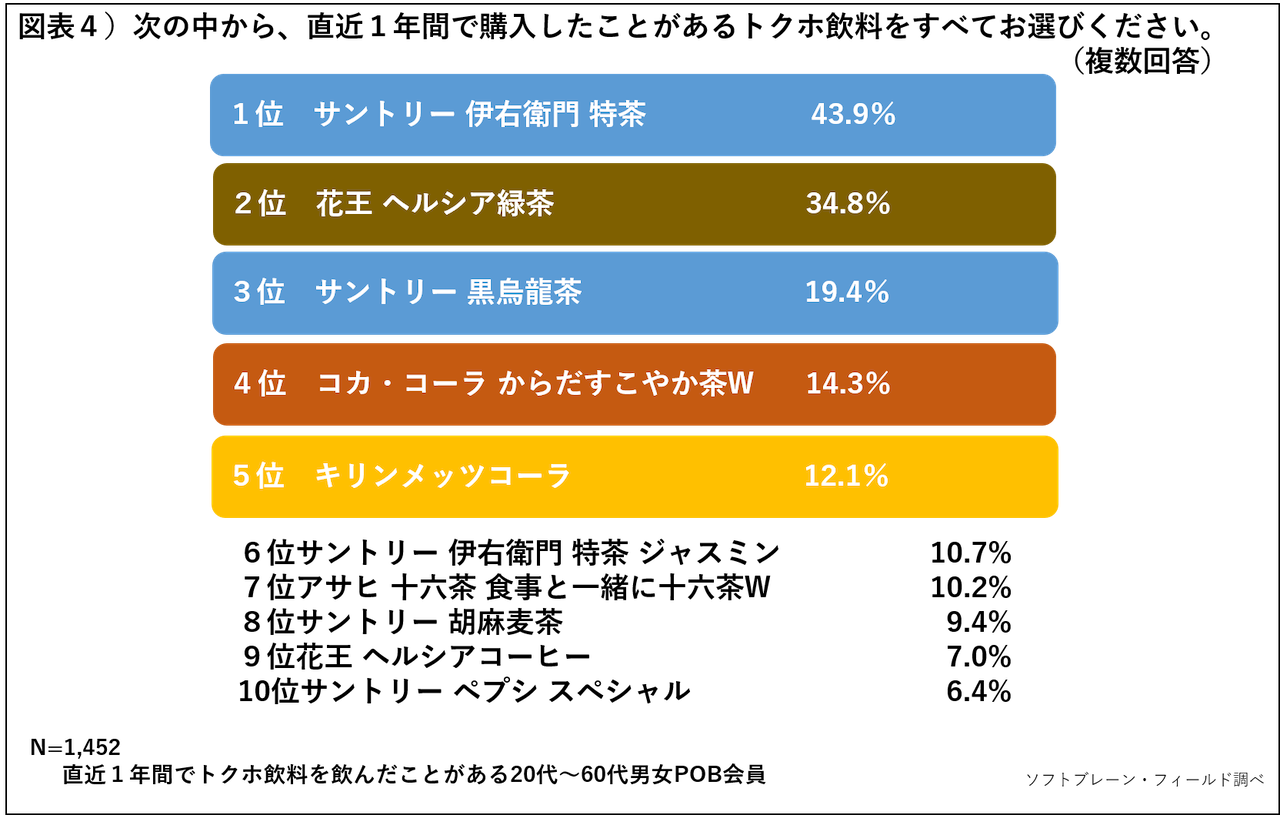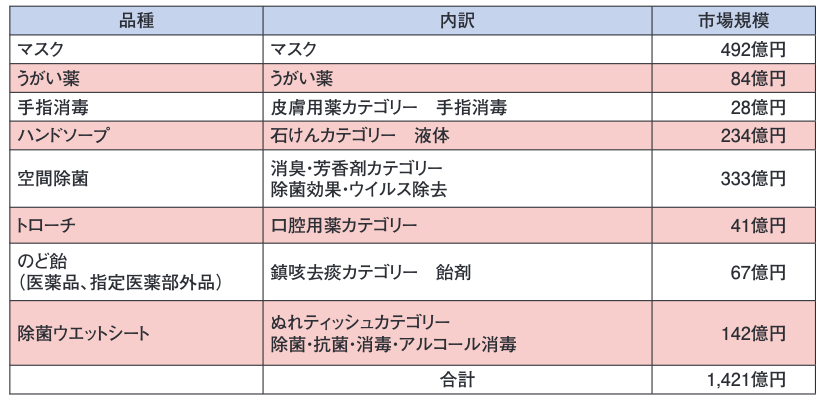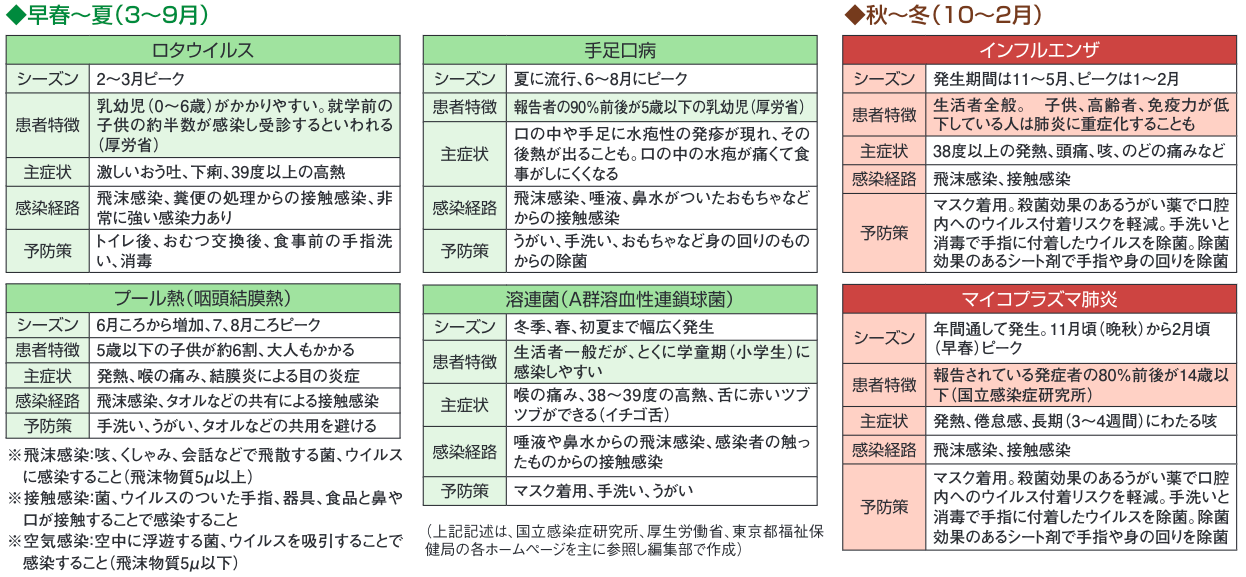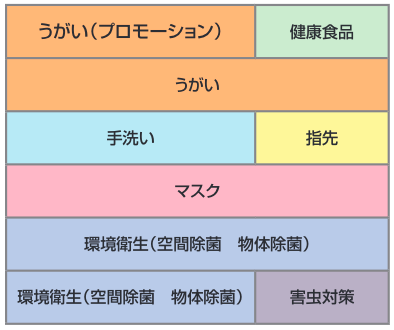どんな時代でも揺るがない組織・人事政策を確立した小嶋
イオングループは、1969年四日市の「オカダヤ」、姫路の「フタギ」、大阪の「シロ」という3つの繁盛店が合併して生まれた「ジャスコ」がその中核となり、大なり小なりの様々な事業体を吸収しながら今日まで発展を続けてきた。その中には、ヤオハン、ニチイ、ダイエーといったかつてジャスコとともに戦後の高度成長期の中を疾走し斃(たお)れた大チェーンも含まれている。
その変遷の姿を評して「発展ではなく膨張だ」と揶揄する業界通もいる。しかし今日まであれだけ膨大かつ個性的な組織体を抱え込みながら、瓦解することなくひとつのグループ経営を推進していくことを可能にしているのは、まさにいつどのような時代にあっても揺るがないイオンの組織・人事政策を貫くポリシーの確立があってこそと言われている。
その骨格をつくりあげ、磨き続けたのが、小嶋千鶴子である。
1916年(大正5年)、岡田家の次女として生まれた千鶴子は、若いときに相次いで両親と姉を失い、9歳年下の弟卓也を早稲田大学在学中に学生社長に据え、オカダヤを切り盛りする。卓也を立派な後継に育て上げることはもちろんのこと、自身は戦中・戦後という激動の時代のなかで翻弄されることなく荒波を乗り越えるためには何が必要なのか。1店舗の時代から、それは人づくり、組織作りであると見定めて、ひたすらにその本質を追求し続けたのである。
先読みとプリンシプルの人
小嶋千鶴子は「先読み」と「プリンシプル」の人と言われている。
先読みは、商人の優れた資質のひとつである。
太平洋戦争中、様々な情報を集めて分析し、負け戦を見越して現金を銀行に預けないようにしていた千鶴子。戦後、店も商品も焼かれなにも売るものがなかったとき、お客の家に焼けずに残っていた岡田屋の商品券をその現金と引き換えた。千鶴子は文字通り「信用」を売ったのである。お客はさすがは岡田屋とその名を高らしめたという。
また千鶴子は戦後のインフレと新円切り替えを予見し、ありったけの現金を商品に変えておき、新円を獲得する。統制経済下、人々は配給に対して商品を引き換える店を指定し、切符を買わねばならなかった。しかし先の「信用」のおかげもあり、オカダヤは地域一番の引き換え指定を受けたという。
先読みの根底には、人に対する厳しくも優しいまなざしがあった。この2つがなければ事業というものは大成しない。
プリンシプルとは、「原理原則」と訳されることが多いが、プリンシプルという英語の持つニュアンスは、例外や条件付が多い日本的な原理原則とは少し異なる。
プリンシプルとは、どんなことがあっても守らねばならない、自身の行動規範という意味に近い。
あるとき、オカダヤにあすの遠足のための遠くの町からお弁当箱を買いに親子がやってきた。ほしかった商品を見つけたが、わずかにお金が足らなかった。「お金が足りないので、家から持ってこようと思いますが、遠いので持ってくることができません。すこし安くなりませんか?」という親子に、千鶴子は「値段は商人が実印を押す気持ちでつけたものなので変えられない」と答えたという。残念そうに諦めて帰る親子の後を追いかけて千鶴子は、「値段はまけられないが、足りない分はお貸しします。お返しはいつでもよいです」といって親子にそのお弁当箱を買って帰ってもらった。
自身の行動規範を変えず、お客の気持ちによりそうという千鶴子のプリンシプルがよく示されているエピソードである。
人事・組織のトップとして常に現場に入り込み問題点を浮き彫りにしていく姿は、オカダヤからジャスコに変わっても、従業員たちをときに畏怖させた。しかしそれは同時に絶対的な信頼の現われでもあったろう。
そのときに大切にしていたのは、自分が問題点を発見するのではなく、当事者たちの観察眼と意識に問い続けることであった。問題が生じたとき、この問題はこの従業員固有のものなのか、この店、部門だけのことなのか、全社的なものか、上司は把握しているのか。本質に迫り、問題の根本要因を突き止める。根本要因を特定して除去しない限り、また同じ問題が起こるからだ。
お客様から商品について聞かれたのに答えられなかった従業員は、単に個人の勉強不足と結決めつけず、年次にどのような研修制度が行われているのか逐一チェックし、教育研修担当者に解決策を提案させた。その解決策には、新しいアイデアがなければ突き返したという。
一方で、個人の勉強も督励した。自己とは己だけにあらず、他者との関係性においてはじめて「自己」は成り立つ。その自己が自ら勉強すれば、周囲にもどんどんよい影響が生まれる。
いつも明るい笑顔の社員が、最近曇りがちになっていたら、直近の個別シートと自己申告書に目を通す。この従業員が親の看病に従事していることを知ると、異動手配や、よい病院、先生を自ら探して、提言する。
この姿は、ウォルマート創業者のサムウォルトンに通じるものがある。彼もまた組織が巨大化してもルーティンとして店舗を訪問し続け、現場の声や問題点に耳を傾けてスピーディに解決策をはかっていくことを自らと幹部に課していた。
「企業内大学」と「人事政策覚書」
業界に先駆けて大卒者を採用し、1964年には、小売業界初ともいえる企業内大学OMC(オカダヤ・マネジメント・カレッジ)を設立したのも小嶋千鶴子である。
5年後、合併を機にジャスコ大学となる。学長に経営学の川崎進一を迎え、マネジメント、計数管理、マーチャンダイジングといった実務講座に当代一流の講師陣を揃え、哲学や文学といった教養講座も整備。実学とリベラルアーツの双方を修め社会に貢献する人間をつくることを目的とした米欧一流大学に通じる体制を一企業内に構築した。
合併による企業規模の拡大には、一握りのスターによる経営では限界であり、常に組織内に新しい人材の発見、育成の装置が必要であること。そして国内外、他分野へと社員たちの活躍舞台が広がる中で、従来の経験値では対処できない事態に対しても臆することなくチャレンジする人材を育成し、同時に他業界の数多専門職能、異才を取り込み生かしていくことが、これからの人事・組織作りに不可欠だと考えたからである。
1977年、小嶋千鶴子は、60歳でジャスコの役員を退任する。「老人が跋扈」しないよう自ら定めた定年制を守ったものであった。退任後は、常勤監査役として人事・組織づくりの裏方に徹する。
本書には、小嶋千鶴子が1980年に人事担当者向けに記した「人事政策覚書」が一部抜粋されている。 彼女の人事・組織政策観の根底にあるものは、次の一文(部分抜粋)でよく示されているだろう。
「経営の安定を維持することが人事戦略なのである。維持の要諦は発展にある。発展はすなわち改革にある。改革をするのは人間である。人間をつくるのが人事である」。
どんな経営環境にあっても倒れない組織を構成する人間をどうつくるのか。その内容は、40年を経てなお、新しい。
*文中人名の敬称は略させていただきました。
(東海友和著 プレジデント社)