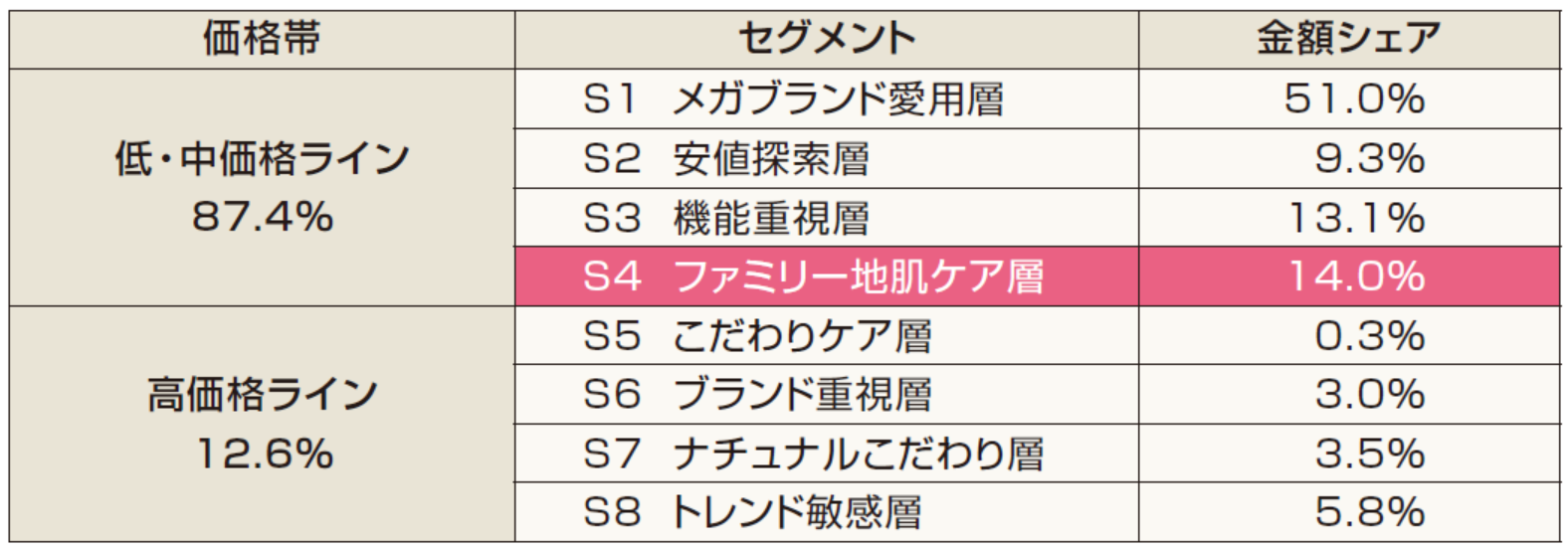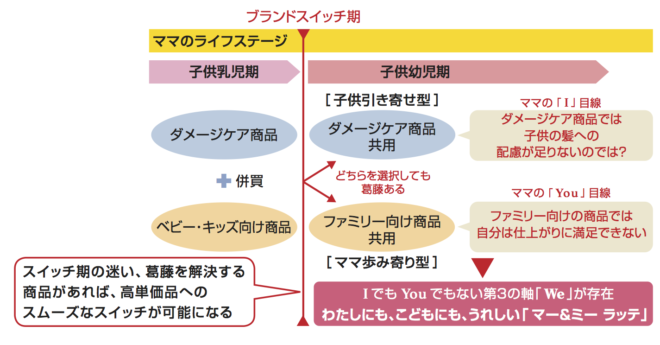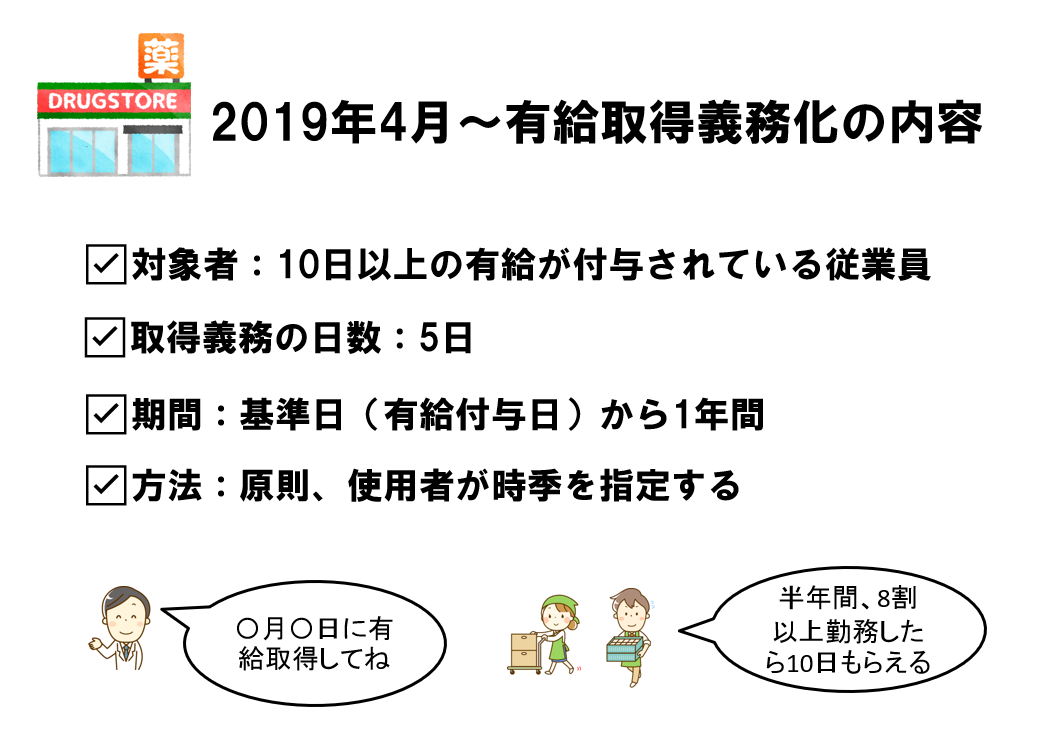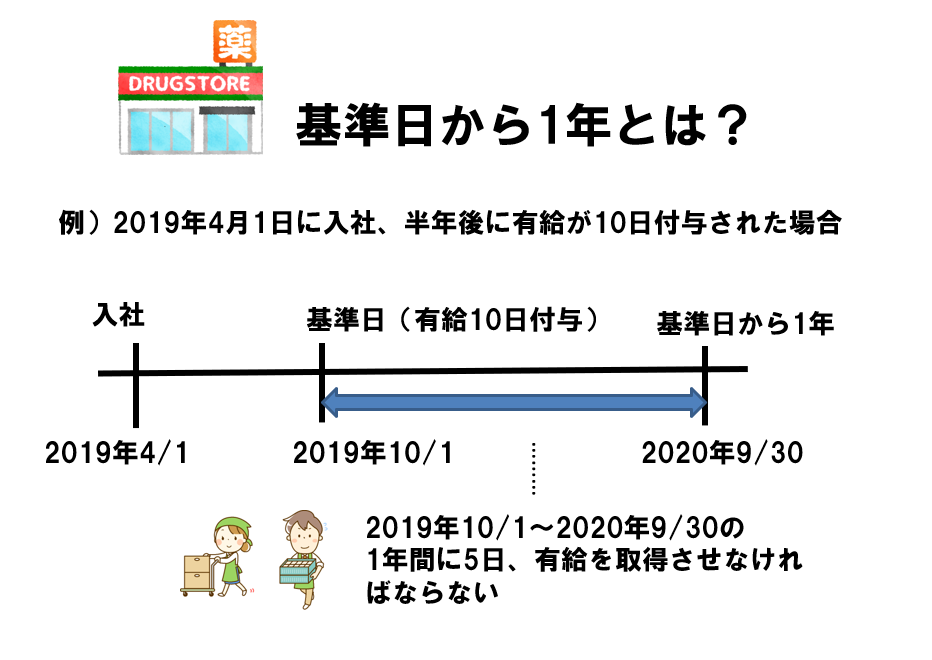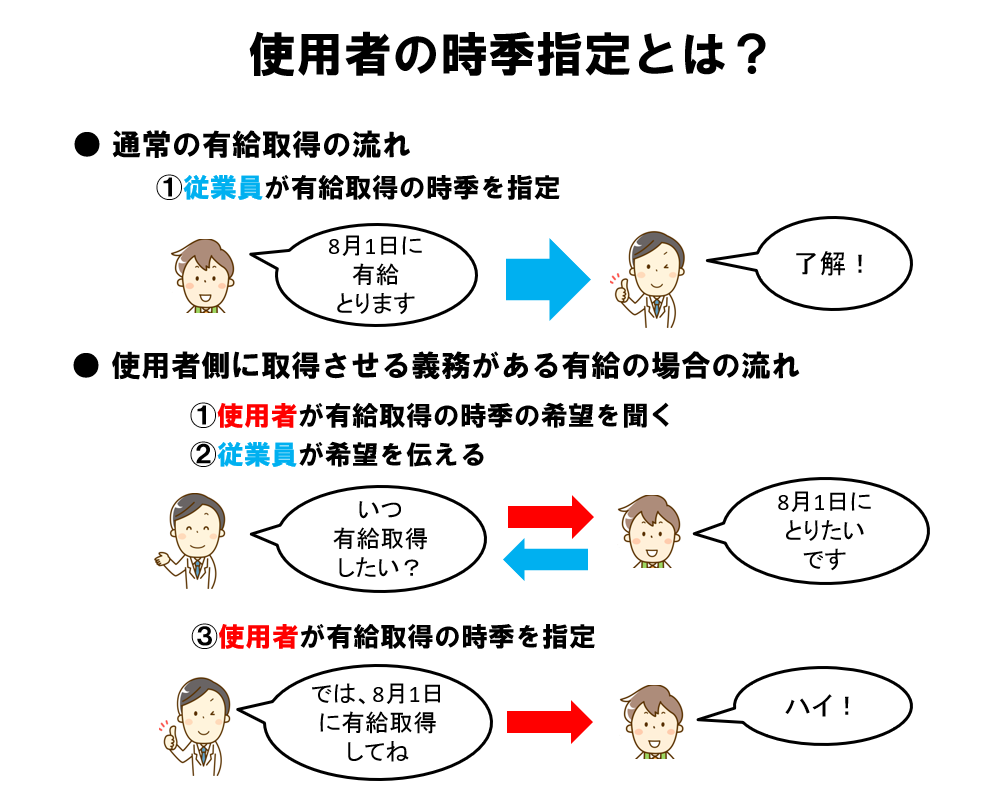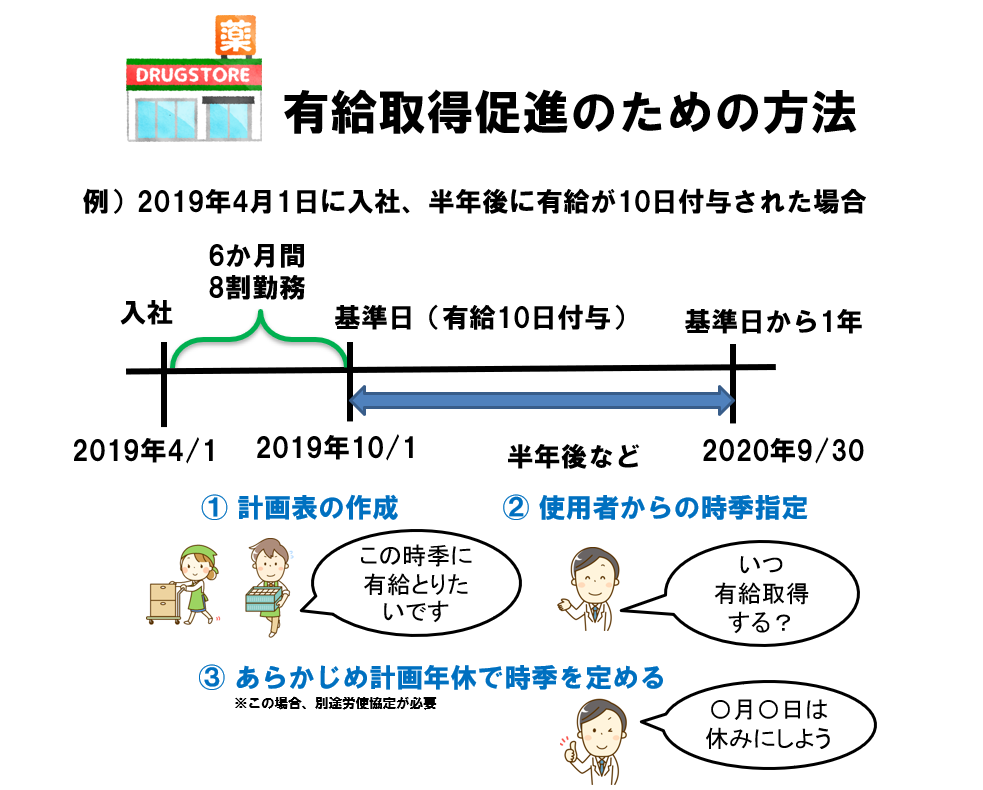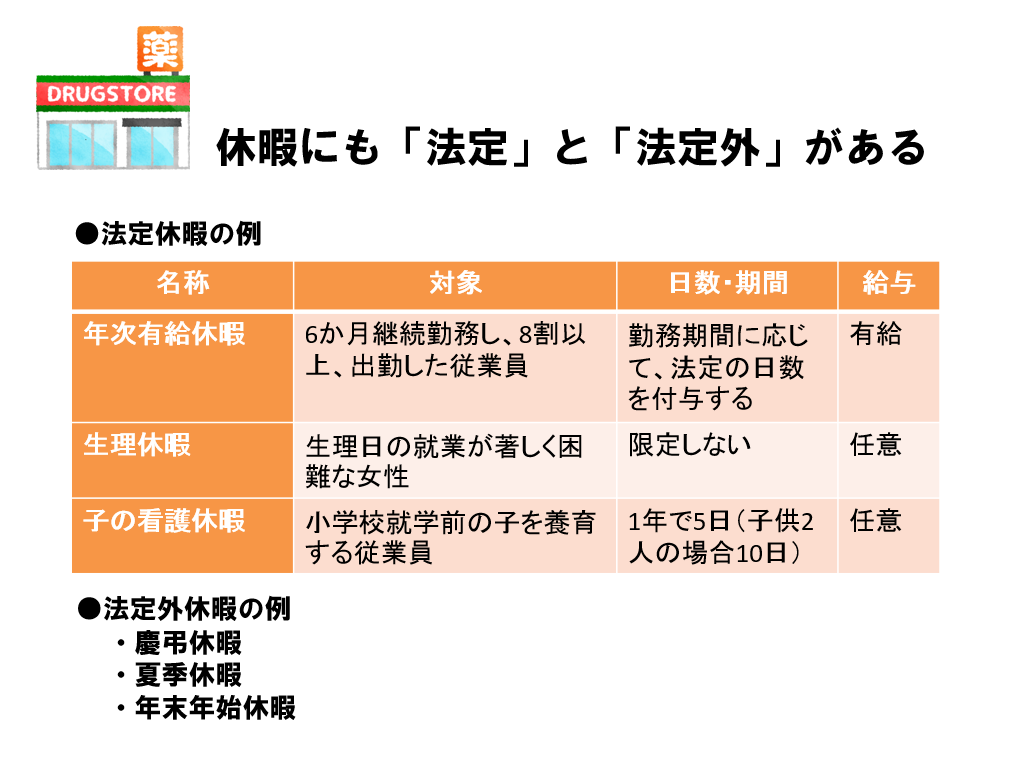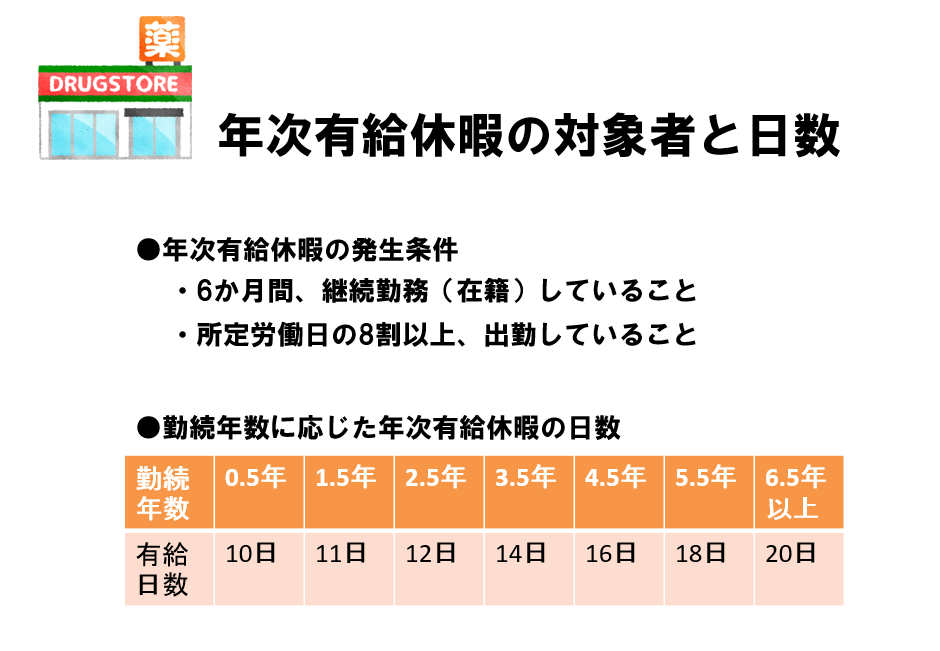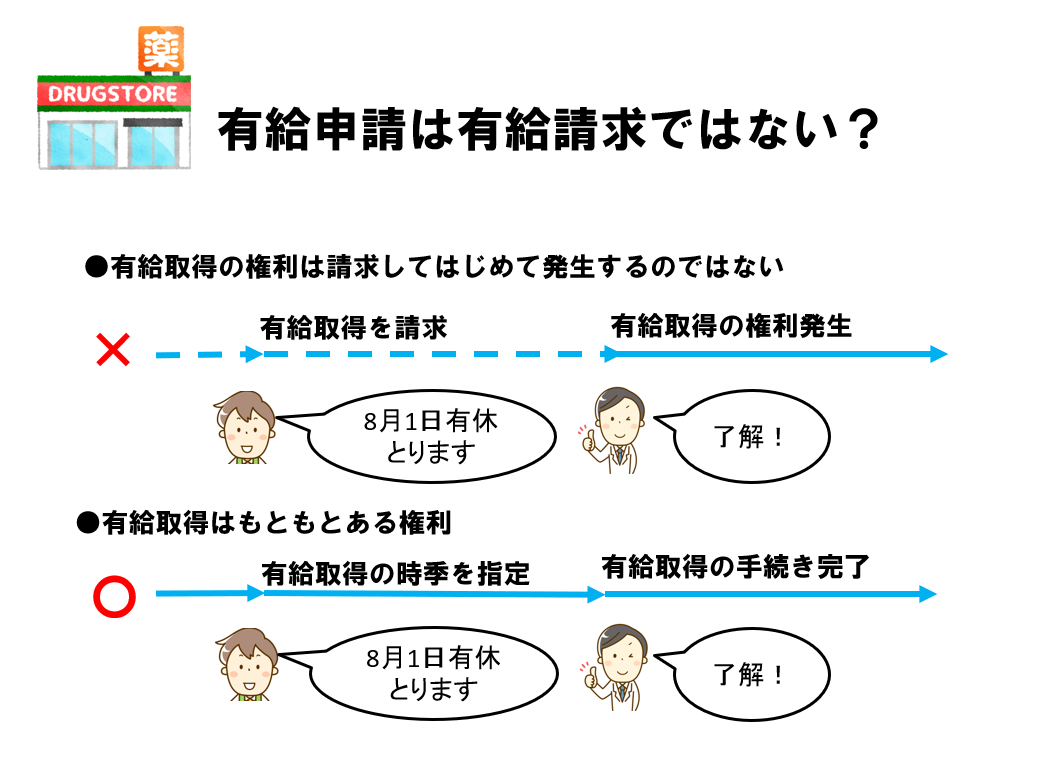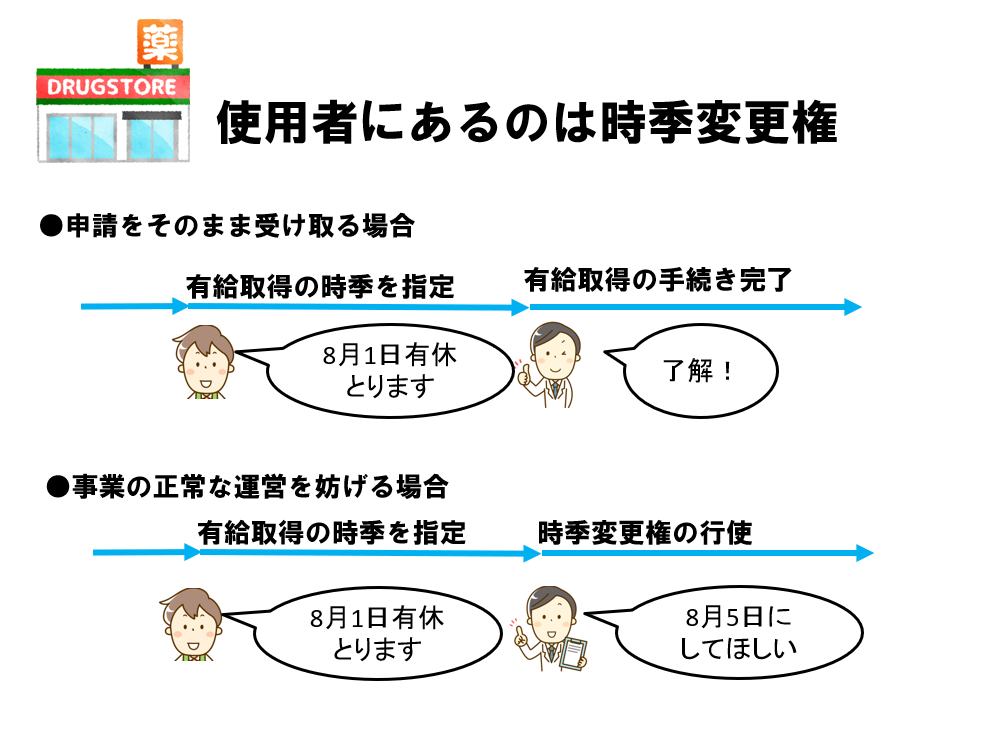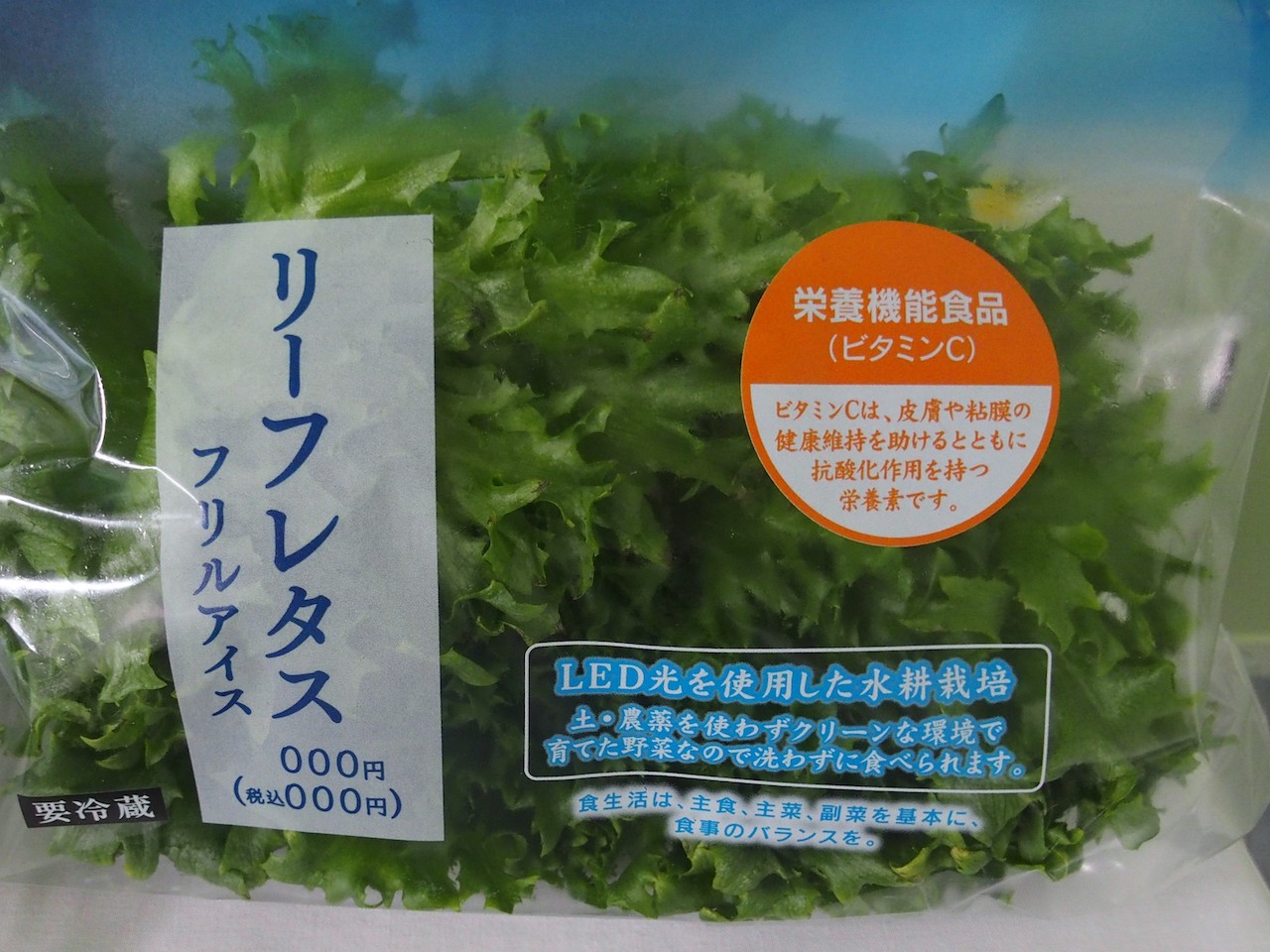小売業に一家言あるコンサルタント・実務家の方々に2019年の展望を語っていただく特集企画「小売業界2019年業界展望」。最終回となる今回は、オムニチャネルコンサルタントの逸見光次郎さんが登場します。カメラのキタムラでオムニチャネル化に成功し、現在さまざまな企業でデジタルシフト、オムニチャネル化に取り組む逸見さん。今後小売業にとって重要になる戦略は「たくさん売る」ことではなく「買い続けてもらう」ことだと言います。(聞き手:MD NEXT編集長 鹿野恵子)
小売業はまだまだ変化が足りない
――2018年までの小売業は、どのような状況だったと思われますか。
逸見:まだまだ変化が足りないと思っています。
お客様はみなスマートフォンをお持ちになって、さまざまな情報にアクセスできるようになっています。しかしいまだに小売業の店舗では「エンドに商品を積みましょう」「原価率を低減しましょう」というような話ばかりです。「高付加価値で粗利の高いものを売りましょう」とか「PBを作りましょう」という話も相変わらず耳にしますが、重要なのは本当にそこなのでしょうか?
――購買行動が変化しているのに、実店舗は変化が追い付いていません。
逸見:そうですね。ECやデジタルと、まだ距離をとっている小売業も少なくありません。ECやデジタルに関する事業部が組織上(店舗運営部などの)事業部門と別になっていますし、戦略がない企業が多いと感じています。
もしEC事業部が事業部門と組織上わかれていたとしても、(逸見氏が以前オムニチャネル化を推進した)カメラのキタムラのようにEC関与売上のような指標を立てて「店舗運営部とEC事業部で一緒にカメラの売上を伸ばそう!」という目標に一丸となって向かうことができればよいのです。スマートフォン上のお客様との接点であるアプリはECの部署が作るけれども、店舗で商品を受け取れば売上と利益は店舗に入る…というような構造になっていれば、店舗運営部も積極的にアプリのダウンロードを推奨するはずですから。
ですが、お客様はネットもリアルも関係なく買物をするようになってきているのに、大手企業ではやはりEC部門と事業部門の組織が別になっている。もうそのようなやり方は限界がきていて、根本的に変わっていく必要があるのだと思います。

2018年は既定路線のままでいられる限界の年だった
逸見:2020年のオリンピックの後はかならず景気が落ちて、市場はシュリンクします。消費増税も控えていますし、消費は確実に冷え込むでしょう。日本だけを市場とみていると明らかにつらいところです。
そこでインバウンドに注目が集まっているわけですが、このインバウンドという言葉ひとつとっても、日本の小売業がお客様のことを見ていないということがわかります。日本の既存の小売業は、海外からいらっしゃったお客様をひとまとめにして「インバウンド」と呼んでいますが、これは「塊」のように見えても実際は世帯年収や年齢などの背景が全く違う方々の集団です。ユニークIDで管理できる「顧客」と考えるべきです。
――お客様一人一人を見ないというのは不思議です。なぜなのでしょうか?
逸見:今までお客様をそのように見る習慣がなかったのですから、仕方ないと思っています。ですが、経営者の方には、「お客様個人の行動が見えるようになったという事実はしっかり理解してください」と申し上げております。
たとえば無印良品のスマートフォンアプリを例に挙げれば、アプリを立ち上げて何かを検索すると、その時点でお客様がどこでどんな商品を検索しはじめたのかがわかります。店舗でチェックインしてくれれば、わざわざ来店したとお客様が宣言してくださっているということになりますね。店頭での商品購入時にもアプリを見せていただけますから、購入した商品の商品コードと店舗コード、顧客IDを紐づけることができる。
つまり、ID番号XXXX番さんが店内、店外でどのような行動をしているのかということが、つまびらかになったということです。
「ユニーク客数」を増やすのではなく「リピート率」をあげる
逸見:これが今までわからなかったから、商品カテゴリ単位で予算を組んで予実管理をしていたわけです。でも誰が購入しているかがわかれば、考え方が変わりますよね。当然、それを実現するためには膨大なデータを処理するという課題は浮かび上がってきますが。
端的に言うと、これまでとは完全に逆の流れになっているんです。これまでは「商品」つまり「何を」から分析することしかできませんでした。しかし現在のような状況では、まず「誰が」というのが見えて「何を」「何回」「何個」購入している、というのが見えてくる。
売上は「客単価×客数」です。そして、この客数の中身を今はもっと細かく分解することができるようになりました。以前は客数が1000人だといったときに、そこでAさんが何回購入したのか、という話は全く見えませんでしたが、まずそのお客様が新規客なのか、既存客なのかがわかりますよね。既存客の中でもずっと購入し続けてくださっているお客様なのか、それとも久しぶりにお買求めいただいたお客様なのか…そういうことも顧客IDを使えば分解することができるわけです。
その上で主に購入している場所がネットなのか店なのか、両方にまたがっているのかということまでわかります。もちろんお買い物のときにポイントカードやアプリを提示することが前提ですので、100%レジ通過客の属性がわかるわけではありませんが、80%ぐらい見えればデータとしては十分でしょう。
昨年年間30万円購入していただいた7000人のお客様に、今年はあと1万円追加で購入していただくためにはどのようなアプローチをすればいいのか。年間30万円を31万円にするのはそれほど大変なことではありませんが売上は7000万円アップします。その30万円を分解していくと、食品を買っている、医薬品を買っている…とカテゴリでの購買動向で分けることができるかもしれません。
ーー商品軸のマーケティングから顧客軸のマーケティングへの移行が必要ということですね。そういったデータを基準にしたマーケティングに小売業は全く着手できていない状況ということでしょうか。
逸見:そうです。データが見えているのに、その事実を見ないで経営しています。売上と利益と客数の塊しか見ていない。
今まで中期経営計画といえば絵に描いた餅にすぎませんでしたが、それが本当に必要になってきたとも言えます。3年、5年というスパンでお客様とどのようなリレーションを深めていこうとしているのか。どれだけ繰り返しお買い物をしていただけるようにするのか。一般的な、日本国内のみをターゲットにしているような小売業さんでしたら、ユニークIDを増やすということはなかなか難しいので、いかにリピートを上げていくかということを考えていくべきだと思います。
顧客行動の全体像を設計できているか?
――本来でしたらそういった施策をどこの企業も打つべきですが、なかなかそこまで至っていないというのが現状です。
逸見:どこの小売業さんも、業績が厳しくなってきてやっと気が付いてきたタイミングだと思います。投資力がある企業さんは、なぜかレジを進化させたりしていますが…。
ーーそれは方向性に問題があるとお考えですか?
逸見:そうですね。お客様へ提供する価値を高めるという発想であれば、商品やサービスのクオリティも重要ですし、店舗やネットでの買物の利便性も重要です。とにかくほとんどのお客様は、ネットでも店舗でも情報を入手してお買い物をなさるようになりつつある。その全体像をしっかりと設計していく必要があります。
昔はメールでの販促も手運用だったのでできませんでしたが、今はビッグデータを分解して、最後はお客様一人一人に対してコミュニケーションを最適化させることもできるようになりました。
ただ、問題なのは仮説を立てないでツールにデータだけ流し込んで、マーケティングオートメーションツールでメールを配信すればいい、とやってしまうことが多いので、余分なメールが届いてお客様も離脱してしまう。
今でもマーケティングのデジタル化が理解されていなくて、メールをたくさん配信したほうが売上が上がるというような一時的な話がなされているような状況です。
本当は継続し続けたらお客さんは減り続けるということが理解されてないわけですよね。メールの配信先は少なくても、ピンポイントで「あなただけのメール」を送れるかどうかの方が重要なのに。
――販促の個別化、商品の個別化が今後重要になってくるということですね。
逸見:そうです。その点ヨーロッパは進んでいて、技術寄りで荒っぽいアメリカとは違って、派手さはないのですが、店舗で発行しているポイントカードやアプリがメールアドレスと紐づいていて、適切に連動をしています。
要はお客様と適切につながり、どうアプローチできるかが大切なんです。最近うまくいっているのは顧客視点で全体最適を描ける小売業さんですよね。企業理念がしっかりとしていて、それを愚直に考え続けて「ここはデジタルにしたほうがいいよね」とか「ここは人間が対応したほうがいいよね」という組み合わせを考えることができる企業さんです。こういった企業さんは、良さを残しつつ生き残ることができています。
失敗している企業さんは、それがはっきりしていなくて、いろいろな技術をつまみ食いして「この技術が面白い」とか「CtoCだ」とか「AWSにデータを乗せて分析すればいいんだ」とかとか(苦笑)、技術が先行してしまいがちです。
小売業だけでは顧客満足の実現はできない
ーーお客様にどう認知していただくかが重要ですよね。もっとマーケティングのデジタル化に向き合わなければならないということでしょうか。
逸見:今店頭ですらモノがありすぎてほしい商品を探しにくくなっています。その上、昔は商品が進化していて「バージョンアップしたこの新しい型に買い替えなきゃいけないね」という購買行動が多かったのですが、今はそういうものがほとんどなくなってきていて、逆にお客様の方向性がどうモノを減らすかになっています。
世帯構成人数も大きく変化しています。日本人の6割が単身世帯か2人世帯です。典型的な家族構成は減ってきている。それではモノを買わなくなりますよね。
そういう状況を理解した上で、お客さん個人にアプローチをしていくべきだと思います。「たくさん売る」ではなく「買い続けてもらう」んです。在庫をたくさん持つ必要もなくなります。メーカーさんも、ものをたくさんつくる必要はなくなりますよね。工場を稼働させることが重視されていましたが、それを絞り込んでいかにお客様の必要としているものを生産するのか、という方向に変わっていければいいんです。
――小売業だけでは顧客満足の実現は不可能ということですね。
逸見:そうですね。今後、ますます卸、メーカー、小売はデータを共有しなければならない時代が来ると思います。小売業側には個人のIDに紐づくデータがありますし、メーカーには全国というセグメントのデータがあります。
これまでは巨大な小売業が同じ製品を日本全国津々浦々まで流通させようとするから、メーカーの生産量が追い付かなくなってしまいました。コンビニの大手チェーンも2万店舗体制になると、メーカーが生産・納品しなければならない商品の個数も膨大になります。小売業は大きくなりすぎてしまったのだと思います。
海外の小売業はNBのコントロール弁としてPBに力を入れています。それを販売するためにウォルマートも店舗網を増やしているといって過言ではありません。
メーカーはこれまでのように製造量を増やして原価を下げて消費者にコスパを提供するのではなくて、消費者が本当に必要なものを作って提供することによって、無駄を省き、利益を出す必要があるのではないかと考えています。
――どんぶり勘定の見込み生産では今後が厳しくなる企業が多そうです。
逸見:本当に、ぎりぎりにきていると思います。キャッシュに余裕があったトップ企業も転換しなければならないですし、収益性が厳しくなっている企業もたくさんあります。
そのような企業さんがこれまでと同様、たくさん売るために市場を獲得してシェアを上げて原価率を下げ利益を出すという発想をいまだに持っているのでしたら、この先厳しくなる一方ではないでしょうか?
でも変わる余地はまだあります。2018年は既定路線のままで進むことのできる限界の年でした。2020年や2030年を見据えて、2019年からは戦略を本当に変えていく必要があるのではないでしょうか。
ーー本日は興味深いお話をありがとうございました。





![[PR]「わたしにもこどもにうれしい」ヘアケアブランド誕生](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/CKV.png)