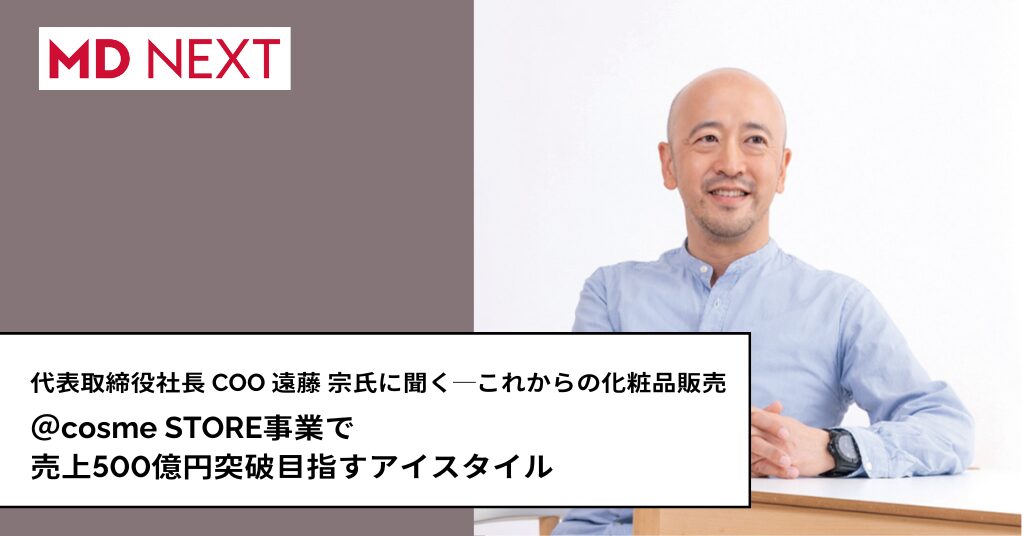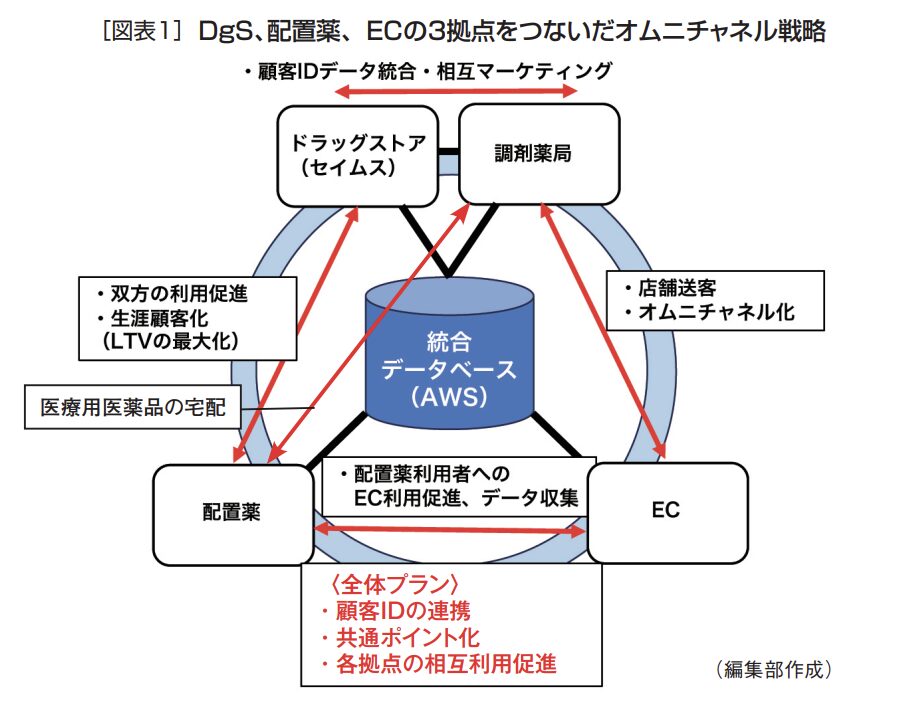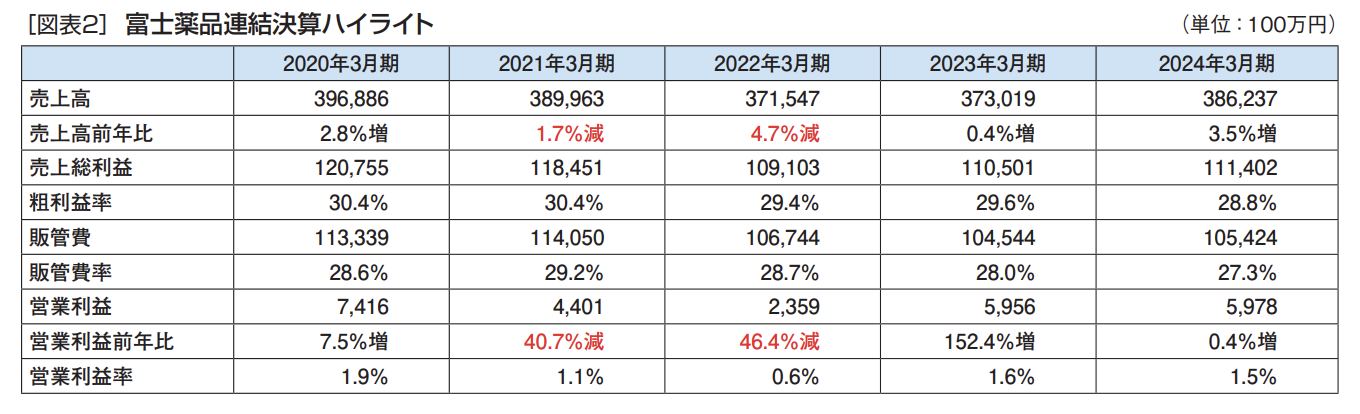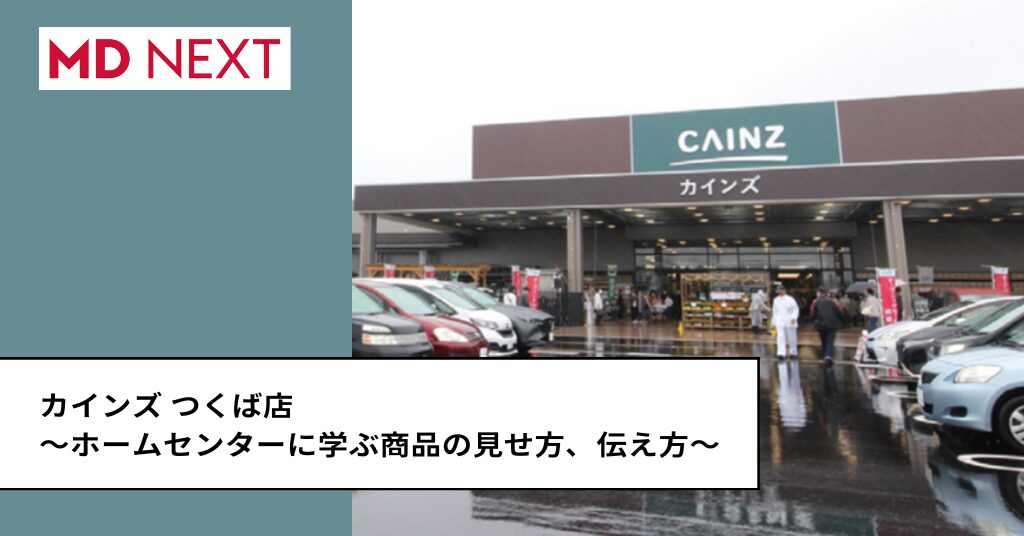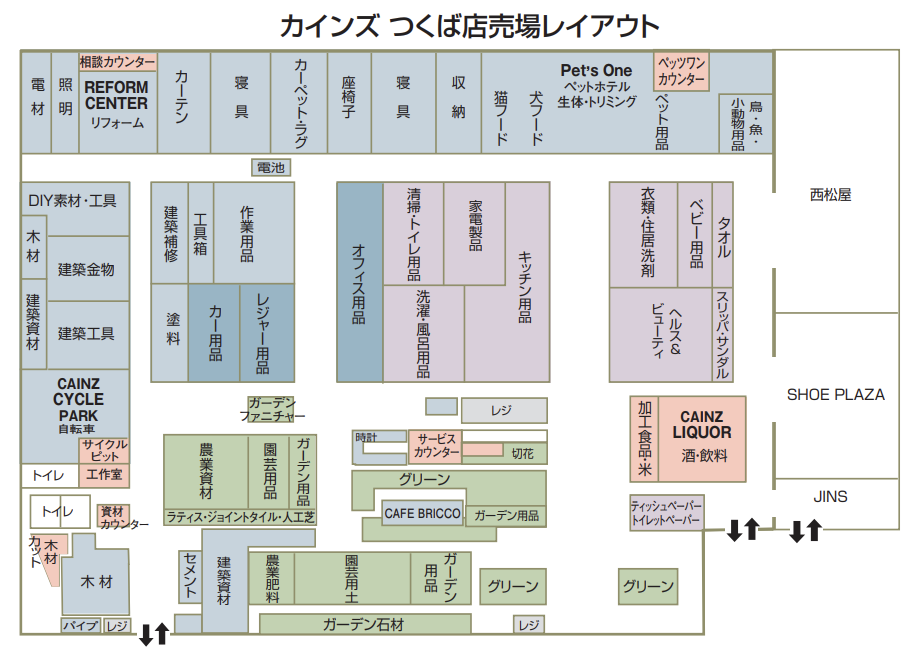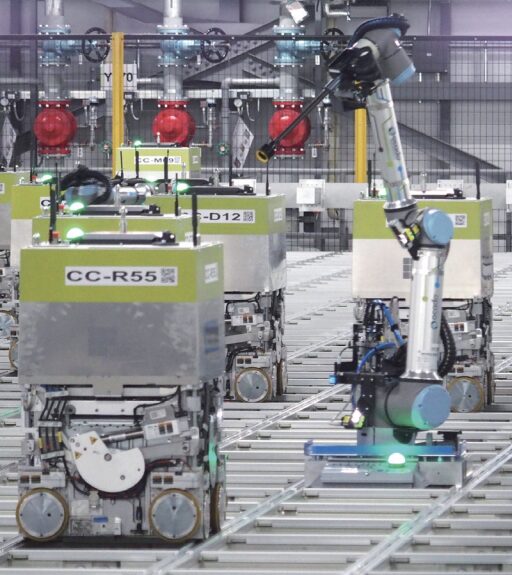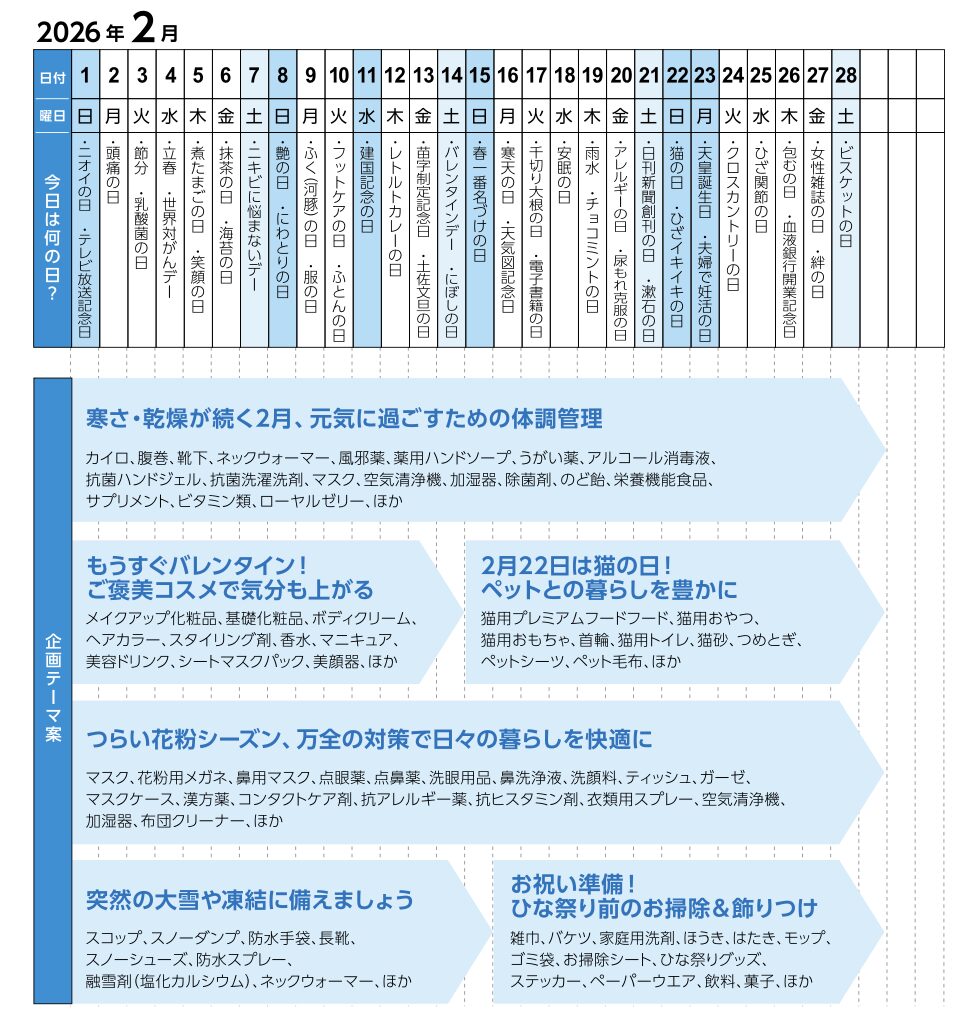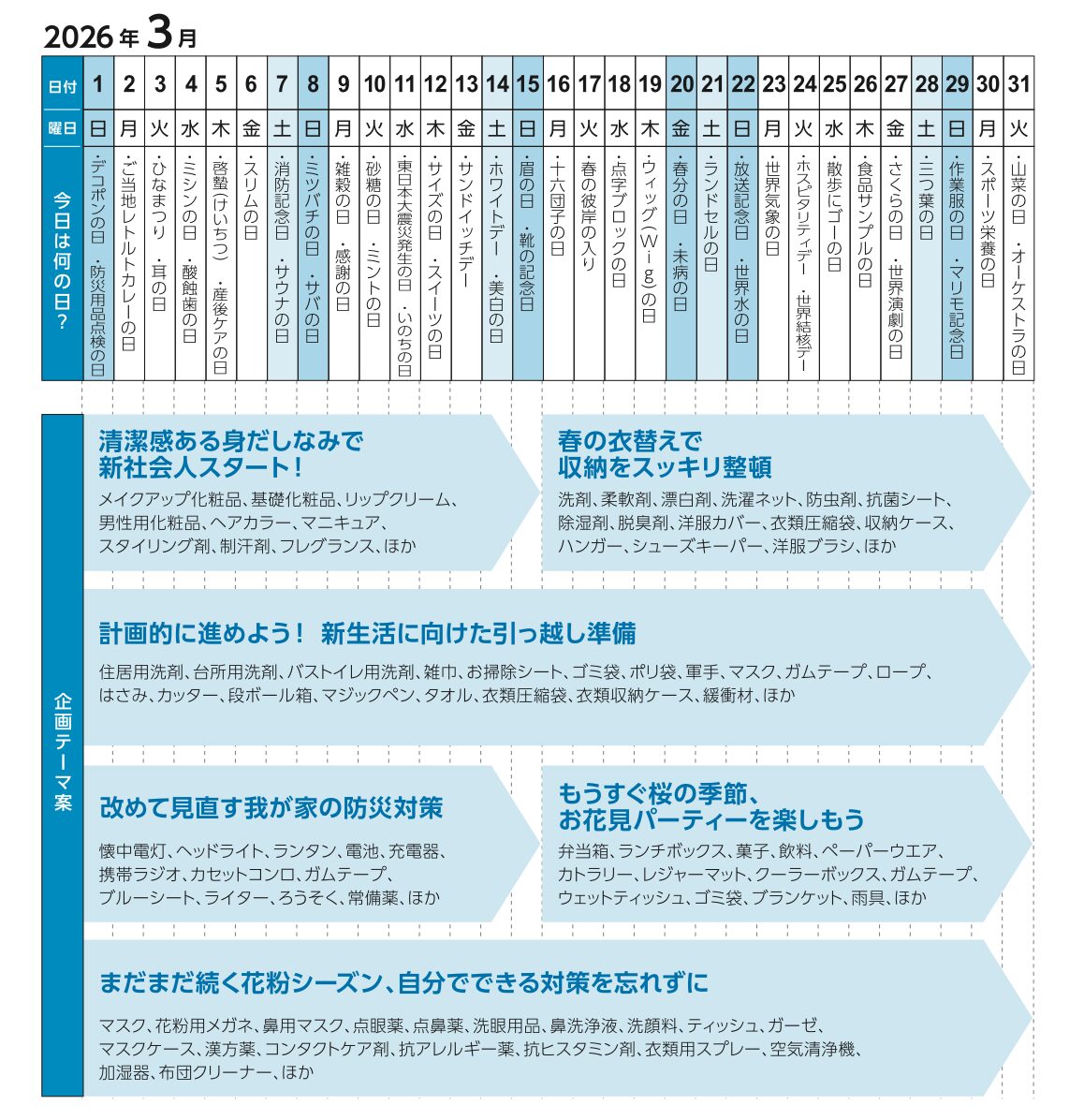滞留時間を長くして買上点数を上げる店づくり
─今回はアイスタイルのリテール事業の戦略を伺うとともに、御社の店づくりや売り方、遠藤社長からドラッグストア(DgS)の化粧品売場がどのように見えているかなどを伺い、DgSの化粧品売場の参考にさせて頂きたいと考えています。
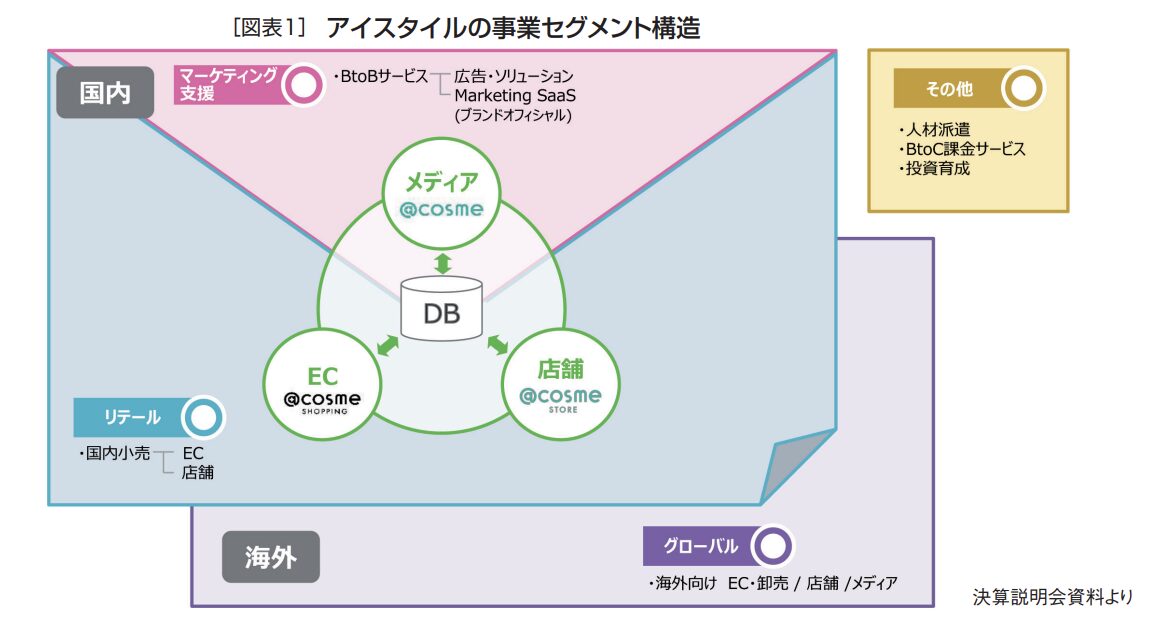
遠藤 店舗で化粧品を販売する方法は、@cosme STOREや@cosme TOKYOのような店があってもいいし、DgSのような便利に使える店があってもいいと思います。
私たちは、あえて「非効率」な売場レイアウトにすることで、滞留時間を長くして買上点数を上げるお店にしています。決して高額な商品を売ろうとしているわけではありませんが、圧倒的な客数を呼べるようにマーチャンダイジング(MD=品揃え)を深く掘り込んで人も配置しています。
DgSの化粧品売場は、私たちの店づくりとは真逆の方向性だと思います。セルフで効率的に圧倒的に探しやすい売場が基本ではないでしょうか。
目的の商品がどこにあるかがわかりやすく、関連性のある商品の売場もすぐわかる。商品特徴もPOPやサインでわかりやすい。当然実行されていると思いますが、ぱっと見て、売場、特徴が「わかりやすい売場」を充実させるのがいいのではないかと思います。
─DgSは比較的商圏が狭い(商圏人口が少ない)ということもあり、セルフ販売に加え、顧客台帳を整備してカウンセリング販売に注力している企業も多いと思います。
遠藤 全部の店をその販売スタイルにすると儲からなくなるので、そうする店としない店を立地条件や商圏規模で明確に選別する必要があると思います。また、多くのDgSはPOSデータの分析などで、そのように選別しているのではないでしょうか。
─店舗視察などすると、対面カウンターがありカウンセリングに人手をかける態勢になっているのに、人が配置されていない化粧品売場も多くみられます。
遠藤 そもそも接客することとカウンターを設置することは同義ではありません。私たちの店では対面カウンターはほぼつくらず、側面接客がメインです。椅子と鏡をどこかの壁面に置くだけで立派な接客スペースになります。DgSは気軽に買えるというのが魅力なので、気楽に買える場所としての接客のあり方、そのためのハードのあり方を考えるといいのではないでしょうか。
DgSの売場を見ていると、メーカー、ブランド単位で単純に区切られているという印象を受けます。私たちは什器を設計する際は、商品の取りやすさや出会い方などを徹底的に考えています。DgSは規模が大きく、防犯も考慮しなくてはいけないので大変だとは思いますが、効率的に買物できる什器はどうあるべきかを考えて設計するのがいいと思います。
─効率重視ではなく、楽しさ重視の「面白い」店づくりをしたい場合、「面白い」とはどういう売場でしょう。
遠藤 様々な要素が複雑に絡み合うと思います。売場レイアウト、動線設計、編集売場の配置、そもそもどういうブランドを品揃えするかなど、それぞれの要素を組み合わせて、自分が探している商品にいかに出会うか、新しい発見をするか、その「わくわく感」を引き出せるのが面白い売場だと思います。
卸との良好なネットワーク構築はスピーディな商品改廃には必須
─韓国コスメに代表されるように、最近の流行は移り変わりが早く、店舗は人気商品の導入、改廃が追いつかない、その結果、欲しいものが欲しいときになく、チャンスロスが発生することもあります。これにはどのように対応すべきでしょうか。
遠藤 トレンドが変われば、単純にそれに対応しなければいけないでしょう。韓国コスメはブームではなく定番のカテゴリーのひとつとなっていますが、プレーヤーは目まぐるしく変わります。昨年大流行していたものが今年は売れないということは普通にあります。流行の変化は現場が努力し、わかっているので、高頻度で入れ替えることは、非常に大事です。
DgSが韓国コスメを扱っているのなら、本社のMDの感覚、センスを磨くためにどう情報をインプットするかは大事です。放っておくと市場では終わっている商品が棚を占拠することになるので、トレンドに合わせた商品の改廃はキモになります。
感度高くアンテナを張って、取引先の皆さんとも面白い商品があれば、すぐに仕入れられる態勢を構築しておく。いま取引している卸、代理店が人気ブランドを扱っているとは限らないので、複数の取引先のネットワークをつくるのも重要です。はやっているからといって自社でメーカーと直接取引することほど怖いことはありません。人気商品がすぐに不良在庫化する危険があります。
卸との関係性を強くすることは大事です。最近、あらたさんが韓国コスメに力を入れているので、私たちもよい関係を築かせてもらって、商品を紹介して頂いています。
短くなる商品サイクル データ分析でロングセラー化を支援
─先日、御社のデータを活用した新規事業の説明会で、制度品メーカーの方が、新商品を開発し続けて、新規客を獲得するのは大変なコストだと語っておられました。目まぐるしいトレンドの変化に対応しようとすると莫大なコストがかかることについてはどう思われますか。
遠藤 新商品開発はどのメーカーにとっても苦しいものではないでしょうか。一番いいのは、開発した商品の人気が長持ちして売れ続けることです。
しかし、いまの時代は頑張って新商品を開発して売上をつくると、短期間で売上が鋭角的に落ちていく。この繰り返しです。そして、そのサイクルが早くなっています。鋭角的に落ちていくのを防いで、緩やかに落ちていくのなら、つまり、ヒット商品がある程度の期間そのままであり続ければ、それほど早く新商品を開発しなくていいはずです。
そのために、私たちは@cosmeはじめ、アイスタイルに蓄積された膨大なデータを分析して、どのようなお客様にどのような情報を伝えていけばよいのかを解明しようとしています(編集部注:アイスタイルではデータに基づいたソリューション提供を事業化するため、アイスタイルデータコンサルティング株式会社/ISDCを2025年2月に立ち上げた)。
新商品を発売して投資回収が終わらないうちに、また新商品の開発、発売を余儀なくされる。この悪循環が続かないように、データ分析に基づいて自分たちの商品の良さをわかってくれる人たちとコミュニケーションしてロングセラー商品を育成する必要があると思います。ISDCではそれをお手伝いしています。
─韓国コスメのように小回りの利く企業と制度品メーカーでは、投資の負荷が違うように思いますがいかがでしょうか。
遠藤 ヒット商品がどれだけ長持ちするかは、トレンドに合わせる能力と商品力の掛け算だと思います。日本の制度品メーカーのヒット商品は長持ちする商品が多くあります。
一方で、プロダクトライフサイクルが短くなっていることは確かなので各メーカー、開発から発売までをいかにクイックにできるか、そこには向き合っているし、必要だと思います。
《取材協力》

代表取締役社長 COO
遠藤 宗氏