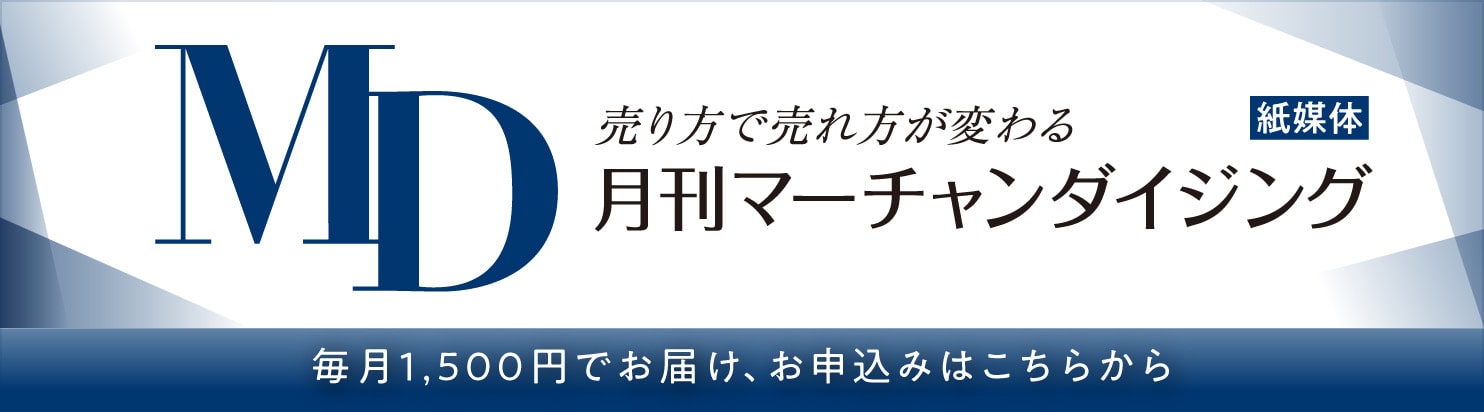若い世代のお客様を中心にブランドイメージがやや低下
「7-Elevenの変革」と題した会見の冒頭、デイカス氏は近年の停滞を次のように指摘した。近年のセブン−イレブンの停滞を客観的に言い当てている。
「私たちは長年のマーケットリーダーであり、今でも圧倒的なトップポジションを維持しています。そこには多くのポジティブな面がある半面、実はとても危険な環境でもあると考えています。長期にわたる成功は、われわれの事業に慢心をもたらし、イノベーションやエクセキューション(計画や戦略を実行に移すこと)のスピードを低下させるのです」
国内セブン−イレブンの店舗数は2万1,743(2025年2月期)で創業以来、毎年増店、チェーン全店売上は5兆3,698億円でコロナ禍の2020年度、2021年度を除けば、こちらも創業以来、一貫して増加させている。ただし、2010年代後半から伸び率に鈍化傾向が見られる。加盟店の損益は公表されていないが、増店の鈍化は最終利益が厳しい状況に置かれていると推測できる。
それは業態の垣根を超えた競争環境の激化に加えて、高騰する人件費を十分に吸収できる利益確保が難しくなっているからであろう。売上を上乗せできる新たな商品やサービス、カテゴリーの創出、さらに加盟店の運営コストを抑える仕組みづくりに後れをとっていると筆者は認識している。
競合チェーンとの比較においても消極的な部分があるとデイカス氏は次のように指摘する。

代表取締役社長最高経営責任者(CEO)
スティーブン・ヘイズ・デイカス氏
「セブン−イレブン・ジャパン(SEJ)は、お客様とのコミュニケーションやエンゲージメント(深いつながりを持った関係性)において、競合他社に遅れをとっています。率直に言って、競合他社に比べてやや受け身であり、コミュニケーションへの投資の一部は誤った方向に進んでいました。その結果、特に若い世代のお客様を中心に、ブランドイメージがやや低下しています。高齢のお客様からは依然として強い支持を得ていますが、若い世代のお客様からの支持は減少しています。SEJのリーダーシップチームはこの問題を認識しており、迅速に対応を進めています」
利用者とのコミュニケーションに関して、最も強い来店動機は、加盟店のオーナーや店長、その他従業員による接客になるだろう。セブン−イレブンに限らず、コンビニフランチャイズに加盟した初期のオーナーは、業種店から転換した商人が多かった。
その土地で古くから酒販店、米穀店、青果店、食料品店などを営んできた商人は、顔と名前を覚え、御用聞き(配達サービス)を実践してきた。特にセブン−イレブンは、創業期に酒販店からコンビニへの業態展開を集中的に促してきたので、地域と深くつながった加盟店オーナーが力を持ってきた。
一方で、90年代後半から家庭用パソコンが普及。続いて携帯電話、スマートフォン、タブレットなどを一般の人たちが持ち、いつでもどこでもインターネットにアクセスできるようになった。そこでは、多様なチャネルを通した、利用者との双方向のコミュニケーションが求められるようになった。
コンビニ各社はキャンペーンの告知や、クーポンを発行する自社アプリを開発。利用客の囲い込みに注力している。大手3チェーンの自社アプリ、それぞれ2,000万から2,500万の累計ダウンロード数を記録している。自店のカウンターでのフェース・ツー・フェースのコミュニケーションから、自社のアプリやSNS、さらにはAIカメラを用いた商品のお薦め、店内のデジタルサイネージなど、利用客との接点が多様化していった。
セブン−イレブンが、この分野で競合チェーンと比較して目に見えて遅れているとは思えない。お届けサービスの「7NOW(セブンナウ)」を自前で開発し、既に全国で展開している。ただし、7NOWを除けば、競合チェーンをリードする存在かといえば、決してそうは見えない。
初期のセブン−イレブンを支えた加盟店オーナーは世代交代をしている。現場の力が強かった分、最新デジタルを活用した合理化に後れをとった。特にデイカス氏が指摘する「若い世代の支持の減少」に対しては危機感を持って当然だ。
「優秀な外部人材の獲得も含め、コミュニケーションチームの刷新と強化を進めています。商品開発、店舗活動、そしてコミュニケーションへの統合的なアプローチを確立することで、事業運営の変革を進めています」(デイカス氏)と対策を説明する。
もう一つ卑近な例として挙げられるのが「上げ底」騒動である。SNS上でセブン−イレブンの弁当や惣菜が以前の商品と比較して「上げ底」が目に見えて増しているといった指摘が、画像や動画とともに拡散した。
週刊誌の取材に(当時社長の)永松文彦氏が強く反論したことも火に油を注いだ感があった。SNS情報に敏感な若い世代に対しては非常にネガティブな発信になった。この一連の騒動が二度と起きないような万全な体制を組む必要があるだろう。
AIの活用、データ分析などにパートナーの協力が必要
加盟店を軸とした生産性向上は喫緊の課題である。前述したように店舗従業員の人件費は上り続けていく。コスト削減に取り組むと同時にトップライン(売上)も高めていく必要がある。デイカス氏は次のような問題意識を持つ。
「テクノロジーと膨大なデータを活用し、お客様にとってより便利で魅力的なショッピング体験を提供すると同時に、店舗(特にフランチャイズ加盟店)の生産性と収益性を向上させる新たなモデルを構築することです。グローバルな展開と業界をリードする規模を持つ私たちは、これを実現できる立場にあります。当社は日本に約1万1,000店舗、北米に約1万3,000店舗を展開しており、この2つの地域だけで毎日約3,000万人ものお客様が当社の店舗に来店されています。私たちはサプライチェーンとマーチャンダイジングにおいて大きな強みを持っています」
それには最新デジタルの活用が欠かせない。デイカス氏は次のような認識を示す。
「AIの活用、オートメーション、データ分析といった分野にはまだ強みを持っていません。これを実現するためには、パートナーの協力が必要です。幸いなことに、競合他社もこの分野においては先行しているわけではなく、この分野における強みを実現するには非常に大きなチャンスがあります」
最新デジタルの取り組みが十分ではないことを伸びしろと捉える。競合するローソンは親会社の三菱商事に新たにKDDIが資本参画し、2024年8月に出資比率を50%ずつとする共同経営パートナーとなった。KDDIが強みとするITを強化し、コンビニの未来を描こうとしている。
デイカス氏も業界動向を見ながら、柔軟な姿勢を示している。
「重要なのは、新しいテクノロジーを生み出すことではありません。テクノロジーは既に存在し、日々急速に進化をしています。つまり、テクノロジーを活用し、お客様により良い体験価値を提供し、パートナーに新たなモデルを提示することです。これは一朝一夕に実現できるものではありませんが、私たちが注力していかなければ決して実現できません」
単に変化に対応するのではなく受け止め、その変化をリードする
セブン&アイHDは2025年9月に中間持株会社のヨークホールディングスを投資ファンドのベインキャピタルに売却する。イトーヨーカ堂を祖業とするセブン&アイHDはコンビニに特化した事業体になる。
日本のセブン−イレブンを実質創業した鈴木敏文氏も2016年4月に経営から退き、イトーヨーカ堂を創業した伊藤雅俊氏は2023年3月に亡くなっている。
デイカス氏は今こそ創業の精神を取り戻すだけでなく、それを乗り越える覚悟が必要と説いている。
「この先、私たちには多くの変化が待っています。しかしながら、一つだけ決して変わることがないのは、当社の基本的な理念です。私たちの創業者(伊藤雅俊氏、鈴木敏文氏)は、どのように事業を行うべきか、とても明確なビジョンを持ち合わせていました。ステークホルダーからの信頼獲得のために、私たちの創業者は変化を受け止めることを求めています。
単に変化に対応するのではなく、受け止め、その変化をリードすることを求めています。(中略) 現在、私たちの課題の一つは、この創業者の精神が失われていることだと考えています。特に日本において、私たちはかつてほどお客様からの信頼を獲得できていません。また今、私たちは創業者がしたように、積極的に変化を受け止めることができていません。本社を中心に、私たちは少し現状に甘んじてしまっている部分があります。だからこそ、創業の精神を取り戻すことがとても重要なのです」
デイカス氏は創業の精神と表現するが、伊藤雅俊氏、鈴木敏文氏の跡をたどることでは決してない。既存の枠に捉われず、自らの限界を超克する取り組みが令和の時代に求められている。