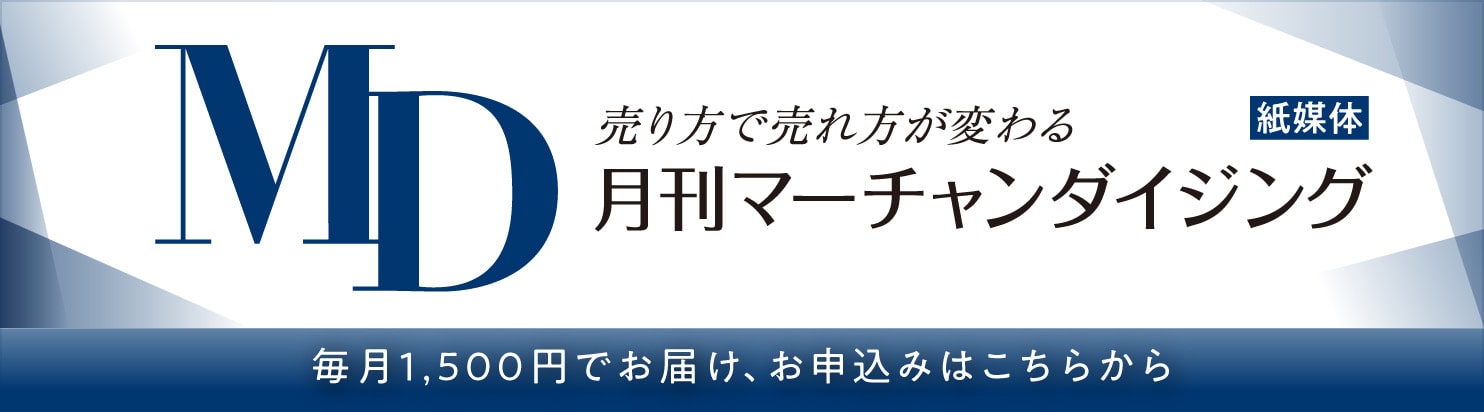低価格PBを定着させた後上位ブランドのビールを投入
コンビニの商品開発は「単品」を基本にしている。チェーン本部は売れる単品を推奨し、フランチャイズ加盟店は自らの意志で売っていく。
わずか40坪の売場面積と3,000品目で商売を営むには、売れない商品を並べる余裕はない。商品部は、1万数千店から2万店以上の加盟店に送り込んだ商品が売れなければ責任問題になるし、加盟店は発注した商品が売れずに廃棄ロスが増えれば、“日々の生活が脅かされる”のだ。
アジアに出店する日系コンビニや地元ローカルの店を見ても、日本ほど商品が入れ替わるコンビニは他にない。日本のコンビニは1週間に約100品目の商品を新たに投入している(100品目が退場する)。新商品が来店客にとっては情報であり、トレンドや季節を演出してきた。もちろん「おいしさ」が大前提にあり、単品量販ができない業態特性上、付加価値の高い商品を中心に品揃えしてきた。
しかしながらコンビニは今、逆風にさらされている。今年4月の消費者物価指数は(生鮮とエネルギーを除き)前年比3.5%の上昇、5ヵ月連続で3%以上となり、消費者の生活防衛意識は高まっていく。
食品に関しては、生鮮素材から調理をすれば加工品を購入するよりコストは低い。米飯弁当や調理麺、調理パン、惣菜をメーンにそろえるコンビニは、どうしても割高に映ってしまう。
それでも「本当に価値のある商品を提供すれば、お客様には喜んで買っていただける」が、コンビニ業界の理念ともいえるし、商品に価値を認めてもらえれば、多少の価格差は問題ないとする考え方はいまだに支配的である。そうした「価値」を前面に打ち出したコンビニの新商品を見ていきたい。

一つ目はセブン−イレブンの「有頂天エイリアンズ」。今年5月21日より首都圏および長野県・山梨県のセブン−イレブンで順次先行発売、今後は全国のセブン−イレブンでの展開も予定している。
同商品は一般的なラガービールの特徴である「透明ですっきり・苦みが強め・穏やかな香り」のテイストとは大きく異なる「濁ってまろやか・苦み控えめ・トロピカルな香り」といった特徴を持つ。昨年12月に長野・山梨ほか一部地域のセブン−イレブンでテスト販売を実施したところ、想定より1ヵ月前倒しで完売したことが今回の販売拡大につながった。
ビールを大まかに分類すると、下面発酵で造られるラガービールと上面発酵のエールビールに分類される。日本のビールメーカーが製造する商品はほとんどがラガー系で、消費量を見るとラガー系が95%を占めている。米国の80%、ドイツの70%と比較しても、日本の消費者はラガー系を選択“させられている”。
今回の有頂天エイリアンズはエールビールの一つに分類される。セブン−イレブンは、従来の大手ビールメーカーが造るラガービールに加えて、日本ではマイナーの領域にあるエールビールを後押しする格好になった。
“後押し”というのは、2024年12月にセブン&アイ・ホールディングスはサントリーと共同開発したエールビール「セブンプレミアム エールズ350ml」(180円、税別)をグループの約2万2,300店舗で販売を始めている。同年10月に一部地域で先行販売を実施したところ計画した数量の2倍を上回った実績を持つ。
エールビールを180円の低価格PBで定着させ、その上位ブランドに318円のクラフトビールを品揃えした。近年、日本のビール市場でも小規模な醸造所が造る多種多様なクラフトビールが飲食店やスーパーマーケットに並ぶようになってきた。日本のクラフトビール市場は10年間で4.6倍に伸長している。
日本クラフトビール業界団体連絡協議会が2024年4月に公表した「クラフトビール統計」によると、ビール系(新ジャンル含む)の中でクラフトビールのシェア(数量)は0.96%と1%も満たしていない。その意味では、今後も伸びしろはあるだろう。※
※本稿のヤッホーブルーイングはキリンビールと資本関係にあり、商品の一部はキリンビールの製造工場を使用しているため「クラフトビール」に含めるか否かは意見が分かれ、上記のクラフトビール統計に同社が含まれているかは公表されていない。ただし、商品のバラエティと同社の開発体制から本稿では「クラフトビール」として記述している。
ライト層に訴求して市場拡大
セブン−イレブンは2021年下期の商品政策で「ワクワク」をキーワードにした販促の強化を打ち出した。今回は個性的な味を追求するクラフトビールの「ワクワク」、そして「選ぶ楽しさ」を提案して、ビール市場を拡大したい狙いがある。
セブン−イレブンの説明によると、日本の成人人口は約9,000万人で、飲酒に関して「週1回以上」が2,000万人、「月1回以上」が2,000万人、「飲酒しない」が5,000万人で、この「飲酒しない」のうち「きっかけがあれば飲む」が2,000万人いるという。
セブン−イレブン・ジャパン商品本部飲料・酒・加工食品部シニアマーチャンダイザーの上條智氏は次のように市場を見ている。「われわれは上位2,000万人にお酒を提案しているが、月1回以上の方、そしてきっかけがあれば飲む方たちに購入いただければ、お酒のマーケットは2倍にも3倍にも広がるチャンスがある」
そのきっかけがワクワク感を発信するクラフトビールにあると上條氏は見ている。実際にセブン−イレブンで既存のクラフトビールを購入する客層は40代男性が30%、50代男性18%、40代女性12%となり、レギュラービールの購入客層(主に中高年の男性)と比較して若く、女性比率が高いという結果が出ている。こうした新しい客層へワクワクする仕掛けがビール市場開拓には必要で、クラフトビールは有効になると見る。
併買商品についても新しい傾向が出ている。クラフトビールの併買商品は「香ばし炒めの玉子炒飯おむすび」「赤坂璃宮監修五目春巻」「たことブロッコリーバジルサラダ」といった食事としての買い合わせが多いことに特徴を持つ。
一方のレギュラービールは「ななチキ」「揚げ鶏」「牛肉コロッケ」など、おつまみとしての買い合わせが多い。クラフトビールの購入客層は、食事と一緒(with)にお酒を楽しむ傾向がある。こうしたアルコールに対するライト層にも市場の広がりを期待できるだろう。
「日本には地域に限定したクラフトビールがある。エリアごとに、さまざまなビールに対応していきたい。エールビールについては、われわれのセブンプレミアムでも扱っており、多種多様な商品を紹介しながらビールの飲用人口を増やしていきたい」(上條氏)。
セブン−イレブンはクラフトビール系の最大手と組んで、ユニークなブランド名を発信しながら、新たなマーケットを開拓していく。
カテゴリーを横断して同じテーマで商品展開
ファミリーマートはスイーツに注力。「コンビニでスイーツを買うならファミリーマートと一番目に想起されるチェーンになることを目標にしている」(ファミリーマート商品本部スイーツ部部長の山岡美奈子氏)

アフタヌーンティーとは、2019年10月にアールグレイの紅茶を使用した焼き菓子4種類を発売したのが取組のスタート。この女性層に支持のあるブランドとの初コラボ商品が支持されたことで、他のカテゴリーの商品を拡大し、これまで継続してコラボレーションを実施している。
「コラボレーション商品は数量限定が多いのだが、定番商品として展開しているものもある。主に女性のお客様から厚く支持をいただいている」(山岡氏)
こうした背景から、ファミリーマート商品で“アフタヌーンティーを楽しんでいただく”をコンセプトに、カテゴリーを横断して、コラボレーションでは過去最大規模となる新商品16品を含む合計25商品を一斉に展開することにした。「カテゴリーを横断して同じテーマの商品を展開することで、買い合わせ点数のアップや食べ比べなどの話題化を狙っている」と山岡氏。最近、コンビニスイーツで“ヒット商品”を聞かなくなった。単発のヒット商品は狙いにくいのか。
「コラボレーションによる品質向上、そして話題性も大きい。単発の商品ではなく、今はカテゴリーを横断した“総力戦”で臨んでいます」(山岡氏)
ブランドの力を借りながら、共通のテーマで各カテゴリーの底上げを図っていく考えである。生活防衛の厳しい環境下にある顧客に日常の“ワクワク感”を、どう訴えていくかが問われている。