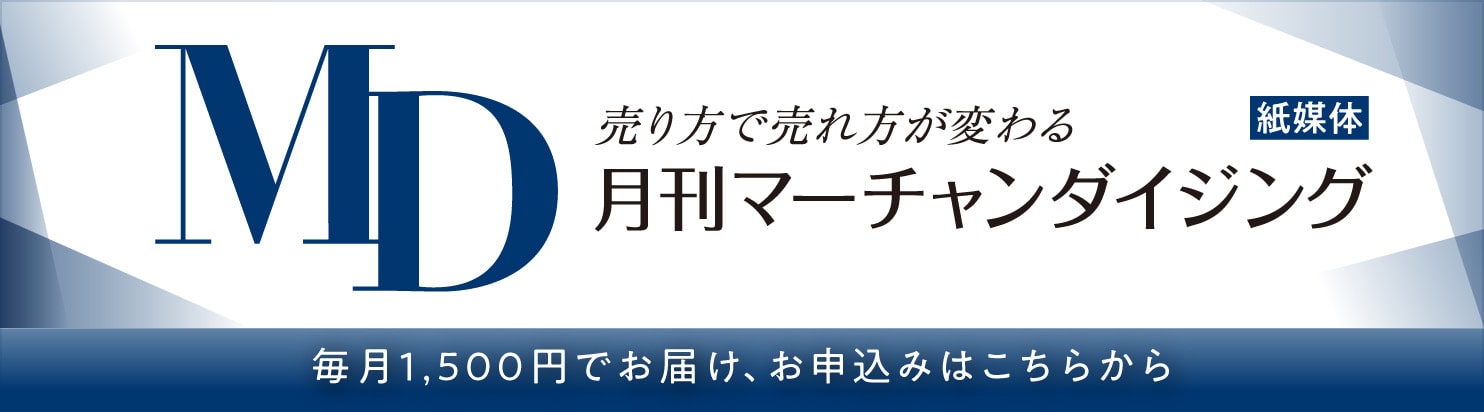新たなお客様体験と店舗運営で売上を高め作業人時の削減図る
これまでの経緯に簡単に触れると、2024年、KDDIがローソンにTOB(株式公開買付)を実施、ローソンはKDDIが50%、三菱商事が50%を出資する共同経営体制に切り替わった。
2024年9月の会見で3社のトップが顔をそろえ、情報通信のKDDIが経営に参画することで、ローソンは、テクノロジーを強化した「Real×Tech Convenience(リアルテック・コンビニエンス)」として業態の進化を早めていくと方向性を示した。その「未来のコンビニ」を3社の会見から9ヵ月強を経てお披露目となった。
オープン当日、会見に臨んだKDDI執行役員パーソナル事業本部パートナーグロース本部長の久木浩樹氏は、“リアルテックローソン”の意義を次のように述べた。
「少子高齢化に伴う生活インフラ維持の危機に対し、テクノロジーを活用することで、コンビニの位置づけを地域のマルチハブとなるようにする。リアルテックローソンが地域における最重要インフラ拠点となり、さまざまな社会課題の解決に貢献することを目指していく」。
この構想の一環として、リアルテックローソンをKDDIが直営の形で運営する。KDDI社員がコンビニ経営に自ら携わることで、その知見を蓄積していく。さらにKDDI社員がファーストユーザーになることで、各種実験検証を加速させ、ローソン店舗への波及速度を高めていくという。
このリアルテックローソンは二つの取り組みを強化し、その中で成果の見られる施策については全国のローソンに導入していく。第1は「新たなお客様体験の提供」、これはトップライン(売上)を高める施策であり、主に客数アップと買上点数の向上を図る。
第2は「新たな店舗運営の確立」となる。AIなどを用いて店舗運営の適正化を図り売上の向上を目指し、またロボティクスの導入により店舗人時数の削減を図る。
相談所で幅広いサービスを提供 日常生活のお困り事に応える
第1の「新たなお客様体験の提供」についてはAIサイネージを設置した。AIカメラを活用した行動解析により、商品棚前のお客の行動に合わせたレコメンドを実施する。
例えば、商品棚の前に滞在する時間が長ければ、商品選択に悩んでいると判断し、棚に設置したサイネージでランキングやお薦め商品を表示する。
また、商品に手を伸ばした際には「そのお弁当と一緒にお茶をご購入いただくと50円引き」といった関連商品のレコメンドや、必要とされる情報を表示する。
なお、このサイネージでは、性差や年齢、体形などお客の特徴に合わせたレコメンドは実施しない。AIがお客の特徴を捉えた上での情報提供も可能だが、サイネージが周囲のお客の目に触れるため、個人に関係するレコメンドは控える。
一人ひとりの状況や行動にあわせたタイミングで情報を伝えることで、適切なレコメンドやサポートを届けて、主に買上点数の向上を後押ししていく。

サイネージの二つ目は「プライスレール連動サイネージ」。商品棚のプライスレールにタッチ式サイネージを導入して、お客がそれに触れると、ゴンドラ上のサイネージに商品紹介が表示されて詳細な情報を得ることができる。お客は自らの能動的な行動により納得感を持って購入できるようになる。
三つ目は店内の壁面に設置したサイネージ。ここでは「画像生成AI」を活用した壁面緑化演出「MIRRORGREEN ミラーグリーン」により「朝・昼・夜」に応じた演出を行う。1日に複数回来店するお客は、時間ごとに異なる店舗空間により購買意欲を増すことになる。
このサイネージは店舗の販促にも活用する。例えば「からあげクン」を、店内のサイネージを使って、ちょうど揚げたてのタイミングで訴求することができる。買上点数のアップにつなげられる。販促だけではなく、高輪ゲートウェイシティに実装されている都市OSとサイネージを連動させて、地域情報をリアルタイムで伝える拠点機能を強化させていく。

例えば、天気や電車遅延、周辺の混雑情報などをリアルタイムで配信し、お客が店内にいながらリアルタイムで情報を得ることを可能としている。
「その日の天候や温度に合わせて、熱中症対策の商品をレコメンドしたり、街のイベント開催に合わせた食品をレコメンドするなど、お客様の体感、体験と購買行動を結びつけていく」(久木氏)
これは後述する店舗運営に関連するが、周辺の人流データなどをもとに需要予測の精度を高めて在庫の最適化によるフードロス削減も検討していく。
「新たなお客様体験の提供」の目玉になるのがリモート接客の「Pontaよろず相談所」。店内の一角にブースを設置、リモート接客により、通信・ヘルスケア・金融・清掃・家事代行など、さまざまなサービスについて、ビデオ通話を通じて各分野の専門スタッフに相談できるようにした。このリモート接客には、KDDIの提供する「次世代リモート接客プラットフォーム」を導入している。
お客に対しては、自宅のPCを使用せず、わざわざローソンの店内でリモート接客を受けることの、利便性とサービス内容の優位性を上手に訴求する必要があるだろう。
その一つとして「日本で初めてとなるご自宅以外の場所でオンライン診療、オンライン服薬指導が受けられるというサービスを開始する。これにより、すきま時間で診察を受け、常用しているお薬を処方してもらい、自宅で受け取っていただけるなど、さまざまな便利な使い方が可能となる。
AIアバターが会話形式でナビゲートすることでパソコンなどが苦手なお客様でも安心して利用いただくことが可能となる」(久木氏)と、店内のリモート相談所を案内していく。
また過疎化対策にも活用していく。「地域によって各種相談手続きを行える場所が近くにないケースは増えてきている。相談所により幅広いサービスを提供し、日常生活のお困りごとをリモート接客で解決し、ローソンが欠かせない存在になることを目指していく」(久木氏)。
アルコール類、たばこ購入には3Dアバターが遠隔から年齢確認
第2の「新たな店舗運営の確立」について、ローソンでは2030年までに店舗オペレーションの30%削減を目標としている。リアルテックローソンでは、ロボティクス活用による飲料陳列や店内清掃、調理などの業務をロボットにサポートさせている。

ロボティクス活用は人時数の削減を目的とするだけでなく、例えば、飲料陳列ロボットではデジタル在庫棚の組み合わせにより、売場棚と在庫棚の飲料在庫量、売場棚の棚割や日々の欠品状況などを、専用アプリを通じて可視化させていく。これにより在庫管理や余剰在庫削減を実現させていく計画である。
また、従業員が身に付けるタグから店舗業務量の定量データを算出するシステムを導入した。業務量を可視化して、業務最適化に向けた課題を抽出していく。
一方で、防犯カメラの情報をもとに棚の充足率やお客の行動を可視化。そのデータをもとに、「AIエージェント」が改善策の提案、検証を支援する。これまでの店舗運営で、属人的、感覚的だった意思決定を、AIエージェントのデータに基づいて判断することを可能にした。
セルフレジの支援にはアバターの遠隔接客を採用している。お客のセルフレジ操作を遠隔からサポート、新たに3Dディスプレイによってアバターを立体的に表示して、より豊かなコミュニケーションに期待する。
ここではアルコール類、たばこ購入の際、3Dアバターを通じて遠隔から年齢確認を行うことで、店内の人時数の削減にも貢献できる。アバターは複数店舗を掛け持つため、チェーン本部と加盟店の全体により、サービス向上と効率化を実現している。
コンビニ経営の最大の課題は、加盟店利益の確保にある。サービスを高め、売上も上げて、店舗運営のコストを下げる。未来のコンビニは夢のような話ではなく、コンビニ業界全体の存続をかけた課題でもある。