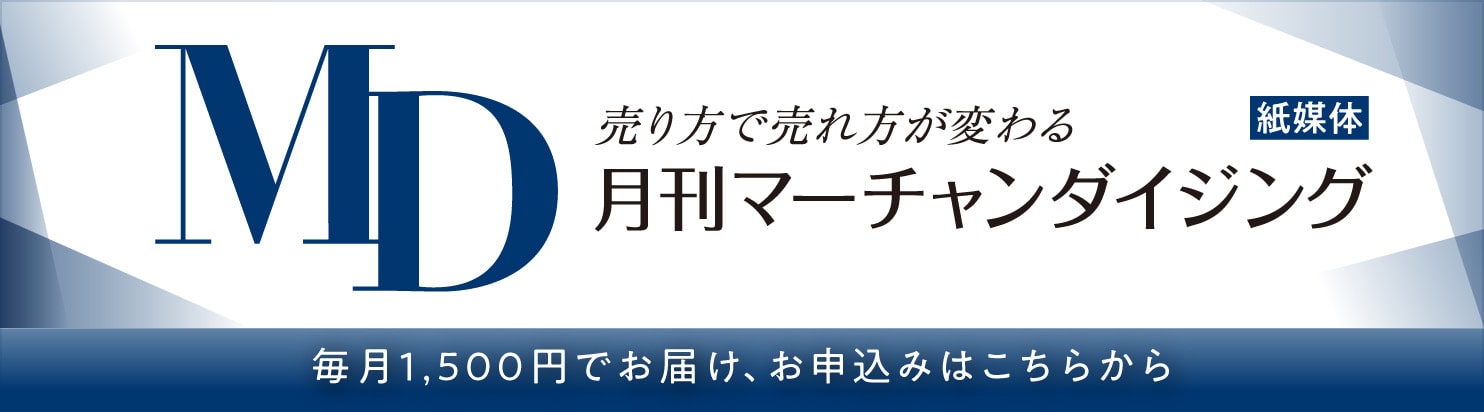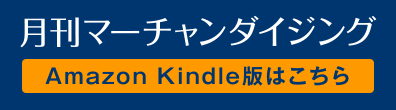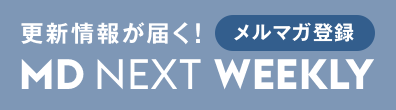コロナ禍後の都市部で影響力を拡大
都市部の食品マーケットの“覇者”は2020年のコロナ前までは間違いなくコンビニだっただろう。その存在は今でも大きく、たとえば東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県で確認すると大手コンビニ3社の店舗数はセブン−イレブン6,873店、ファミリーマート4,801店、ローソン4,003店舗となっている(セブン、ファミマは6月末、ローソンは2月末、いずれも各社「ウェブサイト」より)。コンビニ大手3社がこのエリアで合計で1.5万店以上の店舗数を有していることが分かる。
しかしコロナ禍とその後の混乱、人件費上昇などで物価上昇が続くとコンビニには逆風が吹き始めた。たとえば最大手セブン−イレブンの既存店売上高は2024年度(2025年2月末)で前年比で+0.2%、同客数+0.2%、客単価±0%であり成長が止まった状態で、物価上昇が向かい風になっている様子が想像できる。
東京など1都3県の都市部は小売業にとっては難しいエリアであり、これはドラッグストア(DgS)など他の小売業にも当然、当てはまる。出店するに際しては十分な敷地を確保することは難しいし地代・家賃も決して安くはない。
人件費は高く、またコンビニなどとの競合を考えれば運営に携わる人員の確保は難しい。人口は多く市場は大きく見えるが、世帯では単身者が多く食の“財布”は必ずしも大きくはない。
またコンビニは本部との契約は粗利分配方式を採用するフランチャイズ契約が多いため、物価が上昇しているからと言って売価を下げていくと加盟店の収入減が生じる可能性がある。
都市部は出店においても、運営においても、インフレ期の価格対応についても難しいエリアであることは間違いない。目指す“近便短+安”を実現するのが難しいエリアである。
その都市部で影響力を拡大しているのが都市小型店、とくにイオングループが展開する「まいばすけっと」である。
イオン(株)の吉田昭夫社長は2025年2月期の決算会見の中で、人口減少で生活者ニーズを注視したエリア対策が必要と述べたうえ「アーバンエリア(都市部)は人口流入が進む成長市場であり、そのシェア拡大には強いフォーマットを必要とする。
まいばすけっとは首都圏に1,200店を超える存在になり近さとコンビニに比しての価格の安さが支持されて順調にシェアを伸ばしている。コンビニに対する競争力を付け安定的に利益を創出できる業態にまで成長してきた」と評価する。
さらに利益を安定的に創出できる業態となれば都市部でも賃料は高い額まで出せ許容度が高まり、出店候補地の拡大は可能になるとし「2030年までに現在の2倍の2,500店舗、最終的には首都圏で5,000店態勢を敷きたい」(吉田社長)と表明した。
ネットスーパーなどのオンラインチャネルと合わせてまいばすけっとを首都圏都市部でのシェア拡大の主力とすることを言及したのである。
ではこのイオングループの都市部のエリア戦略の中心にまで進化したまいばすけっとの特徴は、どんなところにあるのだろうか?
2005年から京浜地区出店 1都3県1,200店の店舗網
まいばすけっとは、イオングループのGMS企業・イオンリテールの1事業部門として始まった業態である。横浜市保土ヶ谷区の丘陵地に2005年12月、1号店を開店しそこから出店を開始している比較的新しい企業である。当初の店は現在同様小型だが店内で簡単なベーカリーを焼いたりする機能を有していたことを筆者は記憶している(図表1)。