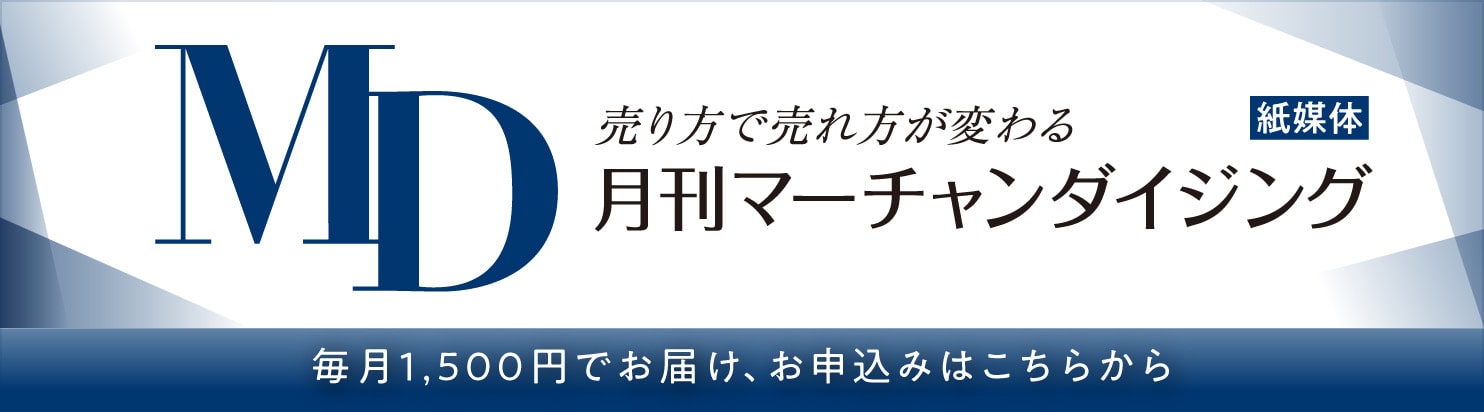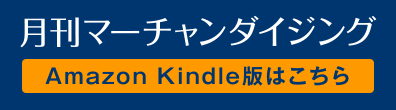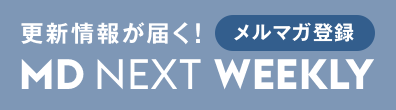商品マスタの歴史的変遷
JANコードとPOS、EOS
日本の小売業は、かつて零細小売店が多数を占めるため、商品はメーカーから一次卸、二次卸、三次卸など複数の卸売業者を経由して小売店に届く「多段階流通構造」が主流であった。商品情報管理は紙ベースの仕組みによる手書きの台帳に依存していた。
1970年代初頭、アメリカでは、POS機器メーカーと小売業界団体によりUPC(Universal Product Code)特別委員会を設置し、10桁のUPCと光学式読み取り印刷を含むPOSシステムの規格が決まり導入されていった。
しかしながら、個別商品への価格表示貼り付けを廃止し、棚表示のみで済ませることは、雇用削減につながるという労働組合と、価格の信頼性に不安を感じ、過去価格との比較が困難になることを懸念した消費者による反対が強く、効率化メリットの大きいPOSの導入は当初想定ほどには進まなかった。
当時から情報関連投資に積極的だったウォルマートでさえ、1986年末時点で566店舗にPOSを導入していたものの、1987年時点でも個別商品への値札の全面撤去は5店舗でのテスト段階にとどまっていた。
日本では1972年に財団法人流通システム開発センター(現在のGS1 Japan)が設立され、標準化に向けた動きが本格化した。1978年にはJAN(Japanese Article Number)コードが策定され、日本独自の商品識別標準が確立された。JANコードは13桁構成で、国コード(3桁)、メーカーコード(4桁または7桁)、商品コード(5桁または2桁)、チェックデジット(1桁)からなり、現在はGTIN-13として国際標準化されている。
このJANコードに対しては、労働組合や消費者からの抵抗はないに等しく、日本国内で急速に普及していった。JANコードの普及は、POSシステムでの自動読み取りによるレジ業務の高速化や、在庫管理の精度向上に大きく貢献した。
POSシステムの普及は商品マスタの重要性を大きく変化させた。バーコードを用いた販売データの自動収集によって、商品単品ごとの販売実績を把握できるようになったことで、商品マスタにはJANコードという業界標準の商品識別コードが不可欠となった。これにより商品マスタは大きく変革した。
まず、POSで販売するにはすべての商品にJANコード(または自社コード)が必要となるため、商品のシステム登録漏れが即座に店頭での販売停止につながるようになった。「商品はあるのに売れない」という事態を避けるため、商品マスタの登録業務は「あったらいい」レベルから「必須」のプロセスへと変わったのである。
POSシステムの導入は、価格管理にも大きな変化をもたらした。従来は店舗ごとに価格設定を行っていた場合も多かったが、POSの導入により本部による価格の一元管理が進んだ。また、期間限定の特売価格や会員価格、割引率などの細かな設定も商品マスタに求められるようになり、マスタの複雑さが増していった。
1980年代はアメリカのドラッグストア(DgS)を参考に、日本でDgS業態が誕生した時期でもある。個人経営の薬店とチェーンDgSの成長に大きな差がついたのは再販制度撤廃と同時に、POSを始まりとしたシステム化の要素も大きい。
発注業務においては、店長や発注担当者が直接メーカーや卸の営業担当者と対面し、紙の発注書や電話でのやりとりが中心であった。FAXによる定型フォーマットでの発注も行われていたが、その場合でも商品情報は手作業で記入する必要があり、ミスが発生しやすい環境であった。
この時代の商品マスタは、現在のようなデータベースではなく、商品または仕入れ先ごとにカードを作成し、棚に整理して在庫や価格、仕入れ先、入出庫履歴などの情報を現場で一元管理する方式であった。
1970年代中ごろから、大企業を中心にEOS(Electronic Ordering System)の導入が始まった。当初のシステムは極めて制約が多く、メインフレームコンピューターへの依存、低速通信、高額な専用回線の使用など、技術的・経済的ハードルは非常に高かった。しかし、電話や紙による発注処理から解放される利益の大きさを認識したチェーンストアが、先駆的な導入を進めていった。
1978年にはセブン−イレブン・ジャパンが初の発注専用の端末機を導入した。同社は第二世代情報システムで「単品管理」を実現し、おにぎり、弁当、飲料などの個別商品追跡を可能にした。
この「単品管理」手法は、トヨタの在庫を最小限に抑える管理技術を小売業に応用した画期的な取り組みで、1日3〜4回の配送を可能にする精密な在庫管理を実現した。
このころからセブン−イレブンを手本として、各小売業者にも「単品管理」の概念が浸透し始め、商品の属性情報(カテゴリー、ブランド、容量、製造元など)による分析ニーズが高まった。これに伴い、商品マスタに登録すべき情報項目は飛躍的に増加していった。
EDI、VAN時代の幕開け
初期のEOSは、極めて限定的な機能しか持たなかった。
《執筆》

郡司 昇氏