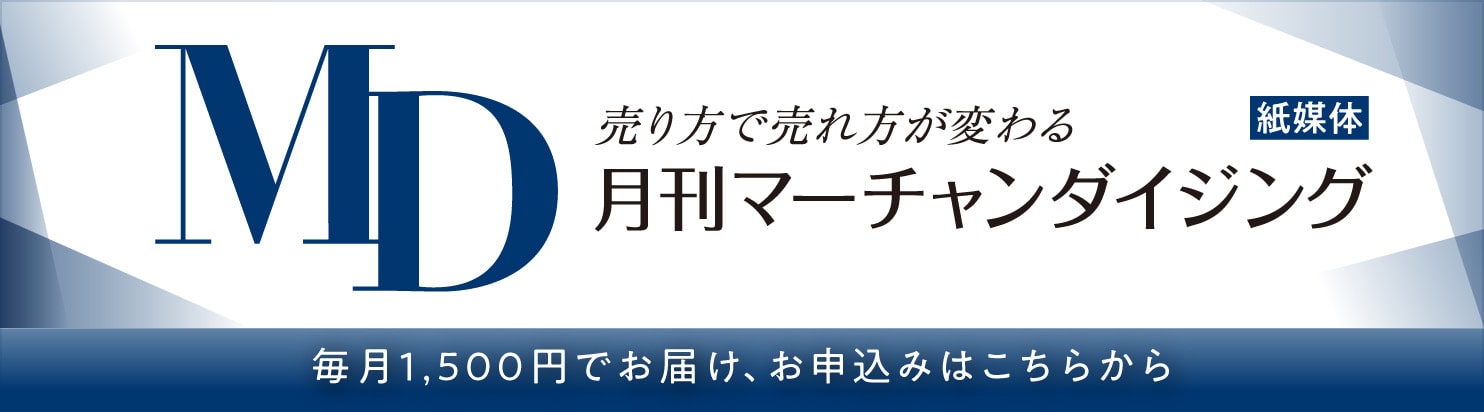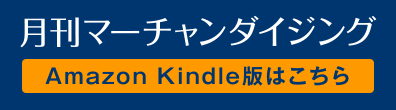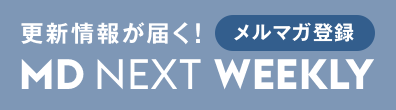ロボットがお菓子を載せて販促
「ベルク」でのMUSE「Armo One」の活用は、埼玉県の和光西大和店および北坂戸店においては2024年6月から始まっている。今回、ゴールデンウイークににぎわう店舗を見学させてもらったのは和光西大和店だ。
エスカレーターを上がって2階にある店内を訪問すると、ロボットはベルクのマスコットキャラクター「ベルクック」の大きな看板が付いた販売促進用の棚を搬送しながら売場内を巡回していた。

カートの下に収まっている円形の物体が移動ロボット本体である。販促用の場合も搬送用途等の場合も、セットされている台車の重心がロボット本体の重心と重なるよう設計されている。色は黒、または白と黒だ。
ロボットは「ベルク」のオリジナルテーマソング「Just for Your Life」を流して、「こんにちはー、ベルクックでーす!」と呼び掛けしながら食品売場内を一定のルートで巡回する。「お子さんのなかにはずっと後ろをついていく子もいる」(MUSE 笠置泰孝氏)そうだ。


販促時の移動速度はゆっくりしている。人が棚を見ながら買い回りしているときの速度くらいだ。低速でないと販促している菓子類をお客が取ってくれないのがその理由。ちなみにスタッフからは「もっと速くしてほしい」という声もあるそうだが、いまは安全を重視し、低速ベースでも運用が成立することを確認しようとしている。
のんびり動くロボットの脇を買物カートを押すお客が通り過ぎていく。意外と店舗に溶け込んでいて、パッと見だと気づかず通り過ぎてしまうかもしれない。実際、店舗内で買物をしている人の多くはチラッと目を向け、必要なら避ける程度で、あまり気にしていないようだった。
移動ロボット自体が社会に馴染みつつあることを感じる。試験導入を含めるとすでに2年半運用しているが「このロボットはなんだ?」といった意見がきたことは一度もないそうだ。
品出し業務をロボットが実施

販促作業時のロボットは、あらかじめ定められた巡回ルートを走る。一方、搬送作業のときは設定されたA地点からB地点へと動くことになる。搬送時オペレーションでは店頭の売場とバックヤードに一人ずつ分担して行う場合もあれば、一人で一度に2台を動かすこともある。
ベルクでは以前から店舗従業員用モバイル機器としてスマートフォンを使っている。その端末内にロボット用管理アプリをインストールした。管理アプリは現在もまだ開発中だが、ロボットの各種ステイタスやバッテリー状態などもわかる。

なおロボットのバッテリーはロボット後面に搭載されており、簡単に取り外しができる。充電がなくなってもバッテリーを交換すればいい。
管理アプリには「タスク管理」という項目があり、一つひとつの定型業務はこのタスクごとに管理される。例えばタスクに飲料の種類などを登録しておく。
アプリからは「飲料売場に商品を補充したい」とリクエストを出すこともできるので、バックヤードでは手が空いている時間に商品を積んで、準備ができたら、あとは「スタート」をアプリから押すだけで、クラウド経由でロボットに指示が飛び、売場の設定された場所までロボットが届けにいくという使い方ができる。これが売場とバックヤードで分担して2人で作業を行う場合だ。
起動したロボットは事前に取得している地図と初期位置を合わせると、スイングドアを自分で押し開けて出ていく。
なお店内には位置情報を示すマーカーが付けられている。バックヤードから店頭に出ると、ロボットの移動速度は遅くなるよう設定されている。販促時と同様、ロボットは音楽を鳴らし「いらっしゃいませ。ロボットが走行中です」と呼び掛けながら走行し、設定された売場まで向かう。
ロボットは500ミリリットル×24本の飲料を7、8ケースくらい載せても問題なく走行できるが、「実際には6ケースくらいが多い」という。
現状では夕方以降の時間帯に一斉に品出しする際に使われることが多いため、ロボットに積めるだけ荷物を積み、人も手押し台車を押しながら一緒に店頭に出て作業するといった状況が多いそうだ。こちらが一人でロボットを使う場合の使い方である。
なお、ロボット自体はA地点からB地点への移動だけでなく、中間地点を経由するよう設定することも可能だが、実際には「飲料なら飲料だけに集中する使い方が多い」そうだ。このあたりは店舗ごとのオペレーションで違ってくる。
ちなみに台車は、ロボットが取り付けられている状態でも普通に押せ、重さの負荷はあまり感じない。これによって売場にロボットが到着後も「ちょっと動かす」といったことは問題なくできる。
ただしロボット自体のタイヤは横には動かないので、前輪が左右に振れない状態になる。ゆえに切り返しのような動きは難しい。
ロボットをバックヤードに戻すときは「ホームボタン」を押すだけで、店舗内のどこからでもバックヤードに戻る。いったんバックヤードに戻して、再度荷物を積み込みしてもらって、また店頭に持ってこさせるといった使い方もできる。
和光西大和店では現在Armo Oneを2台を活用している。ほかの店舗でも「品出しなら2台あれば問題ない」と概算しているという。
MUSEでは「店舗では品出しの最大30%の工数が削減でき、さらにマルチユースで活用することによって約5倍のROIを実現することが可能となる」としている。「マルチユース」とは要するに棚管理とクラウドサービスだが、詳細は後述する。
利用はサブスクプラン形式となるが、具体的な費用は現時点では非公開とされている。
出会いは「Belc Digital Lab」
人手が減少していくなか、どの業態でも搬送は直接の価値を生まない業務であり、自動化が期待されている。搬送ロボットは各社から様々なタイプが出ている。なぜベルクはスタートアップであるMUSEのロボット導入に至ったのだろうか。
ベルクの原田裕幸氏は「4年くらい前から様々なロボットを検討した。だが、しっくりくるものがなかった」と振り返る。
コストや投資対効果の問題だけではない。AGV(無人搬送車)やAMR(自律走行搬送ロボット)には既存の製品も多い。だが、もともと工場や倉庫での活用を想定して開発されている。そのため、大きさや機能などのスペックが、そもそも小売業界の店舗には向いていないと感じていたという。
「スーパーマーケットは売場が狭いし、内輪差をクリアできない。お客様も常にいらっしゃる。状況は毎日異なる。そのなかでロボットをどう活用していけばいいのかと考えていた」(ベルク原田氏)
ベルクは2022年8月から、異業種・異分野の企業団体と連携してオープンイノベーションを目指す「BelcDigital Lab」という取組みを行っている。ベルクの店舗自体を一種の「実験場」とし、DXに向けた実証実験を進める枠組みだ。連携先はWEBから公募しており、そこにMUSEが応募してきたのが最初の出会いだった。
労働力不足を背景として小売店舗向けロボット開発・販売を目指しているMUSEは、2022年4月に笠置氏らが創業したスタートアップ企業だ。笠置氏は前職でも自律移動ロボットの開発と販売を担っていた。
「Armo」の実機デモの初舞台が全米小売業協会がニューヨークで開催した「NRF2024」だったことからもわかるように、MUSEは、人件費が日本の約2.5倍となっている米国をはじめとした海外市場での展開を最初から想定して事業を進めている。
現在の「Armo」の大きさと100kg可搬の能力について原田氏は「最高だ」と絶賛する。「唯一無二なんですよ。こんなに小型でパワーがあって、ハンドリングが良くて、コスト的にもハードルが高くないロボットは、我々が知る限りほかにはないと思う」。
最初に見たときには「駆動輪が空回りするのではないか」と懸念したそうだ。「ところが、静かで音も立てずに荷物を引いていく。これはすごいなと思いました」。
もちろん、もっと大重量を運べるロボットの活用も最初は考えた。
「我々の会社で一番大きいマテハン(運搬道具)は300kgです。最初はそれを運べないかとも考えました。でもそうすると当然大きくなるし、価格も上がる。そこは違うなと。やはり、日中時間帯に店頭に出しても邪魔にならないことが重要です。通路幅も狭いし複雑なので、いまの形と大きさが店舗にマッチしていると思います」
MUSEでも2年間で6回は試作を繰り返し、製品版へとたどり着いた。
午前中には販促 夕方以降は搬送補助
前述のとおり、現在、ベルクでは10店舗に導入して活用しようとしている。運用面では重量物の品出し搬送補助のほか、販促に活用している。現在の稼働時間は「1日当り、3〜4時間程度」とのこと。
「スーパーマーケットの仕事は、どうしても午前中に集中します。バックヤードのスペースの問題などもありますので、作業が集中しているなかでロボットを動かすのは現状では簡単ではありません。そこで、お客様が少ない夕方から夜間にかけて集中的に品出しを行うときに、パートさんたちがロボットをパートナーとしてうまく活用することで、1.5倍、できれば2倍くらいの効率で仕事ができるような使い方ができないか。そう考えて運用しているところです」(ベルク 原田氏)
バックヤードを見せてもらうと、1階のトラックバースから荷物が上がってきて商品を出していくラインの流れは決まっていて、そこに新たにロボットを追加して動かすことはたしかに難しそうだった。
そこで午前中はロボットが売場を巡回して、お菓子類などの商品の販促を行っている。つまり生産性を高める役割と販促の2つの使い方で活用されている。
ロボットに積んだお菓子類も「1日10個くらいは売れる」そうだ。ただし「投資対効果だけを考えてやっているわけではない」という。「いまはまだロボット技術活用の可能性をどんどん探っている段階です。『このロボットで、どこまで何ができるのか』ということです。コストばかりにとらわれていると何も生まれませんから」(ベルク 原田氏)
運用結果のフィードバックはMUSEにも随時伝えられて反映されている。
「週に1、2回くらいは必ず我々のカスタマーサクセスのチームが店舗を訪問させて頂いています。お店のスタッフに実際にどれだけ積極的に使って頂けるのかというのはすごく重要な点ですので、非常に密にコミュニケーションをとらせて頂いています。並行して、定期的に面談もやりながら課題へのフィードバックを行い、我々からも新しい機能を提案したりと、随時、コミュニケーションしています」(MUSE 笠置氏)
現場定着には時間がかかるがチャンスでもある
実際のユーザーであるパート従業員からは、最初はやはり「否定的とまではいかないけれど、『ちょっと使いづらい』とか、『もっとこうしてほしい』という意見が多かった」そうだ。「自分が運んだ方が早い」という人も多かった。
それらに対して現場で直接メリットや効率の上がる使い方を説明し、アンケートを取りながら2度、3度と改良を進めていくことで「時間はかかってますが、満足度がぐわーっと上がっていった」という。「この店は最初に導入した店ですが、ここのパートさん、アルバイトさんは、もう普通に使ってくれています」(ベルク 原田氏)
もちろん現場向けのマニュアルやトラブルシューティング集もつくった。MUSEがつくったものをベルクとしての使い方に落とし込みながら新たにつくり直していった。
MUSEの笠置氏は「使いたがらない人がいるのは逆にチャンスでもある」と考えたと語る。
「心理的に負担を感じることには何か理由があるはずです。なぜ使いたがらないのか。『めんどくさい』と考えている背景には必ず何か要因があるはず。運用上の問題なのか。機器操作の問題なのか。インターフェースの問題なのか。そこを我々のカスタマー部隊とベルクさんの本部の方々で詳細に聞き取りをして、タイムリーに反映させていきました。使いたがらない理由を一つひとつ解きほぐして、製品を良くするための材料に変えていくことが重要だと考えています」
改良点はロボットの止まり方やスタートの仕方、スピード感、カーブの曲がり方、ユニットの接続方法、アプリのインターフェースなど多岐にわたる。各種の改良は常に続けており「どこが導入期だったのかわからないくらい、常に改善して変えているくらい」だという。
生産性向上≒従業員の歩数を減らす
現在の主な用途は前述のとおり飲料の補充だ。飲料は1ケース当り8kgから10kgと重い。それをひとつの台車に載せて売場に持っていき、補充を行い、また帰ってくる。これが通常のやり方だが、その途中工程をロボットに担わせるわけだ。補充と積み込みは人が行うしかないが、運搬ならロボットでもできる。バックヤードのA点で積み込んだ荷物を、店頭のB点で受け取って補充することで、作業を効率化する。
「Armo」にはオプションユニットを使うことで牽引する機能もあるので、将来的にはさらにカートの回収などにも応用できないかと考えているという。「ロボットを行き来させることで、人が動くことを極力減らす」ことを目指している。
歩数の減少はどの業態でも効率化の基本である。ベルクの原田氏も「人が動く仕事をロボットに変換していきたい。『人が動かない』というのが僕らの仕事の原点だと思っています」と語る。
「スーパーマーケットの仕事は発注や補充、製造、レジなど、たくさんあります。『業務で一番多いのは何か』と聞くと、みんな『補充』と言うんです。でも、我々は『人が動くこと』だと考えています。『歩くこと』です。歩行をとにかくなくす。それによって違った生産性やビジネスモデルができるんじゃないかと思って、ロボットの活用を考えています」(ベルク 原田氏)
クルべやベルクの一部店舗がローラーコンベアを使ったバックヤードから売場への品出しや、「座りレジ」を導入しているのも同じ考え方を背景にしている。「物が動く。人は動かない。それが生産性向上につながる。本当に単純なんです」(ベルク 原田氏)。
現在の食品スーパーマーケットのオペレーションが確立されたのは1990年代ごろ。そこからの脱却を考えているという。
欲張らずに進めていくことが重要
これまで両者は約3年間、互いに擦り合わせを行いながら取組みを進めてきた。では今後はどのようなロードマップを描いているのか。
「将来は全店で活用できるような環境をつくっていきたいですが、まだそこまで見ているわけではありません。まずは従業員の方々が手軽に、ストレスなくパートナーとして使ってもらえる環境・フィールドをつくることが重要です。成功事例をどれだけつくっていけるかですね」(ベルク 原田氏)
さらに今後は棚割や売価のチェックなどへと活用を進めていく予定だ。カメラその他のユニットを搭載したロボットを走行させることで売場データを収集。それをMUSEのクラウドサービス「Eureka Platform」に蓄積し、小売業者やメーカーがリアルタイムで、商品棚の画像や欠品、棚割の乖離などの解析結果を確認できるようにするというものだ。店舗運営の効率化や最適な棚割の作成を支援することが目的である。
ただ、この用途にはこれまでにも多くのベンダーや店舗が取り組んできた。ベルクとMUSEは、どこに勝ち目を見いだすのだろうか。
MUSEの笠置氏も「多くのメーカーが取り組んでいることは創業当初から認識しています」と語る。難しさは想定しつつも「一定のニーズはある。軌道に乗るかどうかについては採算性が大きなボトルネックになっていますので、我々はマルチユースのコンセプトや低コストでうまく採算に乗せていきたいと思っています。ひとつのロボットでできることをどんどん増やしていけば、ROI(投資収益率)も自然と高まっていくので、我々の強みを生かせるようになります」。
もうひとつは「欲張りすぎないこと」が重要だと語る。「棚のデータが取れるとなると『あれもしたい、これもしたい』といろいろ欲が出てきます。ですが、どこが採算ラインなのか、業務改善効果が見込めるデータ取得のレベル感、最低ラインを見極めることが重要です。国内でも多くの企業が取り組んできましたが、最初からフルスペックでいこうとして結果的に非常に高コストになって導入できなかった。そこが一番の課題なので、それをいかに回避するかが重要です」。
つまりステップバイステップで、欲張らずに進めていくことが重要だというわけだ。
「ないと明日から成り立たない」ような状況を目指す
ベルクの原田氏は「まだまだ成功事例が足りない」と語る。「まだまだ解決しないといけない問題がたくさんあります。全店に広げたくてウズウズしているけれど、問題点を解消してからでないとほこりをかぶるだけになってしまう。だからいまはぐっとこらえて我慢しています」。
MUSEの笠置氏も同意する。
「現場スタッフの方々の意見は本当にすごく重要です。いまは我々がサポートしながら使って頂ける状況をつくり出しているところもあります。本当に広がっていく状態というのは、スタッフの方々からどんどんと、いろいろな使い方も考えながら積極的にやってもらって、『これがないと明日から業務が成り立たない』くらいの状況にならないといけないと思っています。それが店舗での成功事例です。そういう状況にいかに我々が持っていけるか。そうなれば我々がサポートしなくても自然と広がっていくと思います」
いわゆるユーザーイノベーションが生まれるようになって、はじめて成功事例と言えるというわけだ。
品出し業務に使う場合は、おのずと郊外型の大規模店舗の方が効果自体は出しやすい。だが汎用性を理解できる担当者がいる店舗であれば、小型の小売店でも効果を出せるという。
なお数字としては「まだ出せる段階にない」そうだが、ロボットが搬送を担うことで補充業務に人が専念できるようになると、品出し全体の作業量を3割削減できると概算している。品出しは業務全体の4割を占めると言われているので、その4割のうち3割を削減できれば、おおよそ1割あまりの人件費を削減できると考えられる。「そうなると店舗側にも喜ばれるようになるはずだ」という。
MUSEという社名はギリシャ神話の女神に由来している。創造性にインスピレーションを与える女神だ。笠置氏の「人にインスピレーションを与えるロボットをつくりたい」という思いを託した名前である。笠置氏はこう語る。
「人とロボットは今後ますます距離が近くなる。ロボットは人間をもっと幸せにする側面があるはずです。人はロボットを見ながら今後自分はどうやって生きていくべきか、仕事をすべきか考えるようになる。ロボットは人の動きや考え方をもっとよく見るようになる。そしてロボットは人をもっと成長させていけるのではないか。そういう方向性が今後のロボットには求められるようになっていくと思う」
そして小売店舗は、その考え方を具現化できる場なのではないかと考えたという。
「人がもっとハッピーになる、クリエイティブになるような店舗から人が完全にいなくなることはない。その人たちが働くうえで、人間ではなくてもできるようなところはロボットが巻き取って、従業員さんがもっと自分たちにしかできないことにフォーカスできるような環境をつくっていく。それが今後のロボットに求められていくことなのではないかと思っています」(MUSE 笠置氏)