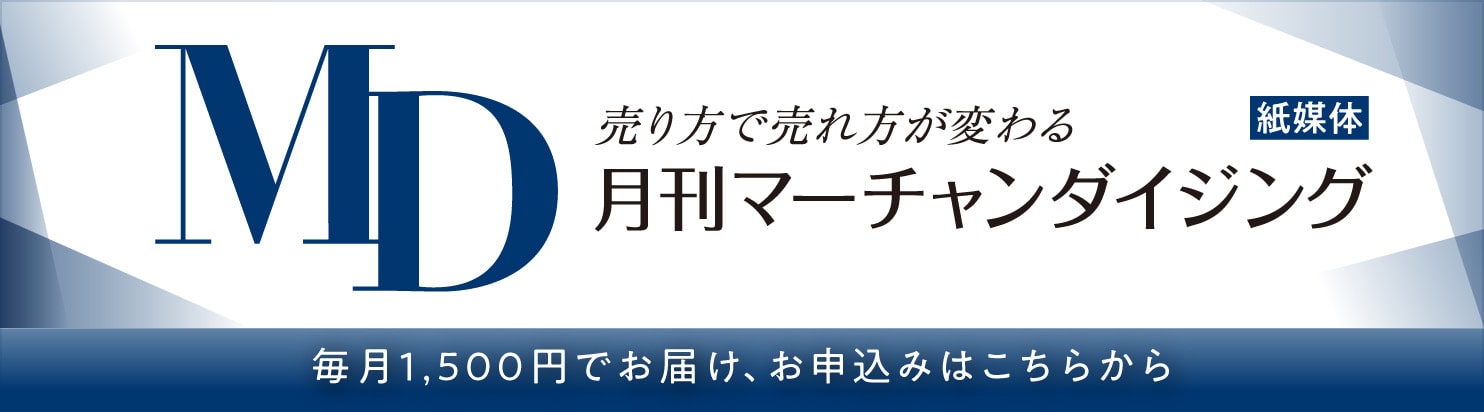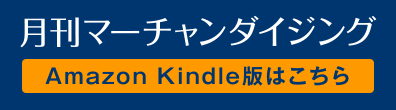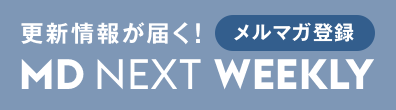ツルハHD──「売らない勇気」で築く信頼とブランド価値

業界最大手のツルハホールディングスは、登録販売者を「販売担当者」ではなく「地域の健康支援者」と位置づけ、体系的な教育・研修制度を整備。
新人教育から法定研修、スキルアップ研修までを一貫して行い、知識と実務を連動させた「継続的学習」を促進している。

現場では、JACDSガイドラインを組み込んだアプリ「健康ナビゲーション」を活用し、受診勧奨を含めた正確な判断を支援。一方で、濫用防止や過剰販売に対しては「売らない判断」を尊重する。
短期的な販売よりも顧客の信頼を優先する姿勢が、ツルハの「選ばれる店」づくりを支えている。
富士薬品──「Google以上、ドクター未満」を掲げる専門家制度

全国1,300店舗のドラッグセイムスを展開する富士薬品は、登録販売者資格を基盤にした「専門家制度(HCC・BCC・NCC)」を構築。電子顧客台帳システムと連動したカウンセリング体制を整え、専門家配置店では年間720万円の粗利増を実現している。
厳格な等級制度と教育体制(Off-JT×OJT)によって「質」を担保し、
スペシャリストとして接客に専念できる働き方を制度化。「AI以上、ドクター未満」という理念のもと、人材育成を企業戦略の中心に据えている。

JACDS──塚本会長が語る「登録販売者の社会的使命」
日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)の塚本厚志会長(マツキヨココカラ&カンパニー副社長)は、
登録販売者を「地域の孤独・孤立をなくす存在」と位置づける。
業界団体として、スイッチOTCやOTC類似薬の制度設計に取り組む一方、
資格者の継続的配置と資質向上を重視。
検査薬のOTC化など、生活者のセルフケアを支える仕組みづくりを進めている。
登録販売者を、薬の販売だけでなく地域コミュニティの接点として育てる――。
その方針は、業界全体の方向性を象徴している。
登録販売者の「再定義」が始まった
3社の事例に共通するのは、登録販売者を「制度上の資格」から「顧客接点を生み出す専門職」へ再定義する動きだ。人を育て、仕組みで支え、地域に根差す。
ドラッグストア各社がこの数年で進めてきた変化は、単なる業務改革ではなく、人材戦略の進化そのものといえる。
今後、登録販売者の力量がチェーンの競争力を左右する時代が訪れる。
その現場で何が起きているのか。詳細は「月刊MD note版」で!
- 【登録販売者大活躍時代】ツルハが登録販売者とともにつくる、「選ばれる店」とは
- 【登録販売者大活躍時代】「Google以上、ドクター未満」目指すドラッグセイムスの専門家制度
- JACDS会長 塚本厚志氏「登録販売者には地域の孤独・孤立をなくす存在になってほしい」